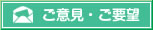主な活動
2018年第2回定例会に提出した文書質問
2018年第2回定例会で、以下の文書質問を提出しました。
【文書質問】
- 原田あきら (東京都の最低賃金について)
- 斉藤まりこ (都営住宅について・公衆浴場の利用券について)
- 藤田りょうこ (ヤングケアラー支援について)
- 原のり子 (学校のブロック塀などの安全対策について・通学路の安全対策について・障害者グループホームの都加算制度の見直しについて・放課後等デイサービスの報酬変更について)
- 白石たみお (日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて)
- 里吉ゆみ (医療的ケア児の通学保障について)
- とくとめ道信 (板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について)
- 尾崎あや子 (国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて・ヘルプマークについて)
- 和泉なおみ (都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について)
2018年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 原田あきら
質問事項
一 東京都の最低賃金につい里吉ゆみ、
一 東京都の最低賃金について
全国労働組合総連合は2015年から2016年にかけて北海道・岩手・福島・秋田・青森・山形・宮城・新潟・埼玉・静岡・愛知・大阪・広島の13道府県で「労働者がふつうの暮らしをするにはどのくらい費用がかかるのか」を明らかにするため、最低生計費について調査を行い、昨年結果を発表しました。現在ではさらに福岡県が加わり、14道府県で調査が行われています。
なお、この調査で言われている「ふつうの暮らし」とは以下の基準です。
・ 25平方メートルの1DKアパートに住み、家賃は各地域の最低価格帯の物件。通勤には、公共交通機関を利用する地域と、自家用車を利用せざるをえない地域とがある。
・ 冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、掃除機、石油ストーブなどは、量販店の最低価格帯で購入する。
・ 1か月の食費は、約30,000円から40,000円。昼食は、男性はコンビニなどでお弁当を買うケースが多く(1食あたり500円)、女性は弁当を持参が多い。飲み会・ランチは月2回から3回行っている。
・ 衣服は、男性は背広2着から3着を、女性はジャケット2着とスカート3着から4着を着回す。
・ 帰省などを含めて1泊以上の旅行は年に2回から4回で、1回当たりの費用3万円から4万円。月に2回から4回は、恋人や友人と遊んだり、ショッピングに行ったりして、オフを楽しむ(1回2,000円)。
この調査でとりわけ重要な点としては、ひとり暮らしの若者がふつうに暮らすためには、全国どこでも月額22万円から24万円ほど(税・社会保険料込み)が必要との試算結果が出たことです。年額に換算すると約270万円前後。試算の月額を、賃金収入で得るとすると、時給換算で1,300円から1,400円前後(中央最低賃金審議会で用いる労働時間=月173.8時間で除した)となり、一般の労働者の所定内労働時間に近い月150時間で時給換算した場合には、ほぼ1,500円に達します。
この調査は現在の地域別最低賃金の加重平均額848円との差が大きく、最低賃金額と必要な生計費が大きく乖離していることを明らかにしたものです。
東京都に近い自治体ではさいたま市で調査が行われ、月額24万2,000円、時給で1,400円から1,600円が必要という結果になりました。
Q1 現在、東京都の最低賃金は958円であり、都内で1日8時間、1ヶ月20日間働いても15万円程度、年収も184万円程度にしかなりません。
現在の東京都の最低賃金額について妥当と言えるか、都の認識を伺います。
Q2 東京都で労働者がふつうの暮らしをするのに必要な最低賃金額を把握するため、都として最低生計費を調査することが必要と考えますが、都の認識を伺います。
最低賃金は中央最低賃金審議会が夏頃に示す目安をもとに、地方最低賃金審議会によって審議され、決定されます。
日本共産党都議団は47都道府県に対し、最低賃金の引き上げのため、国に申入れや要望を行っているかアンケート調査を行いました。その結果、11の道府県で要望を行っていることがわかりました。
新潟県、大阪府、福岡県では国に対し、最低賃金の改善を求める要望、意見書を知事名で提出しています。
Q3 政府はかつて、政府や経団連も含めた合意目標で2020年までに加重平均1,000円にするとしていました。しかし、昨年3月にまとめた働き方改革実行計画では年限が消え、「年率3%程度をめどに引き上げ、1,000円を目指す」に後退しました。「年率3%程度」では加重平均1,000円到達は2023年までずれ込みます。
食料品、日常生活に欠かせない消耗品など、値上がりを続けており、毎年の最低賃金の改定でも追いつかず、実質賃金は下がり続けています。
東京都における人間らしい働き方を実現するためにも、国に対し最低賃金引き上げを都として要望すべきと考えますがいかがですか。
Q4 最低賃金引き上げと合わせて、中小・零細企業に向けた支援制度の創設・拡充を国に求めるべきですがいかがですか。
鳥取地方最低賃金審議会では藤田鳥取大教授が座長のもと、審議会公開にふみきりました。傍聴者の存在が審議を活性化させていると伺っています。こうした中、鳥取県では国が示した「目安」よりも引き上げ額が2年連続で多くなっています。
一方で東京地方最低賃金審議会は一部傍聴が可能なものの、全面公開ではなく、具体的な審議の様子は傍聴ができません。
Q5 議論の活性化や情報公開の観点からも、東京地方最低賃金審議会の全面公開を都として求めることが必要と考えるがいかがですか。
原田あきら議員の文書質問に対する答弁書
一 東京都の最低賃金について
A1 最低賃金の仕組みは、労働者の生活の安定や経済の健全な発展に寄与するものであり、その額は、法に基づき、公益・労働者・使用者の三者の代表が審議し、地域の労働者の生計費や賃金、企業の支払い能力を考慮して、国が決めることとなっています。
都は、この制度が適正に運用されるべきと考えています。
A2 東京都の最低賃金の決定に当たっては、東京労働局長が毎年、賃金実態を把握することを目的とした調査を実施しています。
A3 最低賃金は、法に基づき、地域の労働者の生計費や賃金、企業の支払い能力を考慮して国において決めることとなっており、都としてはこの制度が適切に運用されるべきものと考えています。
A4 国においては、中小・零細企業の生産性向上を支援することで、各企業の事業場内における最低賃金の引き上げを図る制度を有しています。
A5 東京地方最低賃金審議会については、国の規程により、「会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は会議を非公開とすることができる。」とされています。
都としては、この規程に基づき、国の責任において審議会が運営されていると認識しています。
以 上
2018年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 斉藤まりこ
質問事項
一 都営住宅について
二 公衆浴場の利用券について
一 都営住宅について
貧困と格差が広げられるアベノミクスの政策のなかで、安心して住むことができる都営住宅のニーズがますます高まっています。住宅確保要配慮者については、単身高齢者だけでも今後10年間で100万世帯の増加が見込まれるなど、安心して暮らせる住宅セーフティネットとしての都営住宅の役割が一層求められています。2018年5月の一般募集の応募倍率は、足立区では20倍から40倍のところが多くあり、中には100倍を超えるところもある状況です。
そのなかで、足立区での都営住宅の管理戸数のこの数年間の推移をみると、2011年3月末の管理戸数31,338戸から、年々減り続けて、2017年3月末には30,090戸と、合計で1,248戸も減っています。これまでも、建て替えのタイミング等で年ごとに戸数が増減することもありましたが、2011年以降は減少し続けています。
「もう10年も申し込みをしているのに都営住宅に入れない」という高齢の方や、シングルマザーでもなかなか入れないという声がたくさんある中で、足立区民は都営住宅の新規増設をくり返し訴えてきました。ところが、実際には新規増設どころか、約1,200戸も減っている現状に、区民の不安の声が届いています。
Q1 足立区内の都営住宅の管理戸数が1,200戸以上も減っている理由をお答えください。
Q2 減少した管理戸数を元に戻す計画はありますか。ないとしたらその理由は何ですか。
Q3 元の管理戸数を維持することを求めますが、いかがですか?
次に都営住宅の使用承継制度について伺います。
都営住宅のニーズが高まるなかでも新規増設がされない状況のもとで、現在の入居者を追い詰めているのが、使用承継制度の厳格化です。私は足立区の都営住宅にお住まいの方々から、「この制度を改善してほしい」「せめて配偶者だけでなく、一親等までの承継を認めてほしい」という声がたくさん寄せられています。
足立区内の50代のある男性は、80代の母親の介護のために、仕事を辞めざるをえなくなりました。母親は認知症を患い、精神状況も不安定なために、日常生活の中で離れられる時間がない状況です。3時間ほどのデイサービスに行く日もありますが、その時間だけで働ける仕事は見つからず、いまは貯金の切り崩しと母親の年金で暮らしています。男性は、自分が60歳になる前に母親が亡くなることになれば、収入がない中で、住まいからも追い出されることになることについて、非常に大きな不安に苛まれながらすごしています。
都内では、過去には使用承継が認められずに、都営住宅から追い出され、近所の公園でホームレスの状態になって、近隣住民に発見されたということもありました。
Q4 都営住宅の厳しい使用承継の制度があらたな貧困を生み出している状況をどう認識していますか。
Q5 現状を改善するために、使用の承継をせめて一親等まで認めるべきですがいかがですか。
わが党がこれまでも、この問題について繰り返し改善を求めていますが、東京都は「入居者と非入居者間の公平性のため」と繰り返しています。2016年9月に行われた都市整備委員会で、使用承継が認められない理由はなぜか、というわが党からの質問に対して、都は「入居者と非入居者間の公平性を著しく損なうもの」と答弁をしました。
Q6 わが党は、資格要件を満たしながら都営住宅に入れない都民が多くいることを踏まえて、新規増設をするべきだと、都民の声とともに繰り返し求めています。その声に背を向けて、新規増設を行わない東京都こそが、「入居者と非入居者間の公平性」を損なわせているのではありませんか?都民のニーズに応えて、都営住宅の新規増設を行なうことを求めますが、いかがですか?
60歳未満で病弱の方が使用承継をする際に求められる診断書について伺います。
60歳未満でも使用承継が認められるケースの中に、「病弱者」という条件があります。その状況を証明するために、医師の診断書が必要とされていますが、都立病院か公社病院の診断書しか認められていないことに、「かかりつけ医の診断書も認めてほしい」という切実な声があがっています。
足立区内には都立病院も公社病院もなく、比較的近い駒込病院や墨東病院、東部地域病院でも、自宅から病院までは電車を乗り継いで1時間以上かけて行かなければなりません。このことが病弱者の方々に大きな負担を強いています。
都立病院と公社病院の診断書だけを認めることについて、昨年3月の都市整備委員会でのわが党の白石たみお都議の質問に対して、都市整備局は「制度の趣旨を踏まえた診断ができるよう、組織的に周知を図るということで徹底している」という答弁をしています。しかし、「周知徹底」といっても、3、4枚のA4のペーパーを10年間に2度送付しているというだけということが明らかになりました。そのQアンドAには「あくまで医学的見地から患者の病状を記載していただくもの」と記されています。
Q7 あくまでも医学的な見地に立って、「疾患の程度、ぐあいや日常生活に与える影響などを可能な限り記載」することが求められているのなら、むしろ普段から患者の病状を把握しているかかりつけ医のほうが正確に判断ができるのではないでしょうか?認識をお伺いします。
Q8 また、病状が重い人ほど、遠くの病院にいくことが困難であることを東京都はどのように認識していますか?
Q9 病弱者の使用承継にあたって、かかりつけ医など、必要な病院やクリニックに、都立病院等と同様に制度の趣旨を説明した書類を送付のうえ、その診断書を認めることを求めますが、いかがですか?
次に期限なしの子育て世帯の募集について伺います。
今年1月から期限なしの子育て世帯の都営住宅の募集が毎月行われるようになったことは重要な前進です。非正規雇用の広がりのなかで、低廉に安心して住める住宅のニーズは若い世代でも高まっています。また団地の高齢化が進む中で、若い世代が入居して住み続けられるようにしてほしいという声は高齢の方々からも多く寄せられています。
しかし、募集に出される部屋は比較的低倍率の住戸を中心とされているため、その多くは多摩地域に偏り、23区での募集はわずかしかありません。足立区でもほんの数戸の募集があるだけです。
Q10 都心で働く子育て世代や共働き世帯が増えている状況を踏まえて、また、どこの団地でもソーシャルミックスを進めて、地域の活性化につなげるためにも、毎月募集の子育て世帯向けの都営住宅に所在地の制限をなくすことを求めますが、いかがですか?
さいごに、「病死等の理由で発見が遅れた住宅」への入居募集の方法について伺います。
「病死等の理由で発見が遅れた住宅」への入居募集の方法が変わり、一般募集と一緒になったことで、応募できる機会が減ってしまったという声が多く上がっています。いわゆる「事故住宅」は、これまでは一般募集とは別に、年3回、都庁か東京都住宅供給公社の窓口で直接受け付けていました。一般募集と一緒にしたことで、周知が進み、郵送での受付もできるようになりましたが、一般募集か「病死等の理由で発見が遅れた住宅」かどちらかを選ばなくてはならないために、年間あたりの申し込みができる機会は7回から4回へと減ってしまいました。
Q11 募集の機会を維持するためにも、「病死等の理由で発見が遅れた住宅」は、一般募集とは申し込みの機会を分けたうえで、周知の徹底と郵送での申し込みの受付を行なうべきだと思いますが、いかがですか?それができない場合は、その理由も教えてください。
二 公衆浴場の利用券について
区市が高齢者を対象に発行している銭湯の入浴券は、外出支援やコミュニティの形成にも大変役立ち、足立区でも「ゆ〜ゆ〜湯」入浴証が多くの高齢者に親しまれています。しかし、銭湯の廃業が相次ぐなかで、入浴券が支給されても利用できない地域があります。
足立区の中川地域では、中川3丁目にあった銭湯が2年前に廃業になり、いまでは住民は隣接している葛飾区まで足を延ばして銭湯を利用しています。しかし、足立区の入浴証は使うことができません。銭湯に行くことをあきらめてしまった方々も多くいます。一方で、同じ足立区の小台宮城地域では、隣接している北区の銭湯で足立区の入浴証を使うことができます。区市の対応がまちまちであるために、住んでいる地域によってサービスが利用できるところとできないところに差が生じています。
2015年12月の一般質問で、隣接区のサービスの相互利用について、区市に働きかけをしてほしいと要望したわが党の小竹ひろ子都議の一般質問に対して、都は「入浴券配布における隣接区市間の相互利用について、すでに検討を依頼しており、引き続き働きかけを行なってまいります」と答弁しています。
Q1 高齢者の入浴券配布における隣接区市間の相互利用について、区市への働きかけと相互利用の状況は現在、どのようになっているでしょうか。
隣接区のサービスの相互利用ができれば、利用者にも浴場振興にもメリットがあります。都民・高齢者の公衆浴場の利用を通じての健康の増進、外出促進とコミュニティ形成の増進を図ること、そして、銭湯という日本独自の文化を守って地域活性化につなげるためにも重要な施策です。
Q2 公衆浴場振興の面からも、東京都から区市に対して、先行事例を紹介するなどして、相互利用の促進の働きかけを強めていただきたいと思いますが、いかがですか?
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書
一 都営住宅について
A1 都営住宅については、地元区市町と協議しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ適切、的確に供給するよう努めており、管理戸数については、建替え等により変動するものです。
今後とも、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たせるよう、適切に維持更新していきます。
A2 都営住宅については、地元区市町と協議しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ適切、的確に供給するよう努めています。
今後とも、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たせるよう、適切に維持更新していきます。
A3 都営住宅については、地元区市町と協議しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ適切、的確に供給するよう努めています。
今後とも、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たせるよう、適切に維持更新していきます。
A4 都営住宅への入居は、公募が原則となっています。
公募の例外である使用承継によって、長年にわたり同一親族が居住し続けることを認めることは、入居者、非入居者間の公平性を著しく損なうことになります。
このため、真に住宅に困窮する低額所得者に対して的確に都営住宅が供給されるよう、使用承継を認める範囲を、配偶者、高齢者、障害者及び病弱者に限ることとしています。
なお、使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、6か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っています。
また、特に生活保護受給世帯については、区市町の福祉部門と連携して住宅の確保に努めるなど、きめ細かい対応に努めています。
A5 都営住宅の使用承継制度は、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、高齢者、障害者など居住の安定を図る必要がある方への一層の配慮を加えた上で、承継の厳格化を求める平成17年の国の通知や平成18年の東京都住宅政策審議会の答申も踏まえ、原則として配偶者に限っています。
A6 都営住宅については、これまでも既存ストックの有効活用を図り、適切な供給や管理の適正化に努めてきました。
今後とも、社会経済情勢が変化する中で、重要な役割を果たしている都営住宅について、既存ストックの有効活用を図り、住宅セーフティネットの中核としての機能を的確に果たせるよう取り組んでいきます。
A7 都は、都立病院又は東京都保健医療公社が設置した病院に対して、病院経営本部と連携して、同本部を通じて都営住宅の使用承継制度の趣旨、承継の際に必要な診断書の記載事項やそれらを記載する理由などについて、十分な説明を行っています。
これにより、都立病院又は公社病院の医師は、使用承継制度の趣旨を理解した上で客観的で的確な診断を行い、診断書を発行するものと考えています。
A8 他の病院に長期入院中で、都立病院又は公社病院を受診することが困難な場合でも、入院中の病院の診断書により使用承継を認めることができる場合があるため、個別の相談に応じています。
A9 公募の例外である使用承継により、都営住宅への継続居住を認めるかどうかは、重要な判断となります。
この判断を行うためには、都が設置した都立病院又は都が中心となり設立した東京都保健医療公社が設置する病院の医師に、制度の趣旨を踏まえた上で的確に診断を行っていただいています。
その他の病院に対しては、都が組織的に周知徹底することは必ずしもできないと考えており、制度の趣旨について、全ての医師に理解していただくことは非常に困難です。
A10 都はこれまで、都民共有の財産である都営住宅の有効活用を図りながら、若年世帯の入居希望に応えるため、期限付きの入居制度を活用して、若年ファミリー世帯に応募資格を限定した募集を行っています。
現在、年2回、約1,500戸の募集を行い、子育て世帯の支援に努めています。
これに加え、平成30年1月から、期限付きでない若年ファミリー世帯向けの毎月募集を行っています。
A11 病死等の理由で発見が遅れた住宅については、平成29年まで、入居を希望する方が都庁及び東京都住宅供給公社の窓口に来訪した上で住宅を選び応募する直接受付を、年3回行ってきました。
平成30年2月からは、募集の公平性と応募する方の利便性に鑑み、年4回の定期募集と統合して、他の募集と同様にパンフレットに対象住戸を掲載するとともに、郵送による受付ができるよう制度改正を行っています。
この変更に際しては、平成29年10月及び同年11月の募集パンフレットに改正内容を記載し、また、直接受付に来訪された方に対してお知らせのチラシをお渡しして周知に努めています。
二 公衆浴場の利用券について
A1 都は、隣接区市間における入浴券の相互利用について、毎年、区市の公衆浴場担当者が参加する連絡会において、働きかけを行っています。
現在、19区市において、高齢者を対象に隣接する区市で利用可能な入浴券を配布する取組を実施しています。
A2 区市の公衆浴場担当者が参加する連絡会では、隣接する区市で利用可能な入浴券を配布する取組を実施している区市の事例を紹介するとともに、相互に情報共有が図れるよう、担当者の名簿を提供しています。
今後も引き続き、働きかけを行っていきます。
以 上
2018年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 藤田りょうこ
質問事項
一 ヤングケアラー支援について
一 ヤングケアラー支援について
少子高齢化、核家族化、夫婦共働きなど、子育てや介護の形も社会背景の影響を受け、一人でいくつもの役割を担う方が増えています。
団塊の世代が後期高齢者となる2022年からさらに高齢化率はあがり、2030年には都民のおよそ4人に1人が高齢者となる予想です。
高齢者介護の担い手として、まずかかわらなくてはならないのが家族ですが、働きながら、育児をしながらの介護も珍しくなく、介護をする方の健康と尊厳を持った生き方の保障が課題となっています。
介護は若者の生活や人生にも影を落としかねません。
日本ケアラー連盟が2016年に藤沢市の公立小中学校教員を対象に実施した調査では、家族のケアをしている児童生徒には「遅刻、欠席、不登校」や「提出物、学力、学習の遅れ」など学校生活への影響が見られていました。10代から難病の家族を介護していたAさんは、進学をあきらめ18歳から仕事と介護の生活で、自らも心の病を患ってしまいました。本人にとっては重い負担でも周囲には相談しにくく孤立しやすいという特徴もあります。
Q1 健やかな成長と教育の機会を保障されるべき若者が、介護のためにその権利が保障されないことについて、どう考えますか?
2012年総務省の調査によると、家族を介護する15歳から29歳は約17万7千人。若者介護を研究する立正大学の森田久美子准教授は、「家族の規模が小さくなり、少子化や晩婚化でさらに増えるだろう」とみています。
今後増えることが予測されるヤングケアラーの実態を速やかに把握し、必要な支援につなげなければ、未来を担う若者が社会で活躍する機会を失いかねません。それは、社会にとって大きな損失です。若者の未来を支える多角的な政策が必要です。
Q2 都内にはこのようなヤングケアラーが何人存在し、どのような支援を必要としているのか調査すべきと考えますが、いかがですか?
藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書
一 ヤングケアラー支援について
A1 子供たちが、家族の介護を含む家庭の事情等により、学習の機会が保障されない状況に至ることのないよう、学校において、関係機関と緊密に連携しながら、子供を取り巻く環境の改善に向けて支援を行うことは重要です。
そのため、都教育委員会は、区市町村教育委員会におけるスクールソーシャルワーカー配置の推進や、都立学校へのユースソーシャルワーカーの派遣などを通して、学校と福祉分野の関係機関との連携を支援しています。
今後とも、都教育委員会は、区市町村教育委員会と連携しながら、学校が関係機関の協力を得て、子供や家庭への支援を充実させることができるよう努めていきます。
A2 高齢者・障害児者・難病患者等の介護や看護を行っている方のニーズは、区市町村が地域の実情に応じて実施する、家族介護者の交流会や介護講座、保健師による相談等の取組を通じて、把握しています。
都は、区市町村が実施するこうした取組を、包括補助等で支援しています。
以 上
質問事項
一 学校のブロック塀などの安全対策について
二 通学路の安全対策について
三 障害者グループホームの都加算制度の見直しについて
四 放課後等デイサービスの報酬変更について
一 学校のブロック塀などの安全対策について
震度6弱の揺れを観測した6月18日の大阪北部地震で、高槻市の小学校のブロック塀が倒れて9歳の女の子が亡くなったことに、多くの方が心を痛めています。この高槻市の小学校の場合、鉄筋が塀の上部に達していなかったことなどがわかり、詳しい点検が必要になっています。改めて、地域の学校施設などの耐震や安全性について、心配する声が広がっています。学校施設については、文部科学省が耐震性について毎年調査を行なっているものの、ブロック塀や屋外プール、その他の屋外工作物は調査の対象外になっています。学校施設の耐震性について、文部科学省は6月19日、学校の安全点検等を行うよう通知し、都教委は6月20日に区市町村に依頼をしました。早急に点検と結果の公表、対応を求めます。
東久留米市立久留米中学校は、小金井街道沿いにあり正門の横には高い万年塀がたっています。小金井街道は交通量も多く、騒音や排気ガス対策としてもこの万年塀が設置されてきました。しかしかねてから、近隣住民から、危険ではないかと指摘があります。万が一、道路側に倒れた場合、歩道も人のすれ違いがやっとという狭さであり、全く逃げ場がありません。このことについて、2015年の市議会定例会において、当時市議であった私も質問しました。当時は、久留米中学校に難聴学級を設置したことから、防音対策としてもブロック塀をなくす考えはない、というのが市教委の見解でした。
しかし、このたびの事故がおき、改めて検討しなおすことが求められていると思います。都道の騒音と排気ガスの対策をとる必要があるという点からは、東京都としても対応が求められているのではないでしょうか。よって、以下の点について質問します。
Q1 学校のブロック塀をはじめとする工作物の詳細かつ、内部も含めた安全点検を、国、区市町村と協力して速やかに行い、結果を公表してください。
Q2 耐震性が十分でないブロック塀などが発見された場合は、早急に補強やフェンス、生け垣への転換などの対応がはかれるように、区市町村に対し、技術的・財政的支援を行なってください。
Q3 東久留米市立久留米中学校について、点検調査の結果、フェンスや生け垣などへの転換を図る場合、騒音や排気ガス対策を講ずることが必要です。騒音・排気ガス対策も考慮し、十分な検討を行い対応してください。
二 通学路の安全対策について
東久留米市金山町の市道1062号線と都道24号線(練馬所沢線)が交差する、第6小学校の通学路部分についての改善を求め、質問します。
この場所はかねてから、車と歩行者が接触するなどの事故がくりかえされており、いつか大きな事故が起こりかねないと住民から大変心配されています。2018年の東久留米市議会第一回定例会でもこのことが質問されています。都道側にも、カラー舗装を行なう、注意喚起の看板等をわかりやすく表示する、などの要望が出されています。市からも要望していくとの答弁がありましたが、通学路であることから、東京都として早急に以下の点について対応を求めます。
Q1 子どもたちの通学路だということがわかるように都道側にも看板設置や、カラー舗装などをおこなってください。
三 障害者グループホームの都加算制度の見直しについて
東京都は、今年の10月から、都加算制度を見直すとしています。障害者自立支援法により、国がグループホーム・ケアホームを制度化するなかで日割り制度を実施したもとでも、東京都は利用していない日は基本単価を補てんするという都加算制度で、法の欠点をカバーしてきました。これにより、グループホームの収入が安定し、グループホームが増えてきました。地域の中で過ごす、という当たり前のことが実現できるようになりつつありました。ところが、今回の都加算の見直しが行われれば、利用していない日は一日当たりの単価を下げられてしまうため、事業所の運営、そして何より、障害者の暮らしに大きな影響を及ぼすことになります。
グループホームを利用している方々の状況はさまざまです。重度の障害者が、週末は実家に帰って過ごすことで安定して暮らせるという方もいますし、常時ホームで過ごす方もいます。誰もが地域で安心して暮らしていけるように、都加算制度を後退させないよう、強く求めます。
Q1 今回の見直しにより、都内のグループホームに、実際にどのぐらいの影響が出るのか調査し、公表してください。答弁を求めます。
Q2 東京都では事業所に対する説明会をおこなっていますが、疑問と不安の声はますます大きくなっています。10月実施を前提にせず、現場および利用者家族の声を十分に聞き取る必要があると考えますが、いかがですか。
四 放課後等デイサービスの報酬変更について
放課後等デイサービスは、学齢期の障害児が放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や自立促進、また居場所づくりとして必要不可欠なものです。障害児が安心して利用できることが重要です。
今年度から、区市町村が行う判定に該当する児童の割合に応じて、事業所の報酬区分が決まることになりました。国は判定の基となる指標について、障害児の状態像を勘案したものとしています。該当する児童が半数を超えると区分1、それ以下であれば区分2となります。とくに区分2になった場合、報酬の大幅引き下げ、人員配置加算(児童指導員等加配加算)も一人しか認められず、多くの事業所が減収になり存続の危機に見舞われています。判定は区市町村が行いますが、それぞれの自治体で対応に差もあり、国が示した判定における指標についても問題が指摘されています。特別支援学校に通う、重度判定をされている肢体不自由児でも非該当になっており、保護者の間でも混乱が生じています。正しい判定にもとづき、支援を行なうことができるのか、関係者からも問題を指摘されています。
今回の変更は、放課後デイサービスの事業所が増加するなか、国としても「利潤を追求し支援の質が低い事業所」への対策としています。しかし、すでに、「利潤追求」型の事業所は、今回の改定により、利用者への対応も不十分なまま早々と撤退したり、報酬が相対的に高い区分1にするために、利用者を選別するなどの動きをみせています。そうしたなか、良心的な事業所は、区分2になってもこれまでどおり利用者を大事にした運営に努力をしていますが、年間数百万円の減収になると見込む中、事業所を存続できる見通しがない状態です。よって、以下の点について質問します。
Q1 厚労省通知(2018年2月13日)では、指標の判定に準ずる状態について区市町村が判断するにあたり、「障害児の状態を判断するにあたり、利用中の放課後等デイサービス事業所に対してヒアリング等を行うことは差し支えない」としています。また、3月2日の通知では「報酬区分の導入当初の措置として、平成30年3月31日時点において現に存する事業所にあっては、平成30年4月1日時点の在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定すること。また、導入後3月経過後は、3月における障害児の延べ人数により算出すること」としています。
これにもとづき、区市町村が事業所のヒアリング等を実施したのか、当初の時点と3か月後でどのような対応がなされたのか、都として実態を調査し、把握してください。そして、公表してください。
Q2 放課後等デイサービスの報酬、および、区分の指標の見直しを国にはたらきかけてください。
Q3 良質な事業所が撤退しないよう、都としての放課後等デイサービスへの支援を検討してください。
原のり子議員の文書質問に対する答弁書
一 学校のブロック塀などの安全対策について
A1 学校施設の維持管理については、文部科学省の平成27年10月30日付27文科施第375号「学校施設の維持管理の徹底について(通知)」に基づき、学校設置者が実施しています。
今回のブロック塀等の緊急点検は、6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、都教育委員会が区市町村教育委員会に対して、同月20日から同月29日までの間でブロック塀等の安全点検を行い、結果を報告するよう依頼したものです。その結果については、取りまとめて7月5日に公表しました。
また、6月29日には文部科学省から、外観に基づく点検に加えて設計図書等による内部の点検も行い、その結果を報告するよう依頼がありました。これを受けて、区市町村教育委員会に対し、改めてブロック塀等の安全点検の実施と結果報告を依頼し、取りまとめて文部科学省へ報告しています。
今後とも、国や区市町村教育委員会と連携し、学校施設の安全対策に努めていきます。
A2 公立小中学校における学校施設の安全管理等は、設置者である区市町村が実施することとなっています。
ブロック塀等の対策につきましては、国とも連携しながら、対応を検討していきます。
A3 公立小中学校については、安全点検の結果、塀の危険性を指摘された場合は、設置者である区市町村が対応しています。
今後とも、学校施設の安全対策について、国や区市町村教育委員会と連携していきます。
二 通学路の安全対策について
A1 都は、通学路において学童の安全を確保するため、カラー舗装等による歩行者部分の明示や、防護柵の設置による歩車道の分離、注意を促すための看板の設置などに取り組んでいます。
東久留米市金山町の市道1062号線と都道24号線が交差する交差点については、これまでも、市や交通管理者などと調整し、注意喚起の看板設置など、安全対策に取り組んでいます。今後も引き続き関係機関と協議しながら、安全性の確保に努めていきます。
三 障害者グループホームの都加算制度の見直しについて
A1 都は、障害者グループホームの事業者が、質の高いサービスを提供できるよう、国の報酬に加え、都独自の補助を実施しています。
今回の見直しは、障害者の高齢化や障害の重度化等を踏まえ、事業者が職員を手厚く配置し、充実した支援を行えるよう、補助単価を変更するとともに、質の向上のための国加算を取得した場合には、その加算額が事業者の収入に直接反映される仕組みに改めるものです。
事業所の収入への影響は、利用者の障害の程度、職員体制、国や都の加算の取得によって異なるため、事業者説明会においては、知的障害、身体障害、精神障害の障害種別ごとにモデル的なケースを想定し、現行の収入と見直し後の収入を提示しています。
A2 今回の見直しに当たっては、東京都社会福祉協議会の身体障害者福祉部会や知的発達障害部会のほか、東京都精神障害者共同ホーム連絡会などの関係団体へのヒアリングを、平成29年8月から12月にかけて、合計13回実施しています。
また、事業者を対象にした説明会を、平成30年1月から8月にかけて合計4回開催しており、その中で、今回の見直しは、国加算額が事業者の収入に直接反映される仕組みに改めるものであることや、その取得要件などを説明するとともに、個別の事業者からの問合せに対しても対応しています。
さらに、利用者の状況や事業運営の状況等について、事業者から聞き取りを実施しています。
なお、見直し実施時期については、事業者が職員配置や国加算取得のための準備期間を十分に取れるよう、平成31年1月に変更することとし、平成30年7月に区市町村及び事業者へ周知しています。
四 放課後等デイサービスの報酬変更について
A1 国は、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、これまで一律の単価設定だった放課後等デイサービスの基本報酬について、新たに障害児の状態像を勘案した指標による報酬区分を設定しました。
障害児の状態像の指標による判定に関しては、区市町村が実施するものですが、平成30年4月1日までに、利用する全ての障害児に対する指標による判定を行うことは困難であるため、国の通知において、平成31年3月31日までは、行動援護の利用者である場合など、区市町村が認めた場合も指標の判定に準ずる状態として、指標対象児とみなすことができるとされています。
事業所が国の報酬改定に基づき、平成30年4月以降3か月間の児童利用延べ人数による報酬区分の再申請を行う際に、区市町村が障害児の状態像の指標による再判定を行うかどうか、また、事業所にヒアリングを行うかどうかなども、事業の実施主体である区市町村の判断により行われるものとなっています。
放課後等デイサービス事業所に係る平成30年度報酬改定の影響については、平成30年5月、国が調査しています。
A2 都は、平成29年11月に、平成30年4月の報酬改定に向け、放課後等デイサービスについて、「障害の程度や特性に応じた支援内容を適切に評価し、サービス提供の実態に即した報酬単価とすること」等を、国に緊急要望しました。
報酬改定では、放課後等デイサービスについて、新たに障害児の状態像を勘案した指標による報酬区分が設定されましたが、肢体不自由のある児童や比較的重度の障害のある児童等の受入れを更に促進していくため、都は、平成30年6月に、「肢体不自由のある児童や重度の障害のある児童等の受入れに対する評価を更に充実するなど、サービス提供の実態に即した報酬水準となるよう一層の改善を行うこと」等を、国に対して要望しています。
A3 放課後等デイサービスは、国の法令に基づく全国一律のサービスであり、基本的には、国の給付費により運営されるものです。
都としても、引き続き、事業者が安定した事業運営を行うことができるよう、国に要望していきます。
以 上
2018年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 白石たみお
質問事項
一 日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて
一 日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて
日本体育協会(現日本スポーツ協会、以下、日体協)の本部である岸記念体育会館の移転に対しては、都が都市計画公園整備を名目に敷地を購入し、移転費用を支払う、移転先も神宮外苑のスポーツクラスター形成にも資するなどとして都有地をあてがい、容積率や高さ制限も大幅に緩和するなど異例の優遇をおこなってきた。この問題について都と、森喜朗元首相をはじめとした自民党政治家との協議の記録が次々と明るみになり、特定の政治家によって都市行政がゆがめられたのではないかという疑惑が高まっている。
日本共産党都議団は、今年の第一回、第二回定例会でこの問題について都にただしてきたが、そのなかで疑問がますます強くなっている点、これまで時間の制約から質問できていなかった点についてお尋ねする。
Q1 わが党の情報公開請求で、岸記念体育会館の移転、神宮外苑のまちづくりに関する政治家との協議について、5月11日に新たな文書が都から提出された。そのなかには、森氏との2度目の面談記録、内田茂・高島直樹自民党都連顧問との面談記録がふくまれていた。この三つの文書について都は、執務室内に未整理の状態で保管されていたファイルの中にとじられており、3月29日以降に発見されたと考えられるとしている。一方、森氏との最初の面談記録(2012年5月15日付)や、内田・高島氏と間をあけずに会う予定であることが記録されていた文書(同10日付)は、予算案に公園の用地取得費等を計上するにあたって整理をして把握したということである。
森氏との最初の面談記録や内田・高島氏と間を開けずに会う予定であることを記録していた文書は、どのような状態で保管されていたのか。
整理されていたのか、未整理の状態だったのか。ファイルに保管されていたのか。ファイルに保管されていた場合、そのファイル名は何か。それぞれお答えいただきたい。
Q2 3月の都市整備委員会の質疑において、上野雄一都市整備局技監は「国策」を実現するためには働きかけは当然だとの答弁をされたが、この国策とはいったい何を指しているのか。また、その「国策」とは、いつどのようにして決まったのか。
Q3 上野技監の言う「文部大臣を経験された方」は森元首相、「文部大臣の政務官を経験された方」は萩生田光一氏をさすのでよいか。「文部大臣を経験された方」に相談する必要性は何か。また、「文部大臣の政務官を経験された方」に相談する必要性は何か。
Q4 内田氏に、岸記念体育会館の移転や神宮外苑のまちづくりについて説明、相談していたことの理由として、国政への提案や要求などで重要な役割を果たす自民党都連の幹事長という立場だったということをあげている。自民党都連の幹事長が行う「国政への提案や要求」は誰に対して、どのように行われるのか。また、政府に対しておこなうのか、それとも自民党などの国会議員に対して行うのか。
Q5 神宮外苑のまちづくりは、国立競技場の建て替えが契機である、と都はしている。それならば、都と国立競技場を所管する文科省が協議を進めればよいと考えられるが、なぜ、自民党政治家の協力や理解が必要なのか。
Q6 神宮外苑のまちづくりについて、森元首相、萩生田光一元代議士(当時)、内田・高島自民党都連顧問は、それぞれどのような「協力」をしてもらったのか。
Q7 神宮外苑のまちづくりについて、森元首相、萩生田光一元代議士(当時)、内田・高島自民党都連顧問にはなぜ「理解」してもらわなければならないのか。理解しなければ不都合となる理由について、それぞれお答えいただきたい。
Q8 6月8日の都市整備委員会で、佐藤都市整備局長は、神宮外苑のまちづくりについて「事前の協議調整」を行ってきたとしている。森氏、萩生田氏、内田・高島氏との話し合いも、「協議調整」ということでよいか。
Q9 6月8日の都市整備委員会で、佐藤都市整備局長は、「都市整備局では、今回の神宮外苑に限らず、羽田空港の国際化、3環状道路の整備など、重要な政策の案件を常に抱えているが、特に重要な案件については国などとの理解、協力が不可欠という場合が多々あり、そのときは、必要に応じて、案件が固まらない時点でいろんな方を巻き込んで、多くの方々に理解を求め、協力を求める」のが実態だということだが、自民党都連幹事長に対して、現在もこのように理解と協力を求めることをやっているのか。また今後もやっていくのか。
Q10 神宮外苑以外に、特に重要な案件で、国などとの理解、協力が不可欠なため、案件が固まらない時点で自民党都連幹事長に理解を求め、協力を求めて説明した課題があるのか。ある場合は、その課題をお答えいただきたい
Q11 羽田空港の国際化、3環状道路の整備では、自民党都連幹事長に理解と協力を求めて説明しているのか。
Q12 平成27年1月7日付都市整備局作成文書「神宮外苑地区のスポーツクラスター実現に向けた建設局への要請について」では、「当局は、歴代副知事の指導の下、JSC敷地、都営霞ヶ丘アパート敷地、外苑ハウス相互の敷地を整序することにより、岸記念体育会館が移転可能となる土地の確保に向けて、関係者と調整を重ねてきた」と書いている。
ア いつから関係者との調整を開始したのか。
イ 歴代副知事とはだれか。
ウ 「敷地を整序する」とはどういう意味か。
エ 岸記念体育会館が移転可能となるには、なぜ敷地の整序が必要だったのか。
Q13 2012年12月にJSCが提出した企画提案書では、JSC等のオフィス床面積が2.6ヘクタールとされている。そのうち、JSCが使用する面積はどのくらいだったのか。JSC以外にどのような団体・企業の入居を想定していたのか。日体協が入ることは、想定の一つになっていたのか。
Q14 2013年9月にJSCから日体協へ、JSC等を先行整備し、日体協新会館を後発整備とする案を提案したとあるが、なぜ後発整備としたのか。
Q15 2016年2月に日体協・JOCが提出した企画提案書では、日本青年館・JSC本部棟のオフィス床面積は6千平米へと縮小されている。JSCは変更届をいつ提出したのか、オフィス床面積の縮小についてどのように説明しているのか。
Q16 2013年5月の都市計画変更で明治公園こもれびテラス部分が明治公園から削除されたが、その理由は何か
Q17 削除された時点で、こもれびテラス部分について、都は、道路や広場など何らかの利用方法を考えていたのか。それとも当時としては何も考えられていなかったのか。利用方法を考えていた場合、それは何か。
Q18 都が、外苑ハウス、JSCと結んだ協定書の中にある第3者として、日体協は想定されていたのか。
Q19 2017年12月14日の知事ブリーフィング「岸記念体育会館の移転の手法選択について」にある四つの手法の検討はいつからいつまで行われたのか。
一民間マンションにすぎない外苑ハウスが、神宮外苑のまちづくりに早くから参画していた形跡があることも不思議である。
Q20 2011年8月19日付「岸記念体育会館に係る今後の方向性について」では、神宮外苑エリアの状況についてという項目で、「外苑ハウスの地権者は動いても良いと言っているのか」「そのように言っている」との会話がなされている。外苑ハウスと協議しているのはなぜか。いつからどの部局が協議を開始したのか。外苑ハウス敷地をめぐり、文科省、当時の都スポーツ振興局から何か要請はあったのか。それぞれお答えいただきたい。
Q21 「外苑ハウスの地権者は動いても良いと言っているのか」と尋ねているのは、当時の佐藤広副知事だが、なぜ副知事が、外苑ハウスの状況についてわざわざ聞いているのか。
Q22 外苑ハウスが自らの敷地内で建て替え等を行うことは理解できるが、「動く」とは別の場所に移転することと考えられるが、なぜ「動いても良い」という外苑ハウスの意向を把握していたのか伺う。
Q23 神宮外苑のまちづくりについて、この時点で、都は外苑ハウスとも協議していたのか。
白石たみお議員の文書質問に対する答弁書
一 日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて
A1 いずれも、執務室内に未整理の状態で保管されていたファイルにとじられていました。ファイル名は、特に付けられていません。
A2 平成23年2月15日に、超党派のラグビーワールドカップ2019日本大会成功議員連盟が、国立霞ヶ丘競技場を8万人規模のナショナルスタジアムとするなど、明治神宮外苑地区の都市計画や周辺環境整備を含めて一帯のスポーツ施設を再整備すべき旨を決議しています。
また、平成23年6月24日には、スポーツ基本法が公布され、この法律に基づき平成24年3月30日に定められたスポーツ基本計画では、オリンピック・パラリンピック等大規模な国際競技大会の招致・開催等について目標が示され、国立霞ヶ丘競技場等の施設の整備・充実等についても定められています。
国策とは、こうした決議などを踏まえた、新国立競技場の整備とその周辺一帯の再整備を指しています。
A3 「文部大臣を経験された方」、「文部大臣の政務官を経験された方」については、お尋ねのとおりです。
神宮外苑地区のまちづくりの契機となった国立競技場の建替えは、文部科学省が所管する独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の事業であり、都もこれと連動して、神宮外苑地区のスポーツクラスターの実現を目指してまちづくりに取り組んできていることから、文部科学省関係者でもある両氏に説明を行ったものです。
A4 自由民主党東京都支部連合会の幹事長が、都の行う国政への提案や要求に関して、どのようなことを行っているか等については、お答えする立場にありません。
なお、神宮外苑地区のまちづくりは、「10年後の東京」への実行プログラム2011や「2020年の東京」計画に位置付けたスポーツクラスターの形成を図るものであり、国立霞ヶ丘競技場の建替えやオリンピック・パラリンピック競技大会招致という国家プロジェクトとも連動した政策であることから、その実現に向けては、国、地元自治体、関係者などの理解と協力が不可欠であり、都として、自由民主党東京都支部連合会の幹事長など関係者へ必要な説明を行ってきました。
A5 神宮外苑地区のまちづくりは、「10年後の東京」への実行プログラム2011や「2020年の東京」計画に位置付けたスポーツクラスターの形成を図るものであり、文部科学省が所管する独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の事業でもある国立霞ヶ丘競技場の建替えやオリンピック・パラリンピック競技大会招致という国家プロジェクトとも連動した政策であることから、その実現に向けては、国、地元自治体、関係者などの理解と協力が不可欠であり、都として、関係者へ案件や状況などに応じ、必要な資料を用いて、必要な説明を行ってきました。
A6 神宮外苑のまちづくりについて、森氏らにより、どのような協力がなされたかについては承知していません。
なお、森氏らに対しては、当時、神宮外苑の再整備について、都から必要な説明を行い、理解を頂いたものであり、具体的な協力を求めたものではないと考えています。
A7 都は、神宮外苑地区におけるスポーツクラスターの形成について、「10年後の東京」への実行プログラム2011や「2020年の東京」計画に位置付け、国立霞ヶ丘競技場の建替えやオリンピック・パラリンピック競技大会招致という国家プロジェクトとも連動し、都の政策として取り組んできました。
その実現に向けては、国、地元自治体、関係者などの理解と協力が不可欠であり、都として、案件や状況などに応じ、必要な資料を用いて、必要な説明を行ってきました。
森氏は元文部大臣であり、当時、日本ラグビー・フットボール協会会長、及び平成24年2月に設置された国立競技場将来構想有識者会議の委員という立場、萩生田氏は元都議会議員であり元文部科学大臣政務官という立場、内田氏は自由民主党東京都支部連合会の幹事長という立場、高島氏は都議会自由民主党顧問という立場にあったので、神宮外苑の再整備について、都から必要な説明を行ったものです。
A8 平成30年6月8日の都市整備委員会においては、岸記念体育会館の移転・建替えに関する日本体育協会との事前の相談、調整などを念頭において答弁を行いました。
また、同日の委員会において、森氏らに対して、神宮外苑の再整備について、都から必要な説明を行った旨も答弁しており、それは協議調整にはあたらないと考えています。
A9 羽田空港の国際化、三環状道路の整備など、重要な政策目的の実現に向け、国において的確な措置がとられるよう、関係府省庁に提案要求をするとともに、案件や状況などに応じて、自由民主党東京都支部連合会など、国政等の関係者に説明を行っています。
今後も、政策目的の実現に向け、理解と協力を頂けるよう、説明を行っていきます。
A10 国への提案要求では、計画が決定されていない案件も含めて、関係府省庁に対して提案要求をするとともに、課題の解決や施策の確実な実現に向けて理解と協力を頂けるよう、案件や状況などに応じて、国政等の関係者に説明を行っています。
A11 羽田空港の国際化、三環状道路の整備など、重要な政策目的の実現に向け、国において的確な措置がとられるよう、関係府省庁に提案要求をするとともに、案件や状況などに応じて、国政等の関係者に説明を行っています。
A12のア 神宮外苑地区では、国立競技場の建替えを契機として、スポーツ・文化・交流の魅力に富んだスポーツクラスターの形成を目指し、関係者が相互に連携・協力してまちづくりを進めています。
その一環として、都は、新国立競技場等への多くの観客を安全・快適に移動させるための歩行者動線と人だまり空間の早期確保等を図るため、土地区画整理事業を行うこととしました。
土地区画整理事業の実施に向けて、平成26年6月頃には、地権者であるJSCや外苑ハウスとの調整を行っていたと思われます。
A12のイ 都市整備局は、平成23年9月頃から、国立競技場の建替えを契機として、周辺区域の再編整備について検討を開始し、その中で、岸記念体育会館の神宮外苑地区への移転についても検討を始めています。
このことについては、当時の佐藤副知事と村山副知事に説明しています。
平成26年3月及び同年9月には、神宮外苑地区における土地区画整理事業の実施について、当時の安藤副知事と秋山副知事に説明しています。
A12のウ 「敷地を整序する」とは、土地区画整理事業により、土地の形状や位置の変更などを行うことを想定していたものです。
A12のエ 都は、神宮外苑地区におけるスポーツクラスターの形成に向けて、スポーツ関連団体の集約を図ることを念頭に、日本体育協会に対し、岸記念体育会館の移転を検討することを提案しました。
その後、都は、東京2020大会に向けて新国立競技場等への多くの観客を安全・快適に移動させるための歩行者動線や人だまり空間を早期に確保するとともに、土地の形状や位置の変更などによりスポーツ関連団体の本部機能の集約に必要な用地の確保を図るため、土地区画整理事業による敷地整序を行うこととしたものです。
A13 平成24年12月にJSCから提出された企画提案書では、新事務所棟には日本青年館のホテルやホールと共に、JSC事務所等のオフィスが計画されていますが、JSCが使うオフィス面積やJSC以外の入居の計画などは記載されていません。
なお、当時、JSCは、日本体育協会及び日本青年館との合築による新事務所棟の整備に関する検討をしており、JSCは協会の入居も想定していたものと思われます。
A14 当初、JSCは、日本体育協会及び日本青年館との合築による新事務所棟の整備を検討していました。
JSCは、早期の新事務所棟の建設を望んでいましたが、日本体育協会が移転に向けた意思決定に至らなかったことなどから、日本青年館・JSC本部棟を先行整備し、日本体育協会の新会館を後発整備とする案を提案したものと認識しています。
A15 JSCは、日本体育協会の新会館を後発整備としたことにより、オフィス部分の計画規模を縮小し、平成27年2月に企画提案書の一部見直し報告書を都に提出しました。
A16 都は、神宮外苑地区地区計画の決定に合わせて、公園区域を再編し、バリアフリーに対応した歩行者動線や人だまり空間の確保等を図るため、平成25年6月に東京都市計画公園明治公園の変更を行いました。
こもれびテラスの区域については、この変更により、都市計画公園から削除しています。
A17 平成25年6月に、国立競技場の建替えを契機として、神宮外苑地区地区計画が決定されています。その決定に合わせて公園区域を再編し、バリアフリーに対応した歩行者動線や人だまり空間の確保等を図るため、都市計画公園の変更を行っています。
その際、こもれびテラスの区域については、地区計画上の地区施設である広場などの整備を図ることとしました。
A18 都有地の譲渡が予定される第三者として、日本体育協会を想定していました。
A19 移転の手法については、平成26年9月から平成27年3月までの間に検討していました。
A20 外苑ハウスから最初に相談を受けた時期については、記録がなく不明ですが、都市整備局は、平成23年9月頃から国立競技場建替えを契機とした周辺地区の再編整備についての検討を開始しており、その中に、外苑ハウスの区域内での移転・建替えを行う案が含まれていることから、都市整備局は、当時、外苑ハウスから相談を受けていたと思われます。
なお、平成24年7月に外苑ハウスから都に対して出された要望書では、耐震性などに課題があり、以前から建替えについて検討してきたことが記されています。
外苑ハウスをめぐり、文部科学省や、当時のスポーツ振興局から都市整備局に何らかの要請があったとの記録は、見当たりません。
A21 都市整備局は平成23年9月には、国立競技場の建替えを契機とした周辺区域の再編整備について検討を開始しており、その中に、外苑ハウスの区域内での移転・建替えを行う案が含まれていることから、お尋ねの同年8月19日の副知事説明の際にも、そのことを念頭に置いて、外苑ハウスについての報告を行っていたものと思われます。
A22 外苑ハウスから最初に相談を受けた時期については、記録がなく不明ですが、都市整備局は、平成23年9月頃から国立競技場建替えを契機とした周辺地区の再編整備についての検討を開始しており、その中に、外苑ハウスの区域内での移転・建替えを行う案が含まれていることから、都市整備局は、当時、外苑ハウスから相談を受けていたと思われます。
なお、平成24年7月に外苑ハウスから都に対して出された要望書では、耐震性などに課題があり、以前から建替えについて検討してきたことが記されています。
A23 平成23年8月19日時点での、都と外苑ハウスとの神宮外苑のまちづくりについての協議記録は、見当たりません。
以 上
質問事項
一 医療的ケア児の通学保障について
一 医療的ケア児の通学保障について
医療的ケアが必要な子どもたちの通学保障について伺います。現在、都教育委員会では、医療的ケアを理由にスクールバスに乗車できなかった子どもを対象に、専用通学車両の運行を準備しています。
Q1 そこで伺いますが、現在何人のお子さんが専用通学車両の利用を希望しているのでしょうか。
9月からの運行を予定していると聞いていますが、車両と同乗する看護師の確保が間に合うかどうか、関係者や保護者の皆さんも心配しています。特に看護師の確保について、学校現場でも大変苦労していると伺っています。
Q2 都教育委員会としても、看護師の確保を進めるべきだと思いますが、現在どのような取り組みを行っているのか伺います。
Q3 専用通学車両は、医療的ケアを必要とする子どもの中でも、スクールバスへの乗車以外に現在何らかの方法で通学している子どもが対象となっています。今後、通学手段がないためにやむを得ず訪問教育を受けている子どもも対象にすべきだと思いますが、今後の予定はどのようになっているのか伺います。
Q4 現在都立特別支援学校全体で、登下校も授業中も保護者が付き添っているのは、何人いますか。その中には安定すれば授業中の付き添いがいらなくなる子どももいると思いますが、人工呼吸器対応のため、付き添いが必要な子どもはどれくらいいるのか合わせて伺います。
2016年に行った医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の学校生活及び登下校における保護者等の付き添いに関する実態調査を示した、文部科学省の2017年4月7日付けの事務連絡によると、保護者が学校に付き添っている理由で最も多いのが「人工呼吸器の管理」でした。それぞれの教育委員会の判断で、一律に人工呼吸器の管理を保護者対応とし、学校に配置している看護師が対応していないとしている場合があるが、「文部科学省としては、人工呼吸器の管理を含めた特定行為以外の医行為について、個々の児童生徒等の状態に応じてその安全性を考慮しながら、対応可能性を検討することと従前から通知しているところであり、教育委員会においては、個別に対応可能性を検討すること。」としています。
Q5 都教育委員会では、人工呼吸器の管理について2年間のモデル事業を実施していますが、モデル事業の終了まで待つのではなく、順次個別に対応可能性を検討するべきです。都教委の見解を求めます。
人工呼吸器の子どもも含めて医療的ケアの必要な子どもも学校に通って授業等の教育を受ける権利を保障するためには、看護師の確保とともに看護師の研修や教員なども増やすことが求められています。必要な体制を整備することを強く求めます。
Q6 同事務連絡には、国の特別支援教育就学奨励費(負担金・補助金・交付金)の対象となる範囲について、安全性等の観点からスクールバスや公共交通機関が利用できない場合など、都道府県、市町村または校長が適当と判断した場合には、通学に要する交通費(本人経費)においてタクシーや介護タクシーの利用料金を対象にすることが可能である、とされています。この対象として、今後も保護者の付き添いで登下校する子どもや訪問教育の子どものスクーリングや授業の一環として行われる移動教室や職業訓練なども含まれると思いますが、見解を伺います。
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書
一 医療的ケア児の通学保障について
A1 都立肢体不自由特別支援学校に在籍する通学籍の児童・生徒のうち、医療的ケアが必要なためスクールバスでの通学対象となっていない者を対象に、都教育委員会で平成30年5月に意向調査を行った結果、専用通学車両の利用希望者は174人です。
A2 専用通学車両に乗車する看護師の確保を進めるため、都教育委員会は、募集のチラシの作成・配布や、新聞折込広告の配布、就職相談会への出展、関係団体への協力依頼などを行っています。
A3 専用通学車両の導入により、本人の体調や健康状態の事情ではなく学校への通学手段の確保が困難なために、やむを得ず訪問教育の対象となっていた児童・生徒は、医療的判断等により通学車両への乗車が困難とされた場合以外は、通学できるようになります。
A4 都教育委員会で平成30年6月に調査を行った結果、都立特別支援学校において、医療的ケア実施のために保護者が登下校及び授業中のいずれも付き添っている児童・生徒は27人です。
このうち、人工呼吸器の管理のために保護者が付き添っている児童・生徒は14人です。
A5 都教育委員会は、都立特別支援学校において、医師、保護者、学校の連携の下、安全の確保を第一に、人工呼吸器の管理を適切に実施するための校内体制や実施方法等を検討することを目的として、平成30年度から2年間のモデル事業を実施しています。
本事業での検討を踏まえた上で、全ての都立特別支援学校において安全かつ適切に人工呼吸器の管理を実施するための条件や留意点等をまとめることとしています。
A6 文部科学省から発出された「公立特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の学校生活及び登下校における保護者等の付添いに関する実態調査(平成29年4月7日付事務連絡)」を踏まえ、都教育委員会は、平成30年度から、訪問学級在籍生のスクーリングに係る交通費を含め授業の一環として行われる移動教室や職業訓練にタクシーや介護タクシーを利用する場合についても、一定の条件の下、就学奨励事業の対象としました。
また、保護者の付添いが必要な児童・生徒の登下校については、専用通学車両の運行を準備しています。
以 上
2018年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 とくとめ道信
質問事項
一 板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について
一 板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について
板橋区のハッピーロード大山商店街を分断することになる特定整備路線の補助26号線について、地域住民からは、建設計画の中止を求める裁判をはじめ、反対の声や疑問の声が広がっているとともに、今後の見通しについて不安の声が寄せられています。そこで、今後の建設計画に関わって、次のような項目について、質問を行います。
Q1 2020年までに建設を完了するとなっていますが、物理的に厳しいとみられています。2020年までに完成できるかどうかの判断は、いつ行うのですか。
Q2 現時点での進捗状況はどうなっていますか。最新の境界立会率、用地取得率を示してください。
Q3 26号線道路建設のために、ハッピーロード大山商店街のアーケード部分で撤去しなければならない部分は、具体的に何メートルになるのかを示してください。
Q4 工事に関わってアーケードを一時的に撤去しなければならない部分が発生するのかどうか、また発生するとすれば、具体的にどの場所になるのかを示してください。
Q5 26号線の建設に関わって、道路と交錯する部分のアーケードの撤去が問題になっています。アーケードの撤去は、道路事業の一環として行われるのですか。それとも、再開発事業の一環として行われるのですか。あるいは両方ですか。撤去のスキームについて教えてください。
撤去の手法が決まっている場合、都の負担の内容と割合について教えてください。撤去の手法が決まっていない場合は、いつごろまでに決まるのか、見通しを教えてください。
Q6 26号線建設に関わるアーケードの撤去、再整備にかかる、すべての経費の見込みの総額と、そのうち東京都が責任をもって、補償できる対象工事、費用について示してください。
Q7 東上線の立体化に伴うハッピーロード大山商店街のアーケードへの影響について、具体的な図面も含めて、その範囲と工事経費の総額、そのうち東京都が補償できる工事対象と費用額、その割合について示してください。
Q8 26号線建設は、大山駅周辺のまちづくりである、「クロスポイント」とは、工事の進捗状況と関係するのかどうか。関係するとすれば、どういった部分が関係するのか、具体的に示してください。
Q9 万が一、26号線の建設計画が予定より遅れた場合、工事完了時期を遅らせるのか、それとも今後のあり方について見直すのかについて、示してください。
とくとめ道信議員の文書質問に対する答弁書
一 板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について
A1 特定整備路線である補助第26号線大山区間は、震災時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域において延焼遮断帯を形成し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る極めて重要な都市計画道路です。
引き続き、関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力を得ながら、平成32年度の整備に向け、取り組んでいきます。
A2 補助第26号線大山区間について、平成30年3月末時点の境界立会率は約95パーセント、用地取得率は約9パーセントです。
A3 平成28年度の現地調査の結果によると、商店街のアーケード全長約560メートルのうち、補助第26号線大山区間の事業施行区域にあるのは、約170メートルです。
A4 アーケードの除却等に関わる工事は、物件移転等補償契約締結後に、所有者である商店街振興組合に行っていただくため、一時的に撤去が生じるか否かは、商店街振興組合の判断によります。
A5 商店街のアーケードについては、現在事業中の補助第26号線の道路事業によるものとして、その一部を所有者である商店街振興組合において撤去していただきます。
当該除却等に必要な経費は都が補償します。
速やかに補償金の概算額等を説明できるよう、補償金算定等を進めていきます。
A6 商店街のアーケードについて都が補償する工事は、補助第26号線の整備に支障となる約170メートル分の除却工事や、当該除却工事に伴い影響が生じる道路区域外の部分の改修工事、機能回復工事等です。
その除却等に要する補償金額については、今後、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」等の関係規定に基づき算定します。
A7 東武東上線大山駅付近の連続立体交差事業については、平成30年2月に説明会を開催し、都市計画素案に関する概略図等を示しました。今後は法令に基づき都市計画案を作成し、案の縦覧・意見書の提出等の都市計画手続を進めて、平成31年度に都市計画決定することを予定しています。
素案では、ハッピーロード大山商店街のアーケードの一部が都市計画の区域に掛かることが想定されていますが、都市計画決定後に詳細な影響範囲を把握するための用地測量等を行い、必要に応じて適切に対応していきます。
A8 補助第26号線大山区間については、平成27年2月に事業に着手しました。
一方、大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業は、平成29年10月に都市計画決定され、今後事業化が見込まれています。
市街地再開発事業の都市計画の区域内には補助第26号線の一部が含まれていることから、それぞれの事業の進捗状況に合わせて、工事等の必要な調整をしていきます。
A9 特定整備路線である補助第26号線大山区間については、引き続き、関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力を得ながら、平成32年度の整備に向け、取り組んでいきます。
以 上
平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて
二 ヘルプマークについて
一 国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて
今年度、国民健康保険料の制度が広域化することによりほとんどの自治体で国保料(税)の値上げが行われます。今でも払いたくても払えない状況が広がっています。私の活動地域である武蔵村山市では、生活費まで差押えようとする強引な徴収がまかり通る、法令違反を行おうとしている事例が明らかになりました。
国保税の滞納分を分納して支払っていた70歳の男性は、病気の奥さんと引きこもりの息子の3人家族で、月の収入は17万円のみです。家賃は6万9千円、医療費が1万円、月額2万円超の国保税が払えず、給料の17万円を差し押さえると市から言われました。
Q1 国税徴収法に基づいて給与等の差押え禁止の基準はどうなっていますか。3人家族の場合はいくらになりますか。
Q2 3人家族の場合の生活保護法における生活扶助の基準となる金額は、19万円です。今回の事例は法令違反になると思いますが、いかがですか。
Q3 日本共産党倉林明子参議院議員は2月1日、今回の事例を国会で取り上げ、安倍首相は「差押えによって生活が極めて困難にならないよう、各市町村の判断により差押えの対象としないことができる仕組みがある。各市町村に周知を図りたい」と答弁しました。直近で「国保料(税)の差押え」等について、都に届いている文書はありますか。あれば、どんな内容で、いつ届いているのかうかがいます。
Q4 都内の区市町村が法令違反の差押えを行っている情報や事実があれば、都はどのように対応しますか。区市町村への指導は行うのか、うかがいます。
Q5 国保料(税)などの滞納がある人への、行政の最大の支援は「生活の建て直しを応援する」「病気で十分に働けない状況であれば、まずは病気をなおすことを支援する」のではありませんか。国会で加藤勝信厚生労働相は「国保の滞納には個々の事情に即したきめ細かな対応が重要。生活を困窮させる恐れがあるときには、差押えの対象外とすることなどが大事」と答弁しています。
都も、この立場に立ち「都民の生活再建」を位置づけ、区市町村のいきすぎた徴収・差押えをなくすために役割を果たすべきです。そのためにも区市町村が滞納者にどのような対応をしているのか実態を調べるべきです。その際、区市町村の徴収担当者からの聞き取りだけではなく、差し押さえられた当事者・滞納者からの聞き取りも必要だと思いますが、いかがですか。
Q6 国保料(税)、都税の差押えの判断について、都は「生存権優先」なのか、「納税義務が優先」にしているのか、うかがいます。
Q7 東京都は、区市町村の徴収担当者に徴収業務の進め方についての資料に基づき、研修をしていますが、「差押え」については、どのような内容で研修をしているのですか。
Q8 売掛金の差押えが行われていますが、商売をしている方々にとっては、売掛金の差押えは、商取引の信用問題にかかわり、取引の継続を脅かすものになります。売掛金の差押えは中小業者の「廃業」につながります。都は売掛金の差押えについて、どのように認識していますか。商売をつぶすようなことはやめて、商売・生活の再建のために支援すべきですが、いかがですか。
二 ヘルプマークについて
難病がある方から「外見は健常者と何もかわらないが、通勤も仕事もできない状況です。難病である自分の病気のことを多くの人に知ってほしい。病院にいくため電車やバスを乗り継いでの移動は、いつ体調が悪くなるか、いつも不安です」「ヘルプマークがほしいと思って調べたが、ヘルプマークがもらえる窓口が近くにないので、なんとかしてほしい。東京都に郵送で送ってほしいとお願いしたが、できないと言われた」と相談がありました。
電車などでヘルプマークを知らせる広告や、駅のホームなどでポスターなども貼られています。しかし、認知度はまだ高くはありません。
2012年に東京都が、全国に先駆けてヘルプマークを作り普及を行ったことは重要です。ヘルプマークを配布している場所、窓口は増えていますが、まだまだ不十分です。
Q1 ヘルプマークの配布実績について、うかがいます。
Q2 ヘルプマークを知らせるためのポスターなどの啓発・普及のための作成部数について、うかがいます。
Q3 ヘルプマークを配布しているのは、都営地下鉄の駅や都営バスの営業所、日暮里・舎人ライナーの駅務室、ゆりかもめの駅務室、多摩都市モノレール駅務室、東京都心身障害者福祉センター、都立病院、公益財団法人東京都保健医療公社の病院等となっています。
配布場所も増やしていただいていますが、まだ不十分です。とりわけ、多摩地域での配布場所が一部地域に限られています。外見は健常者と変わらなくても、長い時間、電車やバスに乗って移動するのが困難な人たちがヘルプマークを必要としています。一番、身近な区市町村の役所と連携し配布できる窓口をつくるべきだと思いますが、いかがですか。
Q4 ヘルプマークの配布窓口が、近くにない場合には郵送(料金は本人負担)も行うべきですが、いかがですか。
Q5 ヘルプマークにシールがついており、伝えたい情報などを記入し貼るようにと説明があります。裏面にシールを貼ってしまうとヘルプマークのマークが片面だけになってしまいます。見開きにできるように改善し、その見開きの部分に「伝えたい情報」を記入できるようにすべきですが、いかがですか。利用者の要望を良く聞き、改善を求めるものです。
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書
一 国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて
A1 国税徴収法第76条第1項では、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)のうち、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押さえることができないとされています。
(1) 給料等につき源泉徴収される所得税に相当する金額
(2) 給料等につき特別徴収される住民税に相当する金額
(3) 給料等から控除される社会保険料に相当する金額
(4) 滞納者及びその者と生計を一にする親族に対し、生活保護法に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合における扶助の基準額を勘案して政令で定める金額
(5) 給料等の金額から、(1)から(4)までの合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額。ただし、その金額が(4)の金額の2倍に相当する金額を超えるときは当該金額
(4)において政令で定める金額は、国税徴収法施行令第34条により、一月ごとに滞納者本人につき10万円、また生計を一にする親族がある場合は、一人につき4万5千円を加算した金額とされています。
生計を一にする3人の世帯の場合、国税徴収法施行令第34条に基づき算定される一月当たり19万円に、(1)から(3)まで及び(5)の金額を加えた額が、給料等の金額を上回る場合には、差押えができないことになります。
A2 今回の事例について、武蔵村山市に確認したところ、当該世帯は住民登録上2人世帯であること、この場合の差押禁止額は14万5千円に源泉徴収所得税に相当する金額等を加えた額になることを前提に納付交渉を行ったと聞いています。
A3 平成30年1月30日に厚生労働省が開催した「全国高齢者医療・国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議」において、保険料(税)徴収業務における留意事項として、給与等の差押禁止の基準や、滞納処分の停止における生活困窮の基準等が示されています。
A4 国民健康保険法第4条第5項では、都道府県は国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとされています。
また、同法第106条第1項では、都道府県知事は区域内の区市町村等に対して、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができると規定しています。
区市町村が行う国民健康保険の事務は自治事務であり、地方自治法第245条の6では、自治事務の処理が法令の規定に違反している場合には、都道府県は区市町村に対し、是正の勧告をすることができるとされています。
都は、区市町村の事務が法令の規定に違反していると認められる場合には、これらの関係法令に基づき必要な指導・助言等を行います。
A5 区市町村は、国民健康保険の保険料(税)の滞納者に対して、納付相談により生活状況を把握し、必要に応じて保険料の分割納付を案内するなど、きめ細かな対応を行っています。
都は、区市町村の滞納整理事務が適切に行われるよう、区市町村の徴収担当職員を対象に研修を行っています。
A6 国民健康保険の保険料(税)が滞納となった場合には区市町村が、また、都税が滞納となった場合には都が、それぞれ、滞納者に対して督促や催告を行うほか、納付相談により生活状況を把握し、必要に応じて猶予制度を案内するなど、きめ細かな対応を行っており、その上で、財産があるにもかかわらず納付しない場合は、法令に基づいて差押えを行っています。
また、滞納処分を執行できる財産がない場合や、滞納処分を執行することにより滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合等には、滞納処分の執行停止を行っています。
A7 都が、区市町村の徴収担当職員向けに行う研修では、国税徴収法に示されている差押えの要件や制限など、滞納処分に関する法令の規定や参考となる判例等について説明しています。
A8 国税徴収法基本通達では、差し押さえる財産の選択は、第三者の権利を害することが少ない財産であること、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること、換価が容易な財産であること、保管又は引揚げに便利な財産であることに十分留意して、行うものとしています。
国民健康保険の保険料(税)が滞納となった場合には区市町村が、また、都税が滞納となった場合には都が、滞納者の生活状況を十分に把握した上で、差押えの判断を行っています。
二 ヘルプマークについて
A1 都は、平成24年10月から都営大江戸線においてヘルプマークの配布を開始し、現在は、都営交通、ゆりかもめ、多摩モノレール、都立病院等に配布場所を拡大しており、配布数は、平成30年3月末までの累計で、約21万9千個となっています。
A2 ヘルプマークの普及啓発のための取組として、駅や公共施設等へのポスター掲示、電車やバスの優先席やホームドアのステッカー標示、イベントでのチラシの配布やリーフレットを活用した企業内研修などを行っています。
都は、平成30年3月までに、ポスター約3万8千枚、ステッカー約3万枚、チラシ約24万5千枚、リーフレット約1万枚を作成しました。
A3 都は、区市町村においてヘルプマークの作成・配布を進めるため、ヘルプマークの作成経費を包括補助で支援しています。
また、「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」を作成し、区市町村によるヘルプマークの活用を促進しています。
現在、13の区市でヘルプマークを作成・配布していますが、今後とも、区市町村の取組が進むよう支援していきます。
A4 ヘルプマークの配布に当たっては、円滑にヘルプマークを取得できるよう、書類等の提示を不要とし、ヘルプマークを必要とする都民が、配布窓口で申し出ることで、配布しています。
また、配布窓口に行くことが困難などと相談を受けた場合には、個別に郵送するなど柔軟に対応しています。
A5 ヘルプマークは、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成しています。シールは、必要に応じて、周囲に伝えたい情報を記入し、裏面に貼って使うことができます。
また、「伝えたい情報」を記入できるものとしては、都が標準様式を定め、区市町村が作成・配布しているヘルプカードがあり、災害時等の緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し、周囲の人に伝えるツールとして活用されています。
ヘルプマークは周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるサインとして、ヘルプカードは必要な支援等を周囲に伝えるツールとして、併用して活用するなど、個々の事情にあった方法を選択することができます。
以 上
2018年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 和泉なおみ
質問事項
一 都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について
一 都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について
京成押上線四ツ木・青砥間の連続立体交差化事業が進められています。この事業は東京都が主体となって、葛飾区および京成電鉄が連携して行うもので、京成四ツ木駅から青砥駅までの2.6キロメートルのうち、立石駅を含む2.2キロメートルを立体化するものです。これにより11の踏切がなくなり、永年の懸案であった平和橋通りの渋滞も大幅な改善が期待されます。
同時に、鉄道が高架化されることによって、高架下や周辺に、あらたに利用可能な土地・空間が生まれます。利用可能面積は、仮に幅10メートルとして、それに新たに高架化される2.2キロメートルをかけると22,000平方メートルに及びます。しかも、立石駅から青砥駅方面の急カーブを是正するために、従来の線路をさらに北側に移動させるため、新たに生まれる土地が幅30メートル近くになり、駅に続く繁華な場所にうまれる新たな空間として、その活用方法に注目が集まるのは当然です。
高架化によって生み出される利用可能な面積のうち15%は地元自治体が利用できることになっていますが、これはあくまで新たにできた高架施設に対して賦課されるべき公租公課分とされています。しかし、第一にこの京成押上線高架化事業のうち、86%が都と区の負担とされており、国民の税金で賄われる公共事業なのであり、第二に高架化事業の目的に「線路により分断されていた沿線市街地の一体化を図る」とうたわれていることからも明らかなように、まちづくり事業なのです。
したがって、地元住民としては15%の枠にとらわれずに高架化利用全体について意見や要望を述べることは、認められるべきと考えます。
Q1 高架下の利用について地域住民の要望・意見が尊重されるべきと考えますが、都の見解を伺います。
私は、この文書質問趣意書の提出にあたり、立石地域を中心に120名以上の方々に要望をお聞きしました。その結果、じつに多様な要望があることがわかりました。最も多かったのは駐輪場です。長く続く高架化工事期間中に最もしわ寄せを受けるのが、立石駅を中心とする自転車利用者だからです。次に保育園、さらに集会所の要望も強いものがあります。立石地域の三つの町会が町会事務所を持っていないという切実な事情もあります。立石駅に隣接して生まれた幅広い空間を利用してのバスロータリー、タクシー乗り場の設置を望む声も強いものがありました。若い方たちの要望としては、ミニサッカー練習場や音楽スタジオが多数あげられたことに注目させられました。
これらの多様な住民要望をどのように尊重し、まちづくりに生かしていくのかが、都や区に問われています。
Q2 東京都が事業主体者として区や京成電鉄と連携しながら、高架下利用についての丁寧な説明会を開くべきではないかと考えますが、見解を伺います。
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書
一 都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について
A1 連続立体交差事業により新たに創出される高架下空間は、貴重な都市空間であり、地域のまちづくりの視点から、有効に活用することが重要です。
都はこれまでも、連続立体交差事業の実施に当たり、地元要望や多様なニーズを踏まえて、地域のまちづくりに資する高架下利用計画を策定してきました。
今後、京成電鉄押上線(四ツ木駅~青砥駅間)連続立体交差事業においても、地元要望等を踏まえ高架下利用計画を策定していきます。
A2 連続立体交差事業の高架下利用に当たっては、事業の進捗に応じて、都が、地元区市及び鉄道事業者と高架下利用検討会を設置し、調整を行っています。
検討会では、地元区市が把握した地域住民の要望などを踏まえ、沿線のまちづくりとの整合や地域ニーズなどを勘案し、都が中心となって高架下利用計画を策定しています。
京成電鉄押上線(四ツ木駅~青砥駅間)連続立体交差事業の高架下利用についても、同様に取り組んでいきます。
以 上