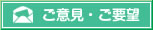主な活動
11月13日 各会計決算特別委員会 和泉なおみ都議の全局質疑
★YouTubeチャンネル(2分動画)
★質問全文(都議会速記録より)
○和泉委員 まず、下水道局に伺いたいというふうに思います。
私は、地元葛飾の水害対策について、この間、さまざまな機会を捉えて、都にただしてまいりました。今回は、内水氾濫の対策について下水道局に伺います。
まず初めに、墨田、江東、足立、葛飾、江戸川、このいわゆる江東五区における下水道局の浸水対策の取り組みと実施状況について伺います。
○和賀井下水道局長 下水道局では、東京都豪雨対策基本方針等に基づき、区部全域で時間五十ミリ降雨に対応する施設整備を基本とし、早期に浸水被害を軽減するため、地区を重点化し、施設整備を進めております。
また、浸水被害の影響が大きい大規模地下街などにおいて、整備水準を七十五ミリにレベルアップした対策を推進しております。
江東五区においては、五地区を選定しており、墨田区八広地区及び足立区小台地区の二地区で基幹施設の整備を既に完了させており、江東区木場・東雲地区、江東区大島・江戸川区小松川地区及び足立区千住地区の三地区において、幹線やポンプ所などの基幹施設の整備を進めております。
○和泉委員 江東五区においては、時間五十ミリ降雨に対応する施設を整備する重点区域として残っているのは三地区だという答弁でした。
雨水が地面にたまらないようにするために、一時的に水をためておく貯留施設と、川の水が引いたら、そこから川へ流すための雨水ポンプ、この下水道の機能というのは、内水氾濫を起こさないために非常に重要だと、大きな役割を果たしているというふうに思いますが、葛飾区内の雨水ポンプを有する施設の箇所数、そして、葛飾区内の浸水対策の取り組みについて伺います。
○和賀井下水道局長 下水道局では、葛飾区内に、小菅水再生センターや堀切ポンプ所など合わせて八カ所の雨水ポンプを有する施設を管理しております。
また、葛飾区内のこれまでの浸水対策として、平成十六年度に、葛飾区奥戸二、三丁目、東金町一から五丁目、東水元二、三丁目の三地区を対策地区として位置づけ、グレーチングや雨水ますの増設など、平成十七年度までに事業を完了しております。
○和泉委員 雨水ポンプを有する施設は八カ所、また、グレーチングや雨水ますの増設などは完了しているという答弁ですが、お聞きしましたところ、時間五十ミリ降雨に対応する施設整備ができているので、貯留施設は要らないということでした。ひたすら荒川や江戸川に流すというのが葛飾の内水氾濫対策ということになろうかと思います。
台風十九号では、荒川も水位が上がりまして、岩淵水門を閉じました。雨水をためる施設がない葛飾で、果たして下水道管だけで内水氾濫を抑えられるのかという不安があります。
ことし一月に策定された東京都豪雨対策アクションプランでは、東京都豪雨対策基本方針、これに基づいて、重点エリアとして対策強化流域と対策強化地区を選定し、おおむね三十年後を見据え、目標整備水準を示して取り組んでいくというふうになっていて、既にその取り組みも行われているところです。
一方で、国は、流域治水プロジェクトにおいて、対策の実施に必要な計画や基準などを、過去の降雨実績や潮位に基づくものから、気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮したものに見直すことが必要であるという認識を示しています。
三十年後を見据えて、目標整備水準を示すというのであれば、国が示した認識に立って、まず、気候変動の影響を考慮してシミュレーションを行う必要があると考えますが、この点についての都の見解と新たな政策の見直しの必要性などについての認識をあわせて伺います。
○和賀井下水道局長 昨年の台風十九号の激甚化する豪雨を踏まえ、これまで進めてきました施設整備の着実な推進と加速や、新たな取り組みによる強化などを取りまとめました東京都豪雨対策アクションプランを本年一月に関係局とともに策定をいたしました。
アクションプランに基づき、幹線や貯留施設の整備などの対策を加速、強化していくとともに、七十五ミリ施設整備する地区等の追加について、最新の流出解析シミュレーション技術を活用した検証を令和二年度末までに完了させます。
○和泉委員 流出解析シミュレーション技術を活用した検証を今年度末までに行うという答弁です。
きょうの質疑を通じて、荒川から東側の内水氾濫への備えとしては、ひたすら荒川や江戸川にポンプで水を流すというものであること、また、今後の対策の加速、強化のためのシミュレーションの検証がこれから行われるということがわかりました。
しかし、一たび浸水被害が発生すれば、江東五区は二百五十万人に被害が出ることが想定されているわけです。これからの水害対策は、これまでの過去の実績から災害を予測するのではなくて、今後の気候変動を見越したものにする必要があると思います。内水氾濫対策も含めて、しっかり取り組んでいただくことを求めておきます。
続いて、都立病院、公社病院の独法化についてです。
二〇一九年十二月三日、第四回定例会の所信表明で、知事は、突然、都立病院、公社病院の独立行政法人化を表明しました。
しかし、その方針がいつ決定されたのかという我が党の質問への都の答弁は二転三転し、東京都公文書条例で定められた決裁手続も行われていないという、まさにブラックボックスでした。
また、パブリックコメントを行っている最中なのに、独法化の準備のための契約手続を進めるなど、多くの都民の反対の声など聞く気もなく、都政の透明化も、都民が決める、都民と進めるという当時の公約も投げ捨てました。
都立病院ではこれまで、都民の命を守る医療を都が直接担ってきました。例えば、小児医療、周産期医療、そして感染症医療など、診療報酬では採算のとれないような医療でも、都民に必要な医療を直接提供してきたのが都立病院です。都民の命に直結することを左右する独法化という重大な判断を知事は行ったんです。
そこで、知事に伺いたいと思います。
都立病院、公社病院の独立行政法人化を決定するに当たって、そのメリット、デメリットについて、知事はご自分で他県の独法病院などに足を運び、現場を確認したんでしょうか。
○小池知事 都立病院の経営形態のあり方は、長年にわたる課題であって、検討を進めてきたわけであります。
私の就任後、平成三十年、都立病院経営委員会から提言を受けまして、都として、都立病院新改革実行プラン二〇一八を策定、経営形態のあり方につきまして、病院事業の見える化改革による課題の検証のほか、他自治体の経営形態の動向調査など、さまざまな検討を重ねてまいりました。
この間、私は、病院経営本部から、検討内容について随時報告を受けまして、必要な指示を行ってきたところでございます。
こうした一連の検討も踏まえまして、都立、公社病院の独法化に向けました今後の進め方を決定、昨年の第四回都議会定例会で、準備を開始することを表明したわけであります。
その後、第一回都議会定例会でのご議論を経まして、昨年度末、独法化の方針といたしまして、新たな病院運営改革ビジョンを確定、令和四年度内の設立を目途として移行準備を進めているところでございます。
○和泉委員 私は、現場に行ったんですか、行かなかったんですかと聞きました。長々と答弁しないでください。端的にお答えくださいね。限られた時間でやっているんですから。
知事は、結局、行ったことがないということが今の答弁でもわかりました。長々答弁しましたけれども、結果は行っていないということなんです。報告だけでは実態は見えてきません。
知事は、質の高い医療の安定的、継続的な提供などの役割を将来にわたって果たすことが独法化の目的だと答弁されています。
しかし、お隣の神奈川県立病院機構では、二〇一九年度の決算で、繰越欠損は九十九億円を超え、危機的な状況であることを法人自身が認めています。そのもとで、原則として職員の増員も認められず、医療機器の購入も、早期にコストを確実に回収できる見込みを立てるよう制約をかけられているんです。つまり、住民への医療に必要な体制づくりに制約がかかっているということになります。
ご自分で足を運んで、現場を見て、しっかり調査すれば、そういう現実がすぐ隣の県で起こっているということはわかるんですよ。
ところが、知事は、それさえせずに、報告を受けた範囲の情報だけで決断をしたと。このような重大な決断に当たっても、みずからの行動、検証を伴わずに判断する、そんなことでいいんでしょうか。知事、無責任だと思いませんか。いかがですか。
○小池知事 新型コロナウイルス感染症患者への対応に当たりましては、その時々の感染の状況を踏まえまして、都内の医療機関がそれぞれの役割に応じて患者の治療に当たってきております。
こうした中で、都立、公社病院は、関係機関等と連携を図りながら、他の医療機関では対応困難な患者を中心といたしまして、積極的に受け入れることで、都民、そして地域から求められる役割をしっかり果たしてきたと、このように認識をいたしており、責任を持って進めております。
○和泉委員 私は、現場にしっかりと足を運ぶこともなく、他県の調査をみずから行うこともなく決断をすることが無責任なのではありませんかと聞きました。答弁は、質問に対して答えていません。
そもそも知事は、報告を受けた、報告で十分だ、そのような認識のようですけれども、昨年の第四回定例会、病院経営本部長は、全ての事例を知事に報告したわけではないと答弁しているんですよ。今のやりとりだけでも、知事が都民の命を守る都立病院のことを真剣に考えているとはとても思えません。
独立行政法人は、地方公共団体がみずから主体となって直接に実施する必要のないもの、これを行うのが独法だというふうに、その法律に明記しています。
知事は、行政的医療、質の高い医療を安定的、継続的に提供する都立病院は、都が主体となって直接実施する必要がないと判断をしたということです。
知事は、コロナ対策で都立病院はどのような認識を果たしてきたと思っていらっしゃるんでしょうか伺います。
○堤病院経営本部長 新型コロナウイルス感染症への対応に当たりましては、先ほど知事もお答え申し上げましたとおり、その時々の感染の状況を踏まえまして、都内の医療機関がそれぞれの役割に応じて患者の治療に当たってまいりました。
こうした中、都立病院及び公社病院は、関係機関等と連携を図りながら、ほかの医療機関では対応困難な患者を中心に積極的に受け入れを行うことで、都民や地域から求められる役割をしっかり果たしてきたと認識をしております。
それから、知事の視察の件でございますが、既に都は、高齢者医療と研究を行います地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターを設立しております。
知事は、現地を視察するなどして、この法人の役割につきまして円滑に行われていることを確認しております。
○和泉委員 もうお願いしますよ。端的なやりとりしてください、限られた時間なんですから。
今、都立病院の認識を示されましたけれども、さらに、他の病院では受け入れ困難なケースでも、都立病院が受け皿となっているんです。例えば、認知症でよく歩き回り、介助が必要なコロナ患者の入院先、これを探すのに八病院かけ合ったけれども、どこも断られて、最後は都立病院が受け入れた、そういう事例。また、軽症であっても、高齢者で基礎疾患を持っているコロナ患者は、いつ重症化するかわからないため、なかなか受け入れ病院が決まりにくい。都立病院がそれを多く受け入れています。そういった活動は、必ずしも数字になってあらわれてきません。けれども、現場は必死に対応し続けているんです。
現場職員が心身を削りながら医療を守っていることを、知事は正面から受けとめていただきたいというふうに思います。
東京都医師会の尾会長も、現場の病院は疲れ果て、メンタルがやられる職員も出てきていると、このように話しているように、コロナ対応の長期化もあわさって、医療現場は一層深刻になっています。
しかし、そのもとでも、東京都は、独法化した後の給与や人事面についての約一時間の動画を見るように職員に求めているんです。実際に、現場はどのように視聴していたかというと、例えば日勤では、朝出勤すると、夜間の患者の状態を夜勤の看護師から聞き取ることから始まって、そこからスケジュールを組み、体温、血圧をはかり、午後は手術後の患者を受け入れ、カンファレンス、点滴、記録などをとって終わっていく。昼間は患者対応が最優先で、受け持ちの患者がいる限りとても勤務中は見ることはできない。夜勤の方は、夜十時、消灯後に見る時間がとれても、ナースコールのたびに中断しながら見たと、このように話しています。中には、夜勤後の徹夜状態で見ざるを得ない人もいました。
勤務中に見ろといわれても、見る時間はない、見ても理解できない、そういう声が出されているんです。現場からは、コロナ対応に集中させてほしい、そういう訴えが届いています。本当にそのとおりだと思います。
独法化のために現場の負担をふやしていることを、知事はどのように受けとめているんですか。知事の受けとめです。知事以外の方の答弁は要りません。知事、いかがですか。
○堤病院経営本部長 職員に対する動画での説明でございますが、このコロナ禍で、直接多数が集まって説明会を行うことができないため、動画による説明資料をつくったものでございます。
動画に対しましては、意見を聴取することといたしまして、この独立行政法人法でも、職員との意思疎通に努めることという附帯決議がなされておりますけれども、意思疎通に努めているところでございます。
それから、先ほど、認知症患者等のコロナ患者さんの受け入れについてのお話がございましたけれども、先ほど私もご答弁申し上げましたが、都立病院及び公社病院一体となって対応をいたしております。
公社病院は、公益財団法人で、東京都の政策連携団体でございます。このような団体につきましても、東京都の意思を反映して、東京都の政策で患者さんを受け入れているところでございます。
○和泉委員 コロナの最前線で頑張ってきたのが都立病院の皆さんです。医療従事者への感謝とか、都庁を青色にライトアップするとかしていますけれども、感謝するつもりがあるんだったら、職員の負担をさらにふやすようなことをすべきじゃありません。集まれないから動画でやったんだ。だったら、やめればいいじゃないですか。
さらに、知事に何を一番伝えたかったか、このことも聞きました。お話しされていたのは、知事に現場を見てほしいということです。視察に来たことはあるけれども、たくさんの人に囲まれて、私たちが話をできるようなものではなかった、そうではなく、知事には、もっと踏み込んで現場を見てほしい、どのように入院して、どのように退院しているのか、どんな患者さんがいるのか、診療報酬はどうやって点数をつけているのか、現場の実情を見に来てほしい、私たちの声を聞いてほしい。
知事、この声にどのように応えますか。知事にお聞きします。病院経営本部長の答弁は要りません。
〔堤病院経営本部長発言を求む〕
〔和泉委員「委員長」と呼び、その他発言する者あり〕
○高橋委員長 理事者に申し上げます。的確に答弁お願いいたします。
○堤病院経営本部長 知事には、何度も都立病院を視察していただきまして、都立病院の実情につきましてご理解をいただいております。
○和泉委員 知事、あなた、独法化の準備によって職員に負担をかけていることを受けとめようともしない。現場の職員から、私たちの声を聞いてほしいという訴えも、あなたには届かない。現場がこれだけ追い詰められているというのに、寄り添う思いも、語るべき言葉も持たない。そのような姿勢は許されません。
独法化に向けて、今後はどのような手順を踏むことになるんでしょうか。
○堤病院経営本部長 法人の設立に当たり、地方独立行政法人法では、法人の根本原則である定款につきまして、議会の議決を経た後に総務大臣の認可を受けるほか、法人が達成すべき業務運営に関する中期目標について議会の議決を経て定める等の手続がございます。
また、地方自治法上の施設でなくなることから、都議会の議決を経て東京都立病院条例を廃止する等の手続がございます。
なお、独法化する際には、地方独立行政法人法に基づき、都議会の議決を経て都が定める法人の定款において、設置する病院の名称や所在地を定めることとなります。
さらに、病院の組織、人事や予算など運営に必要となる事項を順次定めてまいります。
○和泉委員 今、都立病院条例は廃止されるという答弁がありました。重大なことです。今の都立病院は、独法化されると都の条例に位置づけられた存在ではなくなるということです。
都立病院条例第一条には、都民に医療を提供し、医療の向上に寄与するために、都立病院を設置すると、このようになっています。都民に直接医療を提供する、そこをしっかりと条例化して、都としての責務を明確化している、これが重要なんです。
けれども、それを廃止して、文字どおり、都民に直接医療を提供する責任を手放してしまおうということなんです。
知事は、行政的医療を継続するために独法化するといっていますけれども、そもそも行政的医療を守るというんだったら、都が直接実施するのが一番いい。知事、その単純な事実を認識するべきだと思います。
都立病院じゃなくなったら、医療の専門家はどうなるのか、これについても伺います。
都立病院の医師、看護師定数は何人でしょうか。独法化した後は、定数条例における医師、看護師は何人になるんでしょうか。医師、看護師それぞれについて伺います。
○堤病院経営本部長 平成三十一年四月一日現在、都立病院の医師の定数は九百六十三人、看護師の定数は四千二百六十五人でございます。
地方独立行政法人化した場合には、東京都職員定数条例の対象外となりますことから、医師、看護師の定数はゼロとなります。
その後、法人が定める計画数に基づき、必要な職員を配置することとなります。独自の組織、人事など各種制度の構築により、機動的に人材を確保できるものと考えております。
○和泉委員 ご答弁のとおり、人員体制についても都の定数としての位置づけはなくなって、何と九百六十三人いる医師がゼロになるんです。
ことしの予算特別委員会資料をもとにつくったグラフがこれです。(パネルを示す)全体の奉仕者であり、都民のために知事の指示のもとで働く東京都職員の医師の数は、都立病院を独法化したら、千百二十二人が百五十九人へと激減し、わずか一四%まで減ってしまいます。医療の現場がわかる職員が激減して、都の医療政策が脆弱化するのは明白です。
さらに伺います。
一度独法化をすれば、うまくいかないからといって簡単に都立病院に戻すことはできません。独立行政法人化した後、再び都立病院に戻す場合、職員の身分は公務員へと移行されるんでしょうか。いかがですか。
○堤病院経営本部長 まず、先ほどの医師の定数の件でございますけれども、病院の定数は、先ほどお答えしたとおりゼロとなりまして、法人の計画数として、より充実した医師を配置するという予定でございます。百何人に減るというのは、病院以外の部分を指しているものだというふうに理解をしております。
それから、ただいまのご質問についてでございますが、一旦、法人職員となった者が、再度、設立団体等職員となる場合の手続につきましては、地方独立行政法人法上、規定はされておりません。
○和泉委員 ですから、わかっていますよ、そんなこと。地方独立行政法人法には、職員のことも含めて独法化する手続は書かれているけど、直営にもう一回戻す手続の規定はないんです。そして、独法化の人員体制は、独法が決めるんです。
つまり、一たび独法化にかじを切ったら、今の九百六十三人の都立病院の医師、四千二百六十五人の看護師、これを初め、職員は公務員に戻ってはこられない。独立行政法人への道は片道切符だということなんです。独法化して、うまくいかなければ直営に戻せばいい、そんな話ではないということを肝に銘じる必要があります。
人員確保が困難になっているのは、先ほど例を挙げた神奈川県立病院機構だけじゃありません。既に十年前に独法化した東京都健康長寿医療センターでは、二〇一八年から一九年にかけて、医師が十四人減っています。けれども、二〇二〇年になっても一人しか補充できていません。そのために医業収益が落ちています。そうした事実にきちんと向き合うべきです。
都立病院への一般会計からの支出、繰り入れについても伺います。
先ほどお話ししたように、都立病院は、診療報酬では採算がとれなくても、都民の命や健康、暮らしを守るために不可欠な行政的医療、これを担うことを役割としています。したがって、都立病院がその使命を果たすためには、東京都が一般会計からきちんと予算を支出して、都立病院が財政的に成り立つようにすることが不可欠だ、このことは都議会の中で何度も確認してきました。
独法化に係るこれまでの検討の中で、一般会計からの繰り入れについては、どのような議論がされてきたんでしょうか伺います。
○堤病院経営本部長 地方独立行政法人法では、採算の確保が困難な医療等に係る経費につきまして、現在の一般会計繰入金と同様に都が負担する仕組みとなっておりまして、行政的医療の確実な提供が可能となるものでございます。
現在は、独法化後に会計基準が変更となることに伴う運営費負担金受け入れ後の会計処理について検討を行っております。
なお、運営費負担金額の詳細につきましては、繰出基準に基づきまして、これは、現在の一般会計繰入金と同様でございますが、収入、支出の状況によって増減するものでございます。毎年度、都議会の議決を経て決定されるものでございます。
○和泉委員 都の一般会計から繰り入れることを担保すると。このようなことをいいましたけど、ごまかさないでくださいよ。独法化の検討過程について、我が党が開示請求して入手した資料では、不採算な行政的医療の収支は一層厳しくなるとして、一般会計繰入金が将来どうなるか、ご丁寧に試算まで行っているじゃないですか。それがこのグラフです。(パネルを示す)皆さんのお手元にも資料をお配りしました。
そして、現在の行政的医療を提供し続けるだけでも、一般会計繰入金が増加するおそれがあると。そして、お配りした資料の裏面ですけれども、そのため、経営形態のあり方を検討すると、踏み込んだ表現をしているじゃないですか。
さらに、六月十九日の知事室での打ち合わせでも、都は、財政負担の軽減、独法化による効果を生かして、都の財政負担を軽減すると知事に報告されていた。このことは、ことし三月の予算特別委員会で、我が党の白石都議が指摘したとおりです。ここまでの経緯を見れば、独法化の議論は、都の財政負担を減らすことを狙って議論がスタートしているということは明らかじゃありませんか。
ことし二月の都立病院経営委員会でも、委員長は、名前だけ変わっても、相変わらず同じような税の投入が継続されるようなことでは、何のための独法化か、このようにはっきり述べているではありませんか。財政負担を減らすことが目的なのは明白です。
新型コロナウイルスの対応に尽力している現場の職員に、余計な負担をふやし、都が直接提供するべき行政的医療の責任を放棄し、一般会計からの支出の削減のために都立病院を独法化しようという姿勢は、厳しく批判されなければなりません。
コロナ禍での都民の暮らしはますます厳しさを増しています。経済的に困窮することがあっても、安心して医療が提供される環境をいかにして整えるか、このことにこそ本気で取り組むべきです。
無料低額診療は、経済的な理由によって必要な医療を受けることが困難な方に、無料または低額な料金で診療を行う事業です。私たちが繰り返し求めてきた無料低額診療は、都立病院で実施することは制度上可能かどうか、これについて伺います。
○堤病院経営本部長 無料低額診療事業は、社会福祉法の規定に基づきまして、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う社会福祉事業でございます。
この事業は、都立病院を含めまして、医療機関であれば、一定の要件を満たせば実施することができますが、都立病院は現在、要件を満たしておりません。
○和泉委員 今、条件を満たしていないと答弁した無料低額診療の要件というのは、どのような人に診療費を減免するかをまず決めること、実際に、一定数の生活困難な方を受け入れること、こういった無料低額診療を、やる気になって具体的に取り組むことで満たされるんです。したがって、やる気になりさえすればできる、そういう医療を実現させるというなら、こういうことにこそ踏み出すべきなんです。
東京民医連に加盟する病院からの報告事例を見ても、大変深刻な実態が浮き彫りになっています。七十代母親と二人暮らしの四十代男性、コロナで職を失い、所持金は一万円、糖尿病の持病があるが、支払うお金がないと告げると、かかりつけの病院から、診療を断られた、こういった事例が、いとまがないんですよ。
新型コロナ感染症でも、都立病院はその最前線で治療に当たってきました。都民の命のとりでである都立病院の独立行政法人化は撤回して、直営のままで、さらに医療を充実させていくことこそ、コロナと闘う病院の現場、感染の不安におびえる都民の願いに応える道だと厳しく指摘して、質疑を終えます。