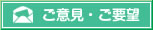主な活動
2018年第3回定例会に提出した文書質問
2018年第3回定例会で、以下の文書質問を提出しました。
【文書質問】
- 池川友一 (一 学校体育館等のエアコン設置について、 二 「ブラック校則」について、三 「学力テスト」について、 四 「カジノ型デイサービス」について 五 避難所について)
- 原のり子 (都庁舎のバリアフリーについて、二 都市計画道路建設について)
- 河野ゆりえ (プラスチックゴミの削減とリサイクル促進のために)
- 里吉ゆみ (光明学園の教育環境の改善について)
- 尾崎あや子 (一 TOKYOチャレンジネットについて、二 豊洲市場水産仲卸売場棟の北側にあるマンホールの噴出について)
- 和泉なおみ (一 都立水元公園の管理改善について、二 風疹の緊急対策について)
- 曽根はじめ (東京都におけるエイズ/HIV対策について)
質問事項
一 学校体育館等のエアコン設置について
二 「ブラック校則」について
三 「学力テスト」について
四 「カジノ型デイサービス」について
五 避難所について
一 学校体育館等のエアコン設置について
第3回定例会での共産党都議団の代表質問に知事は「学校体育館についてでございますが、体育の授業や学校行事、部活動など、子供たちが安全に活動を行う場であるとともに、避難所としての役割も担っております。猛暑による熱中症への対策として、体育館に空調設備を整備する必要があると認識をいたしておりまして、今後、都立高等学校の体育館への整備を速やかに進めてまいります」と表明しました。これは、これまでの立場から大きく飛躍した重要な答弁です。
そこでまず、都立高校の問題について伺います。
Q1 都立高校の体育館へのエアコン設置は、どのように取り組むのですか。既存の体育館、改築や改修中の体育館についてはどう対応するのですか。
Q2 期限を区切った取り組みが必要であり、そのための計画を速やかに策定すべきと考えますがいかがですか。
都立高校は、公立小中学校と比較しても特別教室へのエアコン設置が遅れています。
Q3 都立高校の特別教室はいつまでに設置するのですか。少なくとも計画を策定し、期間を区切って設置する必要があると思いますがいかがですか。
区市町村の特別教室のエアコン設置補助の根拠となっている「東京都公立学校施設冷房化支援特別事業実施要綱」は、今年度末までとなっています。
Q4 期間についてはいつまで延長するのですか。
二 「ブラック校則」について
「ブラック校則」とは、一般社会から見れば明らかにおかしい校則や生徒心得、学校独自ルールなどの総称です。
「朝日新聞」の調査では都立高校の6割で「地毛証明書」について、教育評論家の尾木直樹氏は「頭髪は身体の一部。黒髪直毛を強制するなんて人権侵害」と指摘しています。地毛証明書というのは、一般社会から見れば明らかにおかしいルールです。
さらに、ある都立高校では、地毛にも関わらず「黒く染めてこい」という生徒指導が行われたという事実を私たちは伺いました。こうした指導は大問題ですが、学校一律に基準を決め、そこからはみ出すことを悪とする生徒指導は、生徒の自尊感情を傷つけます。
Q1 知事は、一般社会から見れば明らかにおかしい「ブラック校則」など子どもの人権が侵害されている現状についてどう考えますか。子どもの人権に配慮して常に校則を見直していく必要性についてどう認識していますか。
校則など、自分たちに関わるルールを自分たちで決めていくことが主権者教育としても重要です。
ある都立高校では、髪染めの禁止と制服の導入に対し、在校生の圧倒的多数が反対の意思を表明し、生徒総会では「生徒の学校生活に関わる重要な決定をする場合、在校生及び保護者に明確な説明なしに決定、公表、実施をしないことを求める」ことを決議しました。しかし、校長の決定だからと一方的に導入されました。
子どもの権利条約第12条には「自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」とあります。
Q2 校則の見直しについて、「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化に応じまして絶えず積極的に見直す必要がある」と文部科学大臣が答弁しています。東京都教育委員会も「絶えず積極的に見直す必要がある」という認識ですか。
Q3 校則などの見直しについて、「児童生徒や保護者が何らかの形で参加した上で決定するということが望ましい」と文部科学大臣が国会で答弁しています。子どもの意見表明権を保障する上でも、主権者教育を推進する上でも、児童生徒が参加して決定することが望ましいと考えますが、いかがですか。また、児童や生徒が決定に関わるためには何が必要だと考えますか。
三 「学力テスト」について
「学力テスト」について、文部科学省は「全国学力・学習状況調査に係る適切な取組の推進について(通知)」(28文科初第197号)を出しています。
この「通知」の中で「4月前後になると、例えば、調査実施前に授業時間を使って集中的に過去の調査問題を練習させ、本来実施すべき学習が十分に実施できないなどといった声が一部から寄せられるといった状況が生じています。仮に数値データの上昇のみを目的にしているととられかねないような行き過ぎた取扱いがあれば、それは本調査の趣旨・目的を損なうものであると考えております」と述べています。
私のところにも、「事前対策として過去問題を30回やった」など、都内でも過度に過去問題をやっている実態が寄せられています。
Q1 東京都教育委員会は、こうした「調査実施前に授業時間を使って集中的に過去の調査問題を練習させ」など、国の「学力テスト」のための事前対策の実態を把握されていますか。
Q2 こうした事前対策は問題だとは思いませんか。
Q3 国の「学力テスト」のための行き過ぎた事前対策の実態が明らかになった場合、どう対応するのか伺います。
学力の定着といいながら、悉皆調査で行われ点数の公表が行われるなど、国連子どもの権利委員会から「高度に競争的」と言われる「学力テスト」のあり方に大きな問題があります。
しかも東京都の場合、国の調査に加え、東京都の調査、さらには、39区市町村(2017年度)が独自に「学力テスト」を実施しており、子どもと学校は「学力テスト」体制に汲々としています。
福井県議会は、「学力テスト」による競争によって「『学力日本一』を維持することが本県全域において教育現場に無言のプレッシャーを与え、教員、生徒双方のストレスの要因となっていると考える」ことなどに言及し「義務教育課程においては、発達の段階に応じて、子どもたちが自ら学ぶ楽しさを知り、人生を生き抜いていくために必要な力を身につけることが目的であることを再確認し、過度の学力偏重は避けること」などを求める、「福井県の教育行政の根本的見直しを求める意見書」を可決しました。
Q4 都独自の「学力テスト」のあり方が問われています。悉皆調査や結果の公表など、「学力偏重」の都の「学力テスト」の見直しが必要だと思いますが、いかがですか。
四 「カジノ型デイサービス」について
昨今、介護事業者が様々なサービスを提供するようになっていますが、その一つに「カジノ型デイサービス」と呼ばれるものがあります。
「カジノ型デイサービス」とは、麻雀、パチンコなど、風俗営業法に規定されている遊技を、デイサービス等介護保険サービスにおいて実施するものをさします。
「カジノ型デイサービス」について厚生労働省老健局振興課課長は「プログラムをどのような計画で行っているのか、時間や頻度も含めその中身については、保険給付で提供されているサービスである以上、必ず問われる」と述べています。
一方で、兵庫県や神戸市は、「カジノ型デイサービス」を実質的に規制しています。神戸市長は、適度な娯楽の活用は高齢者の心身の活性化に役立つとする一方、最近は遊技場かと思われるような事業所があり、適当とは考えられないサービスは「(介護)保険料の上昇や利用者の自己負担の増加につながる」と述べています。
Q1 都は「カジノ型デイサービス」についてどのように認識していますか。
Q2 東京都内ではどのくらいの数が存在しているのですか。
Q3 「規制」も含めて、そのあり方を検討する必要があると考えますがいかがですか。
五 避難所について
Q1 国際赤十字やNGO団体などが「人道憲章と人道対応に関する最低基準」、通称「スフィア基準」をまとめ、国際社会における人道対応の事実上の基準となっています。
スフィア基準の考え方の根底には、被災者、避難者の命と健康を守るとともに、その尊厳を守ることの重要性があります。
被災者、避難者の命と健康と同時に尊厳を守ることの重要性について、都の認識を伺います。
スフィア基準では、具体的には、生命維持に必要な水の供給量、20人に1つのトイレ設置や女性用のトイレは男性用の3倍必要などの基準、避難所での一人当たりの必要最小面積3.5平方メートルなどが定められ、政府も避難所の運営ガイドラインに参考すべき基準として紹介しています。
熊本地震では、災害関連死が200人を超え、地震での直接の被害者50人を大きく超える事態となりました。災害関連死の約半数は車中泊や避難所での生活を経られた方で、避難先での環境が要因として挙げられています。
西日本豪雨災害でも、避難所の冷房設置や段ボールベッド、間仕切りの活用など、被災者の命と健康、尊厳を守る避難所の環境整備の重要性が示されました。
Q2 避難所で、床等にじかに寝るより、段ボールベッドを活用することにより、埃等の吸引による呼吸器疾患の防止、足腰の弱い高齢者も容易に立ち上がれ、トイレなどにも一人で行きやすくなり、エコノミークラス症候群の防止にもなります。また、収納スペースの確保にも役立ちます。
避難所において、段ボールベッドの役割、重要性について都の認識を伺います。
Q3 避難所において、間仕切り等を活用し、プライベートスペースを生み出すことによって、ストレスの軽減や、プライバシーの確保などの効果があります。
避難所においてのプライベート空間の創設の重要性について都の認識を伺います。
Q4 わが党の代表質問に対し都は「都は、近年の大規模災害における避難所の運営状況等を踏まえ、良好な生活環境が確保されるよう、東京都地域防災計画に基づき、災害想定を考慮した避難所の指定、女性や子供への配慮やトイレの確保等について記載いたしました避難所管理運営の指針を区市町村向けに作成しております。今後とも、区市町村が地域の特性や実情に応じて避難所を運営できるよう、さまざまな知見も踏まえ、避難所管理運営マニュアルの作成や改定を行うよう働きかけてまいります。」と答弁しました。
区市町村が地域の特性や実情に応じて避難所を運営できるよう、さまざまな知見も踏まえ、避難所管理運営マニュアルの作成や改定を行うよう働きかける際、スフィア基準実現の立場で支援や援助を行うことが重要と考えますが、見解を伺います。
Q5 区市町村が避難所の快適性向上、被災者、避難者の命と健康、尊厳を守る立場で避難所の改善を行う際に、必要な財政的支援も検討すべきですがいかがですか。
池川友一議員の文書質問に対する答弁書
一 学校体育館等のエアコン設置について
A1 都立高等学校の体育館への空調設備の整備に向け、現在、各校の電気容量等を調査しています。今後、調査の結果を踏まえ、空調設備の設置を速やかに進めていきます。
なお、改築や大規模改修工事に既に着手している学校については、設計の変更や追加工事の実施により、可能な限り早期に空調設備が整備されるよう、対応していきます。
A2 都立高等学校の体育館への空調設備の整備に向け、現在、各校の電気容量等を調査しています。今後、調査の結果を踏まえ、空調設備の設置を速やかに進めていきます。
質問事項
A3 都立高等学校の特別教室の冷房化に当たっては、学校と相談しながら、老朽化した既存空調設備の改修も併せて実施が可能か検討しています。
その際、学校全体の空調設備の老朽化の度合いや、校舎全体の改修計画の有無などを総合的に判断し、改修工事を計画しています。
現在、平成31年度の工事予定校まで決定していますが、平成32年度以降の工事予定校についても、順次計画していきます。
A4 都は、平成26年度から、普通教室で代替できない特別教室に空調設備を整備する区市町村に対して補助を行う、「東京都公立学校施設冷房化支援特別事業」を実施しています。
本事業は、緊急対策として特別教室への空調設備整備を進めることから、5年間の事業期間として実施しています。
今後も、都内公立小中学校特別教室の空調設備整備が進むよう、期間を含め区市町村への支援策について検討していきます。
二 「ブラック校則」について
A1 教育の場においては、未来を担う子供たち一人一人の人権を尊重し、健全育成を図っていくことが大切です。
こうした視点に立ち、都立高等学校においては、生徒が社会的に自立できるよう生活習慣の確立に向け、生徒の実態に応じた校則を各校の判断で定め、基本的な生活習慣の確立を図っています。校則の見直しについては、生徒の実態や保護者の意向等を踏まえ、必要に応じて行うことが大切であると考えています。
A2 校則は、教育目標を達成するために、必要かつ合理的な範囲内で定めた、遵守すべき学習上・生活指導上の規律であり、生徒が学校生活を送る上で重要な役割を果たしています。校則の見直しについては、生徒の実態や保護者の意向等を踏まえ、必要に応じて行うことが大切であると考えています。
A3 生徒が校則を主体的に守ることができるようにするためには、内面的な自覚を促し、校則を自分のものとして捉える態度を養うことが重要です。
そうした態度を育成するためには、生徒会やホームルーム活動等を通じて校則について話し合う活動等を設けるなどして、社会規範を遵守する意識を醸成することが大切であると考えています。
三 「学力テスト」について
A1 都教育委員会は、文部科学省の平成28年4月28日付「全国学力・学習状況調査に係る適切な取組の推進について(通知)」を受け、同年5月10日、区市町村教育委員会に向け、同調査の趣旨・目的に沿って実施がなされるよう周知しています。
なお、国の「学力調査」のための事前対策を行っているという事実は、把握していません。
A2 文部科学省の平成28年4月28日付「全国学力・学習状況調査に係る適切な取組の推進について(通知)」には、数値データの上昇のみを目的としているととられかねないような行き過ぎた事前の取組があれば、それは同調査の趣旨・目的を損なうものであるとの考えが記載されており、都教育委員会も同様に認識しています。
A3 「全国学力・学習状況調査」の実施に際して、数値データの上昇のみを目的としているととられかねないような行き過ぎた事前対策の実態が明らかになった場合、都教育委員会は、区市町村教育委員会に対し、所管の各学校において、同調査の趣旨・目的に沿って適切な実施がなされるよう、指導を行います。
A4 都教育委員会は、学識経験者や、区市町村教育委員会、小中学校長会、小中学校のPTAなどの代表者からなる「学力向上施策検討委員会」を平成22年度に設置し、「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の在り方について、毎年、検討を行っています。
四 「カジノ型デイサービス」について
A1 介護保険制度における「デイサービス」とは、「通所介護(地域密着型を含む。以下同じ。)」として取り扱われています。
通所介護は、介護保険法に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話並びに機能訓練を行うサービスであり、各事業所は、様々なサービスを介護保険サービスとして提供していると認識しています。
なお、御質問のいわゆる「カジノ型デイサービス」については、介護保険法等に規定がなく、特定することができません。
A2 介護保険制度における「デイサービス」とは、「通所介護(地域密着型を含む。)」として取り扱われています。
御質問のいわゆる「カジノ型デイサービス」については、介護保険法等に規定がなく、特定することができません。
A3 通所介護等の介護保険サービスの利用に当たっては、ケアマネジャーが、利用者の置かれている状況や生活上の支障・希望などの情報を収集し、心身機能の低下の背景・要因の分析を行い、解決すべき生活課題等を把握した上で、目標とその達成時期等を盛り込んだケアプランを作成します。
通所介護事業所は、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえながら、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成し、計画的にサービスを提供しなければならないとされています。
また、保険者である区市町村は、ケアプランの内容が利用者の自立支援に役立つものとなっているか点検を行うなど、介護給付の適正化に努めています。
このように、介護保険制度においては、利用者が適切にサービスを受けられるよう、様々な措置が講じられています。
五 避難所について
A1 避難所において、避難者一人一人の尊厳、健康を守り、安全・安心を確保することは重要であると認識しており、都は、良好な生活環境が確保されるよう、避難所管理運営の指針を区市町村向けに作成しています。
A2 避難所における良好な生活環境を整備するとともに、避難者の健康を維持するため、寝床について、エアマットや段ボールベッド等を導入することは重要であると認識しており、平成30年3月に改定した避難所管理運営の指針で、区市町村が検討する事項として、段ボールベッド等の設置について記載しています。
A3 避難所における良好な生活環境を整備するため、間仕切り用パーティションを活用するなど、プライベート空間を可能な限り確保することは重要であると認識しており、平成30年3月に改定した避難所管理運営の指針で、間仕切りの設置について記載しています。
A4 御質問の国際基準は、紛争や災害の際の避難所の環境に関する最低基準として、国際赤十字等がまとめたものです。
都は、近年の大規模災害における避難所の運営状況等を踏まえ、良好な生活環境が確保されるよう、東京都地域防災計画に基づき、災害想定を考慮した避難所の指定、女性や子供への配慮やトイレの確保等について記載した避難所管理運営の指針を、区市町村向けに作成しています。
今後とも、区市町村が地域の特性や実情に応じて、避難所を運営できるよう、様々な知見も踏まえ、避難所管理運営マニュアルの作成や改定を行うよう働き掛けていきます。
A5 都は、平成30年7月豪雨等の災害を踏まえ、防災事業の緊急総点検を行いました。
この点検を踏まえ、冷房設備が未整備の指定避難所にスポットクーラーや大型扇風機を導入する区市町村に対して、平成30年10月から包括補助で支援を行っています。
以 上
質問事項
一 都庁舎のバリアフリーについて
二 都市計画道路建設について
一 都庁舎のバリアフリーについて
都庁は、東京都の顔であり、誰もが利用しやすいことが必要です。しかし、かねてから車いすを使う身体障がい者の方々より、都議会議事堂に入るための長いスロープの改善が求められながら、改善されません。都営大江戸線の都庁前駅からエレベーターに乗っても、議事堂には直結していません。高低差もあり、カーブも急なため、通常の車椅子で一人でのぼるのは大変厳しく、時間もかかります。そして屋根もないため、雨の日は議事堂に入るまでにずぶぬれになってしまいます。なぜ、多くの方から指摘があるのに、改善されないのでしょうか。都議会の傍聴や要請に来ても、その建物に入ることさえ困難だということは放置できない問題です。
10月1日、東京都障がい者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例が施行されました。「東京に暮らし、東京を訪れるすべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指」す条例の趣旨に鑑み、障がい者にとってのさまざまな社会的障壁をなくすことは急務です。一日も早く改善を求めます。
Q1 都営大江戸線の都庁前駅から、車椅子の方が、地上にいったん出ることなく、都議会議事堂に入れるように、当事者の方の意見をききながら、改善してください。
Q2 地上から車いすで都議会議事堂に入るスロープを距離を短く、傾斜を緩やかにしてください。あるいは1階大型駐車場入口にあるような車いす昇降機を設置してください。
Q3 抜本的な改善策がとられるまでの間、少なくとも、エレベーターをおりてからスロープを利用して議事堂に入るまで、屋根を設置して雨で濡れることのないようにしてください。
二 都市計画道路建設について
現在、東久留米市では、東村山都市計画道路3・4・21号線、及び3・4・13号線の事業化に向けての取り組みが始まりました。「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業計画)」における優先整備路線になったことによるものです。この計画は、閑静な住宅街、公園を通り、オイカワの産卵場所にもなっている黒目川を横断します。環境が激変することにもなることから、反対や心配の声が多数あがっています。
さらに、第1工区(東村山都市計画道路3・4・21号線部分)は、土砂災害警戒区域も含まれていることから、地域ではこのままこの計画が進められて危険はないのか、心配の声があがっています。この間の災害の状況をみても、それほど急な崖でなくても、豪雨で崩壊する事例もあり、崩れる例もあり、不安が広がっています。
東京都は、土砂災害警戒区域の指定を急ぐことをはじめ、防災対策に力を入れるとしています。また、知事は、都市計画道路について見直すべきは見直すことも表明されています。対応を求め質問します。
Q1 都は、都市計画道路の整備を進める際に、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域が含まれている場合、どのようなことを考慮して道路の構造を決めていますか。
Q2 都は、都市計画道路の整備を進める際に、都市計画道路のような公共性が高い施設のなかに土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域が含まれている場合、まず、土砂災害の可能性について調査が行われ、その結果について、市民に説明が行われるべきだと思いますがいかがですか。また、災害危険やその対策について、市民の納得と合意なしに整備を進めるべきではないと思いますがいかがですか。それぞれお答えください。
Q3 東村山都市計画道路3・4・21号線、及び3・4・13号線の土砂災害の可能性について、都は、東久留米市とともに、調査を進め、市民に公表すべきと考えますがいかがですか。
原のり子議員の文書質問に対する答弁書
一 都庁舎のバリアフリーについて
A1 都庁舎では、来庁される方々が誰でも快適に利用できるよう、これまでもバリアフリー化の整備を進めています。
現在、車椅子の方のルートとしては、都営大江戸線の都庁前駅からエレベーターを利用できる都庁第一本庁舎北側のA4出口となります。
他に車椅子の方が利用できるルートはないことから、都庁前駅から地上へ出ずに都議会議事堂へ入るためには、新たなエレベーターを都議会議事堂に設置する等のルートを確保する必要があります。しかし、都議会議事堂へ新たなルートを確保することは、技術的に非常に困難であると考えており、A4出口の利用を御案内することとなります。
今後とも、引き続き、来庁される方々が、都庁舎を快適に利用できるよう努めていきます。
A2 都議会議事堂へ入るスロープは、東京都福祉のまちづくり条例が規定する整備基準に適合しています。距離が短くなればスロープの傾斜がきつくなり整備基準を満たさなくなりますので、現在の距離は必要となっています。
また、新たな昇降機の設置は、必要なスペースの確保が困難であり、都議会議事堂1階の大型駐車場入口に設置されている昇降機の利用を御案内することとなります。
A3 都議会議事堂へ入るスロープ部分への屋根の設置には、強度を確保するために堅固な柱及び基礎が必要となりますが、既存のスロープの位置をずらす等、広範囲の外構整備を伴うことから難しいと考えています。
二 都市計画道路建設について
A1 道路法第29条では、「道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。」とされています。
都市計画道路の整備に当たっては、土砂災害警戒区域等の指定の有無にかかわらず、同法等に基づき、適切な道路構造を決定しています。
A2 都市計画道路の整備を進める際には、必要に応じ、斜面の状況、地形・地質等を調査し、安全性に配慮した適切な道路構造を決定します。
この内容については、工事の着手前に開催する工事説明会等で地元の皆様に説明します。
工事の実施に当たっては、地元の理解と協力を得ながら進めていきます。
なお、今後も土砂災害警戒区域等の指定に当たっては、住民説明会を地元区市町村とともに開催し、土砂災害の危険性や区域指定の目的などについて説明します。
A3 東村山都市計画道路3・4・21号線及び同3・4・13号線は、平成28年3月に策定された「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」において、東久留米市施行の優先整備路線に位置付けられています。
本路線の工事の実施に当たっては、東久留米市が適切に対応するものと考えています。
以 上
2018年第3回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 河野ゆりえ
質問事項
一 プラスチックゴミの削減とリサイクル促進について
一 プラスチックゴミの削減とリサイクル促進について
安価で軽量のプラスチック製品は、生活のなかで広く利用されています。プラスチックの弁当容器、レジ袋、ペットボトル、発泡スチロールなどのプラスチックゴミが海洋に流出し、マイクロプラスチックと呼ばれる微細なかけらとなって、海を汚染していることが、国際的な問題になっています。
東京農工大学の高田秀重教授の研究によると、大量に消費されるプラスチックは、ここ10年足らずで1億トンも増え、世界での生産量は年間4億700万トンに及んでおり、その約半分が、使い捨ての容器や包装とのことです。海洋に流出しているプラスチックゴミの総量は、世界で27万トンに及んでいます。
2016年の世界経済フォーラムの報告書によると、毎年少なくとも800万トンのプラスチックゴミが海洋に流出していて、海にたまっているプラスチックゴミは、1億5000万トンを超えるとされています。
このまま何も手を打たなければ、2050年には海洋プラスチックゴミの総重量が世界中の海の魚の総重量を超えると試算されています。
プラスチックは自然界では分解され難いのですが、海洋に流出したプラスチックは、太陽熱や紫外線、波の力によって劣化、細分化されて、5ミリ以下のマイクロプラスチックになって浮遊します。
マイクロプラスチックは、鳥類、魚介類が餌と区別できずに取り込んでおり、東京湾のカタクチイワシや貝類からも検出されています。こういった魚介類を人が食べて、プラスチックが体内に入っても、プラスチック自体は排泄されます。
しかし、魚などが食べた微細なプラスチックゴミは、消化管を傷つけ栄養を十分に取れなくなるだけではありません。石油が原料のプラスチックには、製造過程で様々な添加剤が加えられていますから、これらの有害物質によって魚の生殖異常を起こし、その魚を食する人の健康にも影響すると指摘されています。
さらに、海水に残留しているPCBなどの有害物質をプラスチックが吸着することも、研究によって明らかになってきています。
このような状況の下、プラスチックによる海洋汚染を止めようと、今年6月にカナダで開かれた先進7ケ国首脳会議(G7)において、「海洋プラスチック憲章」が採択されましたが、日米両国首脳は署名しませんでした。
一方、東京都は、小池都知事が6月に「海洋プラスチック憲章」への支持を表明し、東京都廃棄物審議会にプラスチック部会を設置し、総合的なプラスチック対策に取り組むことを表明しました。持続可能な社会をめざす重要な取り組みです。
地球環境と、生態系に深刻な影響を及ぼすマイクロプラスチック問題の解決のために、石油由来のプラスチックに依存しない社会に変えていく取り組みを進めるよう、東京都の努力を求めて、以下、質問します。
Q1 日本政府はG7で「海洋プラスチック憲章」に署名を行ないませんでした。東京都として、政府に署名を行なうよう働きかけていただくことを要望します。知事の御所見を伺います。
Q2 プラスチック問題の対策で、3R(リデュース・削減、リユース・再使用、リサイクル)のうち、最も重要なのは、リデュース・削減です。現在、飲食チェーン店やホテルなどでは、プラスチック・ストローの使用をやめ、スーパーなどではレジ袋の削減に取り組んでいます。しかし、コンビニエンス・ストアでのレジ袋削減は進んでいません。東京都は率先して、企業及び消費者にプラスチック製品削減の呼びかけが必要と考えますが、知事の見解をうかがいます。
Q3 海外ではプラスチック削減のため、思い切った取り組みが行われています。国単位でのレジ袋や使い捨てプラスチック食器の使用規制はもとより、アメリカ・サンフランシスコ市では2014年からペットボトル飲用水の販売が禁止され、水飲み場を増やしマイボトルの使用をよびかけています。
東京都内でも武蔵野市では、市民を中心としてレジ袋削減に取り組むと同時に、ペットボトルなどの使用削減の運動が進んでいます。マイボトル携帯を奨励し、マイボトルを持参する市民のために給水スポットが設置されています。
マイボトルやエコバッグなどの普及が進むよう、東京都が自治体と連携して、プラスチック削減に向けた創意ある取組をしていただきたいと思いますが、知事いかがでしょうか?
Q4 日本周辺では他の海域の約30倍のプラスチックゴミが存在するといわれています。海洋プラスチック汚染の実効性のある抑制策を議論するならば、この実態を調査することが肝要です。環境省は、海洋ゴミについて年一回調査結果を発表していますが、降雨時などの季節を考慮した調査が必要です。廃棄されたプラスチックの種類、形状などの調査結果をもとに対策を講じることができます。
国に対して、年間を通した海洋プラスチックゴミの調査を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
湾岸はもちろん小笠原を含む島嶼など、広い水域をもつ東京都の努力も必要と思います。実態調査実施に向けて、国と協力しつつ取り組んでいただきたいと考えます。いかがでしょうか?
Q5 洗顔料、歯磨き粉などに含まれる、マイクロビーズ、また、衣類やスポンジなどの化学繊維の破片などの多くは、下水道から海洋に流れ出していると想定されています。このマイクロビーズなどの量や種類についての正確な調査が必要です。下水処理場などでの調査を求めるものですが、いかがでしょうか?
Q6 知事は、今年8月24日の第19回廃棄物審議会で、プラスチックの持続可能な利用に向けた施策について諮問され、プラスチック部会が設置され、今月20日に第一回の部会が開かれました。
この部会の委員には、プラスチック削減、リサイクルなどに詳しい専門家になるべく多く入っていただく必要があると思います。先駆的なプラスチック対策を進めていくためにも、さらに、委員の拡充を求めるものですが、いかがですか。
Q7 「海洋プラスチック憲章」では、3Rを推進するとともに、革新的プラスチック材料・代替材料の開発及び適切な使用を呼びかけています。環境省は生分解性プラスチック製品開発の委託事業を来年度から行う方針を決定しました。都内にもプラスチックを製造する業者があります。都内のプラスチック製造業者に、生分解性プラスチックなど代替製品の開発、製造を奨励し、そのための補助を行なうことなどが必要と考えます。知事の見解を求めます。
河野ゆりえ議員の文書質問に対する答弁書
一 プラスチックゴミの削減とリサイクル促進について
A1 四方を海に囲まれた島国である我が国にとって、海洋プラスチック問題は、極めて重要な課題であり、都として、いち早く、海洋プラスチック憲章を、強く支持する旨を表明しました。
一方、国においては、平成31年に日本で開催されるG20において、海洋プラスチック憲章の内容を超えたものにしていくとの方針が表明されています。
都としては、こうした国の動きを見ながら、東京都廃棄物審議会におけるプラスチックの持続可能な利用に向けた施策の在り方についての議論を踏まえ、総合的なプラスチック対策に取り組んでいきます。
A2 都は、レジ袋の削減に向けた取組を推進するため、平成29年11月に、スーパーやコンビニエンス・ストアなどの事業者団体や消費者団体、区市町村等とレジ袋削減に向けた意見交換会を設け、議論を重ねてきています。
また、平成30年8月には、事業者やNGOなどに参加を呼び掛けて「チームもったいない」を創設しました。
今後とも、「チームもったいない」参加事業者とも連携しながら、レジ袋削減をはじめとする使い捨て型ライフスタイルの見直しを呼び掛けていきます。
A3 都は、平成27年に設置した区市町村との共同検討会において、レジ袋など使い捨て型ライフスタイルの見直しに向けた検討を行ってきました。
また、平成29年11月からは、区市町村のほか、事業者団体や消費者団体等を加えたレジ袋削減に向けた意見交換会を設け、議論を重ねてきています。
今後とも、こうした自治体との連携を密にしながら、使い捨て型ライフスタイルの見直しに向けた取組を推進していきます。
A4 国では、平成22年度から海洋ごみ調査を実施しており、調査地点や調査箇所数等を変え、一年をかけて海岸などにある漂着ごみ、浮遊する漂流ごみ及び海底に堆積した海底ごみに関して、量や種類などの調査等を実施しています。
都では、平成26年度に東京港で海ごみに関する調査を実施したほか、島しょ部においては海岸漂着物の回収・処理事業を実施しており、回収量を国に報告しています。
今後も、プラスチックを含む海ごみに関する調査研究を行っている国等との情報共有を図っていきます。
A5 マイクロプラスチックは、プラスチック製品のほか、多くの製品に由来すると考えられており、また、マイクロプラスチックが海洋に放出される経路について十分に判明していません。
下水道におけるマイクロプラスチックの調査については、量や種類を正確に測定できる統一した方法が技術的に確立されていない状況です。
現在、様々な研究機関が独自の測定方法を用いて調査を行っており、下水道局としては、情報収集に努めているところです。
A6 都は、プラスチックの持続可能な利用に向けた施策のあり方について、平成30年8月、東京都廃棄物審議会に諮問しました。
審議会では、プラスチック対策の知見を有する2名の学識経験者を臨時委員に加えて、プラスチック部会を設置し、現在、専門的な見地から審議を行っています。
A7 プラスチックの代替素材等の開発については、国において、平成31年度概算要求の中で、産業界と連携した実証事業を予定しています。
都としては、こうした動きも見ながら、使い捨てプラスチックの削減やリサイクルの推進など、総合的なプラスチック対策に取り組んでいきます。
以 上
質問事項
一 光明学園の教育環境の改善について
一 光明学園の教育環境の改善について
肢体不自由部門と病弱部門の併置校として、新たに光明学園が開校しました。現在改築工事を行いながら、子どもたちが学校生活を送っています。久留米特別支援学校から移ってきた病弱部門の子どもたちは、豊かな自然に囲まれた学校から転校してきたことで、当初相当ストレスがあったと聞いています。
もともと、病弱部門の子どもたちにとって久留米特別支援学校の環境はすばらしく、移転することにも、併置校にすることにもわが党は反対してきました。また校舎の改築工事を行っている最中に開校してしまうやり方についても、せめて改築が終わるまで病弱部門の子どもたちは久留米特別支援学校で学べるようにするべきだと再三申し上げてきました。
特別支援学校全体に係る問題も多く含まれていますが、光明学園の教育環境を少しでも改善したいという立場から何点か質問します。
ひとつは温水プールの設置についてです。
Q1 病弱部門の子ども達が転校してから、環境の変化、体を動かす場所が少なくストレスが大きく、その解決策のひとつとして、世田谷区立梅丘中学校の温水プールを活用しています。都教委はその効果をどう認識していますか。
現在改築中の光明学園の新しいプールで採用されるのは加温式というガスのボイラー及び熱交換機を使用したものです。プールの水温を上げることで、夏季の水泳指導が気候の影響で中止になることはほぼ避けられると言われていますが、1年を通じて活用できるわけではありません。
一昨年文部科学省が示した特別支援学校施設整備指針では、屋内プールについて、児童生徒の安全性、地域住民の利用等を考慮し、温水プールとして計画することが望ましいと明記しています。
Q2 現在、肢体不自由部門でも、病弱部門でも、温水プールを活用している光明学園でこそ、今からでも温水プール設置に変更するべきです。見解を伺います。
次にスクールカウンセラーの配置です。
Q3 現在都立高等学校には全校にスクールカウンセラーが配置されていますが、特別支援学校には配置がされていません。久留米特別支援学校では臨床心理士による相談会が定期的に開催されていたため、光明学園への再編後も臨床心理士による相談が行われています。この相談は肢体不自由部門の子どもや家族なども対象になっていて活用されています。現在までの実績について伺います。
Q4 また、保護者からは、相談会の回数を増やしてほしいとの要望も出されています。対象を肢体不自由部門に広げた効果も検証しながら、臨床心理士の相談回数を増やすことを求めますがいかがですか。
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書
一 光明学園の教育環境の改善について
A1 都立光明学園のプールより長いコースがある世田谷区立梅丘中学校のプールを活用することで、中学部や高等部の生徒の体格に見合ったプールを確保でき、児童・生徒の健康や食欲の増進にもつながるといった効果があります。
また、児童・生徒が、公共施設を利用する経験を通して、マナーの遵守などの社会性を身に付けるための有用な機会ともなっています。
A2 都立特別支援学校のプールは、夏季に水泳の授業を円滑に行うことを目的として設置しており、学校施設の新設及び改築の際に、各学校の設置学部や障害種別、立地条件等に応じて、必要な施設・設備を整備しています。
現在、改築を進めている都立光明学園に設置を予定している新しいプールの仕様は、設計の段階で学校と協議を重ね、学校の要望や教育課程を十分踏まえたものです。
A3 久都立光明学園では、月に1回から2回、児童・生徒や保護者等を対象として、臨床心理士による相談を実施しています。平成29年度は年間で18回、実施しています。
A4 都立光明学園では、1人当たりの相談時間を30分として、希望者を対象に臨床心理士による相談を実施しています。
これまでのところ、相談枠が不足したことはなく、また、希望者は毎回相談を受けることができていることから、現時点において、回数を増やす予定はありません。
以 上
2018年第3回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 TOKYOチャレンジネットについて
二 豊洲市場水産仲卸売場棟の北側にあるマンホールの噴出について
一 TOKYOチャレンジネットについて
東京都福祉保健局は昨年「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」を実施しました。このなかで、住居を喪失するに至った理由として、「仕事をやめて家賃などを払えなくなった」、「なりそうなため」と答えたのが、全体で32.9%でした。不安定就労者では、33.7%と高く、正社員でも26.7%と高いことが明らかになりました。しかも、「仕事をやめて寮や住み込み先を出た(出ることになりそうな)ため」と答えたのは、不安定就労者の21.6%でした。このことは、仕事がなくなれば住居を失う可能性が大きいことを示しています。
「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」は、東京都の雇用・福祉施策を考える上で大変重要な資料だと痛感しました。
住まいが喪失した人や喪失しそうな方々が相談できる窓口としてTOKYOチャレンジネットの取り組みはますます求められると思います。そこで、TOKYOチャレンジネットについて伺います。
Q1 TOKYOチャレンジネットの取り組みについて伺います。
Q2 相談件数、就労支援、一時住宅への入所者数などの実績について伺います。
Q3 介護研修について、研修参加者数、資格取得者数、介護職への就職などの実績について伺います。
Q4 一時住宅は、都内に何か所・何部屋ありますか。
Q5 一時住宅は、民間住宅や都営住宅などを借り上げていると聞きましたが、借り上げる費用はどこが負担しているのですか。
Q6 一時住宅の管理はどこが行っていますか。また、管理費用はどのくらいかかりますか。
Q7 TOKYOチャレンジネットは、委託事業になっていますが、2015年度、2016年度、2017年度の予算額と決算額はどうなっていますか。
Q8 2018年度の予算額はいくらですか。
Q9 事業委託先はどのようにして決めるのですか。2011年度、2014年度、2017年度は、何者(事業者)から応募がありましたか。
Q10 2017年度は、応募が1者(事業者)だということですが、1者である場合は、もう一度公募して複数の公募事業者から委託先を決めるべきですが、いかがですか。
二 豊洲市場水産仲卸売場棟の北側にあるマンホールの噴出について
豊洲市場の水産仲卸売場棟の北側にあるマンホールから水が噴出し、インターネット動画(9月23日)が発信され「どうなっているのか」と大問題になりました。
9月10日、農水省の認可がおりましたが、認可されても食の安全・安心の問題、市場業者との合意の問題など何も解決していません。それどころか、水産仲卸売場棟の北側バースなど11箇所のひび割れ「地盤沈下」が起こり、今回のマンホールからの水の噴出など、10月11日の開場日を前に、あらたな問題が次々と起こっています。
開場後もどうなるのか心配です。今、きちんと調査し市場業者や都民に丁寧に説明することが求められています。事実の確認のためにいくつか質問します。
Q1 水産仲卸売場棟の北側にあるマンホールから地下水があふれたのは、いつですか。
Q2 マンホールからの水の噴出の原因は、何ですか。
Q3 マンホールからの水の噴出は、初めてですか。
Q4 あふれた水は、どのような水ですか。
Q5 「付着物」とは何ですか。
Q6 あふれた水の水質調査は行ったのですか。
Q7 水は排水溝に流れたようですが、どのように処理したのですか。
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書
一 TOKYOチャレンジネットについて
A1 都は、平成20年度から、住居を失いインターネットカフェなどで寝泊まりしながら不安定な就労をしている方を対象に、支援拠点であるTOKYOチャレンジネットを設置して、生活、居住、就労に関する相談援助や一時的な住宅の提供、資金貸付、資格取得支援などの総合的な支援を行っています。
A2 平成29年度のTOKYOチャレンジネットの実績は、以下のとおりです。
相談支援では、来所による相談件数は延べ7,569件であり、継続的な相談のための登録を行った方は987人となっています。
就労支援では、就労相談件数は延べ2,464件、職業紹介件数は延べ334件であり、紹介後の採用者数は259人となっています。
居住支援では、住居を喪失した方に提供している一時利用住宅の利用者数は397人となっています。
A3 都は、TOKYOチャレンジネットで、介護職場での就職を目指す離職者等に対し、介護職初任者研修を無料で実施しています。
平成29年度の介護職初任者研修の受講者数は109人、研修修了者数は84人であり、研修修了者のうち介護職場への就職者数は76人です。
A4 民間アパート等を借り上げて、住居を喪失した方に原則3か月間を限度として提供している一時利用住宅は、平成30年10月現在、都内に67か所、100部屋を確保しています。
A5 一時利用住宅の借上げ費用は、都が負担しています。
A6 一時利用住宅は、都が委託している事業者が借り上げて管理しています。賃料以外のクリーニングに係る費用や修繕費などの管理費用は、平成29年度実績で約2,531万円です。
A7 TOKYOチャレンジネット(住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業)の当初予算額は、平成27年度(2015年度)約6億2,344万円、平成28年度(2016年度)約6億7,685万円、平成29年度(2017年度)約6億4,630万円であり、決算額は、平成27年度約4億9,384万円、平成28年度約5億2,827万円、平成29年度約5億2,400万円です。
A8 TOKYOチャレンジネット(住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業)の平成30年度(2018年度)の当初予算額は、約5億9,473万円です。
A9 TOKYOチャレンジネットの事業者選定に当たっては、都のホームページで事業者を募集し、応募があった事業者の中で、企画提案方式により、選定を行っています。
平成23年度(2011年度)、平成26年度(2014年度)、平成29年度(2017年度)ともに、1事業者から応募がありました。
A10 TOKYOチャレンジネットの委託事業者は、運営事業者選定委員会設置要綱に基づいて、外部委員を含めた選定委員会による審査を踏まえて適切に事業者を選定しています。
二 豊洲市場水産仲卸売場棟の北側にあるマンホールの噴出について
A1 豊洲市場水産仲卸売場棟の北側積込場にある、地下水管理システムのマンホールからいっ水があったのは、平成30年9月23日午後2時30分頃です。
A2 地下水管理システムの各揚水井戸から揚水された地下水は、場内に敷設されている送水管に集められ、排水施設棟へ送水されています。
送水管内に空気が溜まった場合、水の流れを阻害する可能性があることから、送水管には管内の空気だけを排出するための空気弁が設けられています。
今回の事象は、送水管の内側の付着物が、この空気弁に挟まったことにより、送水管内の水もあふれ出たものと認識しています。
A3 マンホールからのいっ水は平成30年9月23日に発生しましたが、その4日前の同月19日に、開場に先立つメンテナンスの一環として、6街区において、地下水管理システムの送水管の清掃を実施しました。
今回の事象は、管清掃で剥がれやすくなっていた管内側の残留付着物が、送水により剥がれ、空気弁に挟まったことにより生じたものと認識しています。
送水管の清掃は、今回初めて実施したものであり、こうした事象を確認したのは今回が初めてです。
A4 地下水管理システムの各揚水井戸から揚水された地下水は、場内に敷設されている送水管に集められ、排水施設棟へ送水されています。今回のマンホールからのいっ水は、排水施設棟へ送水するまでの間で生じたものです。
A5 豊洲市場用地は埋立地であり、これまでも井戸やポンプ等の揚水施設には、海水に由来する水酸化マグネシウムの付着が確認されています。
また、再生砕石に由来する炭酸カルシウムの付着も確認されており、今回の付着物もこうしたものによるものと考えています。
A6 いっ水時には、いっ水を速やかに止めるよう、迅速に措置を講じることを優先したことから、あふれた水の水質調査は実施していません。
地下水管理システムの各揚水井戸から揚水された地下水は、場内に敷設されている送水管に集められ、排水施設棟へ送水されています。送水された水の水質については、排水処理の前後で自動分析や公定分析を実施していますが、いずれの分析においても、例えば、ベンゼンやシアンは下水排除基準に適合しています。
今回のいっ水については、速やかに空気弁を閉塞したことから、流出した水の量や範囲は限定的であり、周辺環境や市場業務に影響を及ぼすことはないと認識しています。
A7 いっ水した水は、場内に敷設されている、側溝に流れ、最終的には、下水道に流入しています。
なお、今回のいっ水については、速やかに空気弁を閉塞したことから、流出した水の量や範囲は限定的であり、また、現在、豊洲市場における全ての空気弁は閉じられた状態にあります。さらに、今後、空気弁を開く際には職員立会いの下、短時間で行うこととしているため、今回のような事象は生じないと考えています。
以 上
2018年第3回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 和泉なおみ
質問事項
一 都立水元公園の管理改善について
二 風疹の緊急対策について
一 都立水元公園の管理改善について
水元公園は水郷景観のある都内唯一の都立公園です。豊かな自然と都市型公園の機能を併せ持ち、多くの都民に愛されてきました。その広さは96ヘクタール広大で、江戸時代につくられた小合溜に沿うこの公園には、中央広場のような明るく開けた草原、メタセコイアやハンノキなどが生い茂る樹林、水辺や菖蒲田、ガマ田などの湿地、バードサンクチュアリなど、さまざまな環境があることで、植物、昆虫や鳥類などの種類がとても豊富です。絶滅危惧種に指定されているものも多く観測されています。しかし、近年アサザも、オニバスも急激に減少し、売店前の広場にある噴水はもう4年以上水が止まっています。
水元公園のもう一つの特徴は、都内最大の都市型公園でもあるという点です。散歩やバーベキューを楽しみ、お弁当をひろげてくつろぐ姿、子どもが元気に遊ぶ姿にあふれ、この公園がいかに多くの都民に愛されているかを物語っています。
だからこそ、さまざまな世代の都民から意見や、要望が寄せられます。私は、葛飾区民の誇りであり、都民の宝である水元公園の豊かな自然が守られ、広く都民から愛される公園としてあり続けるために、公園管理について、以下質問します。
Q1 噴水広場の噴水が4年以上も止まったままです。今では土が敷かれ植栽のようになっています。公園正面の入り口であり、水元公園を象徴するような噴水が、訪れる人たちを迎えていたのに、見る影もない現状に、多くの区民が噴水の再開を求めています。水郷景観を象徴していた噴水の再開を待ち望む地域住民の声に都として、応えるべきだと思いますが、見解を伺います。
Q2 菖蒲祭りは、毎年区のさまざまな団体が協賛し、同時期に開催される堀切菖蒲園の菖蒲祭りとともに、地域の重要なイベントとなっています。しかし、今年6月の菖蒲まつりでは13ある菖蒲田のほとんどで花が咲いておらず、多くの区民と来訪者をがっかりさせることとなりました。一方で堀切菖蒲園の菖蒲は、今年も見事な花を咲かせ、来園者の目を楽しませました。都として、菖蒲田の管理を堀切菖蒲園に学び、水元公園の菖蒲田を復活させることを求めますが、いかがですか。
Q3 水元公園の豊かな自然環境を守るためには、専門的知識を持った職員が必要です。江戸金魚の水槽の保全、洋式トイレの速やかな整備、拡張された東金町8丁目との一体的整備や加用水の解決など、課題が山積しています。都として公園管理のあり方を抜本的に見直すべきではありませんか。都の見解を伺います。
二 風疹の緊急対策について
風疹の感染が関東地方を中心に拡大しています。国立感染症研究所の感染症疫学センターによれば、今年第1週から第38週までの風疹患者累積報告数は770人になり、2008年の全数届出開始以降、2013年、2012年についで3番目に多い報告数となり、首都圏を中心に感染が広がりつつあります。
東京都感染症情報センターによれば、都内の風疹報告数は、今年第1週から第38週までで239人に上っています。
2013年の大流行時には全国で14,344人の患者が報告され、この流行に関連した先天性風疹症候群が45人確認されています。先天性風疹症候群は、妊娠20週ぐらいまでの妊婦が風疹にかかると、おなかの赤ちゃんにもウイルスが感染して起こる病気で、難聴や白内障、心臓病といった深刻な影響が出るおそれがあります。
風疹の拡大を防ぐためには、社会全体で免疫を持っている人の割合を高くする必要があります。
しかし、予防接種法に基づく感染症流行予測事業の2017年度の調査結果でも、30代から50代の男性の抗体保有率が低くなっています。これは、この世代のワクチン接種が十分に行われなかったためであり、感染者数もこの世代で多くなっていることから、特に対策が必要です。
しかし、東京都から区市町村への予防接種費用の補助は、妊娠を予定または希望する女性を対象とする場合に限られており、対象の拡大が必要です。
以上を踏まえ、風疹の感染拡大と、それに伴う先天性風疹症候群を予防するために、以下質問します。
Q1 国立感染症研究所は、「女性は妊娠前に2回の風疹含有ワクチンを受けておくこと、妊婦の周囲の者に対するワクチン接種を行うことが重要である。また、30代から50代の男性で風疹に罹ったことがなく、風疹含有ワクチンを受けていないか、あるいは接種歴が不明の場合は、早めにMRワクチンを受けておくことが奨められる。」としています。風疹は、ワクチンで予防可能な感染症であり、男性も含めた30代から50代のすべての成人に対してMRワクチン接種への助成をできるよう、区市町村への補助を行うべきと考えますが、都の見解を伺います。
Q2 1のほか、医療関係者、教育、保育関係者、妊婦の同居家族なども感染の拡大を予防するために重要です。必要とするすべての人への予防接種費用について区市町村への補助を行うべきですが、いかがですか。
Q3 また、居住地以外で接種した場合に、「償還払い」が受けられない区市町村もあります。区市町村に積極的に働きかけ、居住地以外でも費用の心配をすることなく予防接種ができるようにするべきだと考えますが、都の見解を伺います。
Q4 MRワクチン接種への費用助成は、抗体検査をすることが前提となっているのが現状です。しかし、国立感染症研究所は、抗体検査なしでワクチン接種をしても差し支えないと、述べています。感染の拡大を抑え、先天性風疹症候群を防止するためにも、希望する人には抗体検査なしでもワクチン接種の助成を行うべきですが、都の見解を伺います。
Q5 国と連携し、各種のワクチンで近年繰り返されている供給不足の実態・原因を分析・評価し、ワクチン供給体制の問題点を具体的に明らかにしてワクチン供給不足への対策を早期に行うべきです。都の見解を伺います。
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書
一 都立水元公園の管理改善について
A1 水元公園は、埼玉県と東京都の県境に位置し、小合溜に沿って、広々とした水郷の景観が広がる約96ヘクタールの公園です。
水元公園の噴水施設については、平成29年度までに設計を完了しており、平成30年度及び平成31年度に改修工事を実施する予定です。
引き続き、水元公園の特性を生かした公園整備に努めていきます。
A2 水元公園の菖蒲田は、水郷景観の象徴であり、約9,000平方メートルに約100品種、約20万本のハナショウブが植えられています。
指定管理者である公益財団法人東京都公園協会は、これまでも、花付きの悪いハナショウブの植替えや、菖蒲田に繁茂しやすい雑草の除去など、開花率の向上に取り組んできました。
引き続き、指定管理者と協力しながら、更に見応えのある美しい菖蒲田の実現に努めていきます。
A3 水元公園は、メタセコイアが1,800本も林立する「メタセコイアの森」やバーベキュー広場、水郷景観を象徴する菖蒲田や水生植物園などがあり、四季を通じて散策や自然観察を楽しめるとともに、様々な魅力を有する大規模な公園です。
指定管理者である公益財団法人東京都公園協会は、これまでも水郷景観の保全や、アサザ、オニバス等の水生植物の保全など、専門的な知識を生かして維持管理業務に取り組んできました。
今後とも、希少な水生植物の保護増殖や外来種の駆除等の取組を強化するなど、水元公園の特性を踏まえた維持管理を行っていきます。
加用水の公園化など様々な課題については、引き続き、地元区や関係機関と連携するなど、取組を進めていきます。
二 風疹の緊急対策について
A1 風しんは、免疫を持たない妊婦が妊娠20週頃までの妊娠初期に感染すると、胎児が、難聴、白内障、先天性心疾患を特徴とする先天性風しん症候群にかかるおそれがあることから、都は、妊娠を予定又は希望する女性を対象に抗体検査と予防接種を一体的に行う区市町村を、包括補助で支援しています。
平成30年7月以降、風しん患者が急増している状況を踏まえ、都は緊急対策として、同年10月から、抗体検査と予防接種の対象を、妊婦の同居者、妊娠を予定又は希望する女性の同居者にも拡大しました。
また、今般の流行において患者の多くを占めている働く世代の感染予防として、職場で風しんのり患歴や予防接種歴の確認を行うよう呼び掛けるほか、従業員への普及啓発や、抗体検査と予防接種の促進等に取り組む企業を支援するなど、職域における風しん対策を推進しています。
A2 予防接種に必要なワクチンは、法律に基づく定期予防接種の対象者を中心に需要を見込み、計画的に生産されています。
急激な需要の増加に対応し、短期間に生産量を増加させることは難しいことから、効果的かつ効率的な予防接種の実施が求められます。
都は、風しん対策における最優先の課題である先天性風しん症候群の発生防止対策として、妊娠を予定又は希望する女性を対象に抗体検査と予防接種を一体的に行う区市町村を、包括補助で支援しています。
また、今般の流行状況を踏まえ、妊婦や妊娠を予定又は希望する女性の同居者についても、平成30年10月から抗体検査と予防接種の対象に加え、積極的に検査を受け、必要な場合には接種を受けるよう、区市町村や関係機関と連携して呼び掛けています。
A3 区市町村が実施主体となって行われる予防接種は、通常、その区市町村が委託した医療機関で実施されています。
区市町村の委託先ではない医療機関で実施された予防接種の取扱いは、実施主体である区市町村の判断によるものと考えます。
A4 予防接種に必要なワクチンは、法律に基づく定期予防接種の対象者を中心に需要を見込み、計画的に生産されています。
急激な需要の増加に対応し、短期間に生産量を増加させることは難しいことから、効果的かつ効率的な予防接種の実施が求められます。
国が策定した風しんに関する特定感染症予防指針によれば、風しんにり患したことがないと認識している者でも、一定の割合で風しんの免疫を保有していると考えられており、国民の8割から9割程度が既に抗体を保有している状況を踏まえると、必要があると認められる場合には積極的に抗体検査を実施することで、より効果的かつ効率的な予防接種の実施が期待できるとされています。
A5 都は、都内でワクチンの偏在が生じた場合などに、区市町村、医師会、医薬品卸業団体等の関係機関と連携して、必要なワクチンを円滑に供給するための体制を構築しており、国に対しては、ワクチンの安定供給対策を十分に講じるよう提案要求しています。
以 上
2018年第3回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 曽根はじめ
質問事項
一 東京都におけるエイズ/HIV対策について
一 東京都におけるエイズ/HIV対策について
Q1 「世界エイズデー」の日本でのキャンペーンテーマが指摘しているように、HIV/エイズに関する取り組みは、いま「大きな転換期」を迎えています。治療法の進歩により、HIVに感染しても、検査を受けて早く感染を発見し、治療を早期に開始して治療を継続すれば、エイズの発症を防ぐことができるようになりました。
服薬治療を継続すれば、体内のウイルス量を減少させることが可能となり、他の人に感染させるリスクが大きく低下することも確認されています。
治療法の進歩により、HIVに感染した人の生活は大きく変わり、感染予防にもさまざまな選択肢が用意されるようになっているのです。
都は、HIV/エイズをめぐって「大きな転換期」にあることを、どう認識していますか。都として「大きな転換期」にふさわしい対策を具体化する必要があると思いますが、いかがですか。
Q2 東京都は、2009年5月に策定した「エイズ対策の新たな展開」にもとづいてエイズ対策に取り組んできましたが、計画策定から10年が経とうとしています。早急に全面改定して「大きな転換期」にふさわしい、新たな計画を策定すべきです。都の認識を伺います。
Q3 エイズ対策の新たな計画を策定するにあたっては、期限を定めた数値目標と、具体的な行動計画、その実施状況を複数年にわたって検証・評価する仕組みを明確にする必要があると思いますが、都の見解を伺います。
Q4 厚生労働省は、本年1月に、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」を全部改正しました。その内容は、HIV感染の早期発見に向けたさらなる施策が必要であることをはじめ、予防、医療の提供、人権の尊重など全面的なものです。都としては、国の「予防指針」の全部改正に、どのように対応するのですか。
Q5 2014年、国連合同エイズ計画は、HIVの流行を制御する戦略として2020年までに「3つの90%」を達成する目標を提唱しました。
第1に、HIV感染者のうち感染を自覚している人の割合を90%以上にする、第2に、検査によりHIV陽性と診断された感染者のうち、定期的に治療を受けている人の割合を90%以上にする、第3に、定期的に治療を受けている感染者のうち、他の人に感染させない状態にまでウイルス量を低下させた人の割合を90%以上にする、というものです。
国連合同エイズ計画はさらに、各目標を2030年までに95%に引き上げることを提唱しています。
これが、いま世界の大きな流れになっていることを、都はどう認識していますか。都としても、2020年までに「3つの90%」、2030年までに95%を達成する目標をめざして取り組むべきですが、いかがですか。
Q6 「3つの90%」の目標に関連して、日本では、定期通院者の数や治療状況などについて正確なデータが不足していることが指摘されています。都は国と連携して、こうした調査・研究を推進し、「3つの90%」目標に対する現状を、正確に把握する必要があります。見解を伺います。
Q7 治療を定期的に受ける人の割合を引き上げるためには、治療法の進歩により、治療の早期開始・継続によりエイズの発症を防ぐことができること、有効な治療法がなく死に至る病であるというのは、もはや過去の話であるなどの正確な情報提供を、さらに強化することが重要です。
また、エイズ診療拠点病院だけでなく、身近な地域の病院・診療所で適切な治療を受けることができる体制整備が必要です。長期にわたる治療の医療費負担の軽減も、重要な課題です。
都は、治療を定期的に受ける人の割合を引き上げる対策に、今後どう取り組むのですか。
Q8 HIVウイルスの量を低下させる薬は着実に進歩しており、2015年には1日1錠、食事時間を気にせず飲める薬が登場しました。しかし毎日確実に、長期にわたって飲み続けることが必要です。
一例として厚生労働省は、結核患者への服薬支援「DOTS」について、チームによる患者中心の包括的支援、個別患者支援計画の作成、地域におけるDOTSの実施、治療成績評価と地域DOTS実施方法の評価・見直し等を内容とする「戦略方針」を明らかにし、都道府県等に「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認法)の推進について」を、技術的助言として通知しています。
こうしたことも参考にして、医療機関、医療関係者の努力だけにまかせるのでなく、都政の重要課題として位置づけ、服薬支援の体制整備に取り組む必要があります。
しかも服薬治療の継続は、感染者の状態を改善するだけでなく、他の人への感染をふせぐ予防効果もあることが明らかになっており、服薬治療を支援する体制整備は重要な課題だと思いますが、都の認識を伺います。
Q9 都として関係機関、区市町村と連携して「HIV感染症の服薬支援推進協議会」または「HIV感染症の服薬支援のあり方検討会」(いずれも仮称)を設置し、エイズ診療拠点病院だけでなく、身近な地域で、医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、カウンセラー等のチーム医療による、同じ水準の服薬支援を受けることができる体制整備、人材育成を進めることが必要ではないでしょうか。見解を伺います。
Q10 2017年の都の調査では、HIV感染者の69%が20歳未満および20代、30代の若い世代です。都はこれまで、若者のための普及啓発拠点「ふぉー・てぃー」の設置・運営、エイズ・ピア・エデュケーションの実施、若者向けネット配信などに取り組んでいますが、さらに充実、発展させることが必要です。
また、全部改正された国の「予防指針」では、「性に関する適切な意思決定及び行動選択に係る能力が形成過程にある青少年に対しては、心身の健康を育むための教育等の中で、性に関する重要な事柄の一つとして、HIVに関する知識の普及啓発を行うことが特に重要である」との内容が、新たに記述されました。都は、若い世代の対策に、どう取り組むのですか。また、学校教育等で、HIVなどの性感染症をふくめ、科学的な根拠にもとづく知識を学ぶ性教育を充実・強化することが必要です。いかがですか。
Q11 若い世代が多く集まる場所に、敷居が低くて入りやすい、無料・匿名で検査できる場所を、臨時や巡回もふくめ、数多く設置することも必要です。都の対応を伺います。
Q12 都の調査で、外国人のHIV感染者・エイズ患者の報告数は増えており、エイズ専門家会議では、「外国国籍の人たちに向けた対策も必要だということを数年前からのデータは示している」と指摘されています。
HIV検査の促進をはじめ、外国国籍の人たちに向けた対策を、抜本的に拡充する必要があります。都の認識と対応を伺います。
Q13 都の南新宿検査・相談室、多摩地域検査・相談室、HIV検査情報webのホームページは、いずれも多言語対応になっていません。都のエイズ専門家会議でも、NPO団体の委員から、南新宿検査・相談室のホームページが日本語表示のみだという指摘がありました。都は、この問題の重要性をどう受け止めていますか。多言語化を、早急に実施すべきですが、いかがですか。
Q14 都内の梅毒の患者報告数は2011年から増加に転じ、2014年から2016年までの3年間で、報告数が3倍以上と顕著に増加しています。感染原因の多くは性的接触です。都は今年度、検査体制強化、医療従事者研修などの「梅毒緊急対策」を実施していますが、さらに拡充・継続が必要です。また、梅毒などの性感染症対策とHIV/エイズ対策を連携させた施策の推進が重要です。見解を求めます。
曽根はじめ議員の文書質問に対する答弁書
一 東京都におけるエイズ/HIV対策について
A1 近年の抗HIV療法の進歩により、HIV感染者等の予後が改善され、感染の早期発見、治療の早期開始及び継続により、エイズの発症を防ぐことができ、感染していない人と同等の生活を送ることが期待できるようになっています。
また、治療の継続により体内のウイルス量が減少すれば、他の人への感染リスクが大きく低下することも確認されています。
こうした状況を踏まえ、都は、HIV治療の進歩と検査・早期治療の重要性を広く伝えていくため、HIV検査・相談月間やエイズ予防月間などの機会を通じた普及啓発に取り組んでいます。
A2 平成30年1月に国は、近年のHIV感染者及びエイズ患者の発生動向や、HIV治療の進歩、エイズを発症した状態で感染が判明した者の割合の高さ等の状況を踏まえ、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」の改正を行っており、都でも、改正された指針の内容を踏まえ、必要な検討を行う予定です。
A3 都のHIV/エイズ対策は、「エイズ対策の新たな展開」で取組目標と具体的な方策を明らかにして取り組むとともに、その実施状況について、毎年、学識経験者で構成する東京都エイズ専門家会議での検証と評価を行っています。
A4 国は、HIV感染者及びエイズ患者の発生動向、検査、治療等に関する科学的知見など、HIV/エイズを取り巻く環境の変化に対応し、予防を総合的に推進するため、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」を改正しました。
都では、改正された指針の内容も踏まえ、今後の都における対策について必要な検討を行う予定です。
A5 国連合同エイズ計画は、第一に感染者が検査によりその感染を自覚し、第二に定期的に治療を受け、第三に他者に感染させない状態にまでウイルス量を低下させるという一連のプロセスを「ケアカスケード」と称し、その全てのプロセスにおいて90パーセント以上を達成することをエイズ施策の指標とするよう提唱しています。
しかしながら、国は、現在のHIV感染者及びエイズ患者の発生動向調査では、新規感染者の数は把握できるものの、定期通院者の数、死亡者数、抗HIV療法の導入状況、治療状況が把握できないことなどを課題として挙げ、継続的な研究が必要であるとしています。
このため、都は、国の研究等の動向を注視していきます。
A6 国の「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」では、国連合同エイズ計画による、感染者が検査によりその感染を自覚し、定期的に治療を受け、他者に感染させない状態にまでウイルス量を低下させるという一連のプロセスである「ケアカスケード」について、その評価に資する疫学調査・研究を継続的に実施する必要があるとしています。
都は、国の動向を注視するとともに、国からの求めに応じて調査等に協力していきます。
A7 HIV感染者及びエイズ患者に医療を適切に提供するため、都は、HIV/エイズ診療の中核となる医療機関としてエイズ診療協力病院を確保するとともに、各病院が治療などに関する相談にも対応できるよう、患者や家族へのカウンセリングを行う体制を整備しています。
また、患者支援団体と連携して、患者等からの相談への対応や治療に関する情報提供を行っています。
A8 医療機関が行う、HIV感染者及びエイズ患者に対する療養上必要な指導及び感染予防に関する指導は、診療報酬の算定対象とされています。
都は、HIV/エイズ診療の中核となる医療機関としてエイズ診療協力病院を確保し、HIV感染者及びエイズ患者に医療を適切に提供する体制の整備を図っています。
A9 医療機関が行う、療養上必要な指導及び感染予防に関する指導は、診療報酬の算定対象とされ、また、所定の要件を満たしたチーム医療については加算対象とされています。
都は、HIV感染者及びエイズ患者への適切な医療提供のために確保したエイズ診療中核拠点病院において、他の協力病院に対する研修事業を実施するなど、HIV/エイズ診療に関する人材の育成を図っています。
A10 都は、HIV感染者の多くを占める若い世代を対象に、効果的な予防啓発を図るため、若者がHIVやエイズについて主体的に考え、同じ世代の交流や相互学習を通じてHIV等に関する理解を深める取組を行っています。
また、そのノウハウを生かして青少年施設、学校等での啓発や、ボランティア団体等が行う啓発活動への支援に取り組んでいます。
小・中・高等学校においては、性感染症の予防について、学習指導要領等に基づいて指導しています。
具体的には、小学校では、第6学年の保健の授業で、病原体が体に入ることを防ぐことや体の抵抗力等について指導し、中学校では、第3学年の保健の授業で、エイズやその他の性感染症について、疾病の原因や感染経路、予防方法等を指導しています。
また、高等学校では、保健の授業において、エイズなどの新興感染症や結核などの再興感染症の発生や流行等について指導しています。
今後とも、児童・生徒の発達段階に応じて系統的に指導することが大切であると考えています。
A11 都は、保健所や、南新宿及び多摩地域検査・相談室で、無料・匿名でのHIV検査・相談を実施しています。
また、HIV検査・相談月間、エイズ予防月間を中心に、NPO等の協力を得ながら、講演会や、繁華街でのライブイベント、街頭キャンペーンなどを行っています。
さらに、利用者の利便性を考慮し、南新宿検査・相談室の予約受付をインターネットで行えるようにするなど、検査を受けやすい体制の整備に取り組んでいます。
A12 都の保健所や検査・相談室のHIV検査・相談は、原則として、在日外国人を含む都民を対象としています。
外国人の方への検査・相談への対応の際は、平易な日本語で対応するとともに、南新宿検査・相談室では、必要に応じて英語での対応も行っています。
A13 都の保健所や検査・相談室におけるHIV検査・相談は、原則として、在日外国人を含む都民を対象としています。
そのため、利用者は日常使われる基本的な日本語については理解ができると考えられることから、ホームページは日本語表記としています。
今後、検査について広く周知するため、HIV感染者及びエイズ患者発生動向を踏まえ、必要な検討を行っていきます。
A14 都はこれまでも、性感染症の啓発パンフレットに、HIV、エイズのほか、梅毒や性器クラミジア感染症などの予防等に関する情報を併記し、啓発を進めるとともに、南新宿検査・相談室でHIVと梅毒の同時検査を実施してきました。
近年における梅毒の報告数の増加を受け、平成30年4月からは、南新宿検査・相談室で週3日実施していたHIVと梅毒の同時検査を、祝日・年末年始を除く毎日実施に拡充するとともに、多摩地域検査・相談室でも同時検査を開始しています。
さらに、平成30年11月に、HIV、エイズと梅毒を含めた性感染症に関するホームページを新設し、感染予防の啓発や、検査についての情報発信を行っています。
以 上