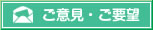主な活動
2017年第3回定例会に提出した文書質問
2017年第3回定例会で、以下の文書質問を提出しました。
- 里吉ゆみ (世田谷区選出) 東京都教育委員会の請願制度について
- 尾崎あや子(北多摩第一選出) 特別支援学校の教室不足問題等について
- 原のり子 (北多摩第四選出) 小・中学校における発達障害教育推進について
質問事項
一 東京都教育委員会の請願制度について
一 東京都教育委員会の請願制度について
地方公共団体が、教育・学術・文化に関する事務を行う場合は、その性質上、政治的中立を維持すること、行政が安定していること、住民の意思を反映することが求められます。これらにこたえるため、都道府県及び区市町村には、知事又は区市町村長から独立した行政委員会として、合議制の執行機関である教育委員会が設置されています。
しかし、現在の都教育委員会は、住民の意思を反映するものとはなっていません。2002年に東京都教育委員会請願取扱要綱がつくられてから、要綱に基づき、請願は総務部教育情報課において収受し、主管課に送付する。そして主管課が迅速かつ慎重に検討してその結果を請願者に通知する。そして主管課は、事案決定規程等において、委員会決定に該当する請願については、速やかに当該請願があった旨を委員会定例会に報告することになりました。
Q1 2003年度から2016年度まで、都教育委員会に出された請願の数と、都教育委員会に報告された請願数、報告されなかった請願数について、年度ごとにそれぞれ伺います。
Q2 請願取扱要綱が定められて以降の教育委員会で、都民から出された請願について議論のあった案件の有無、あったとすれば何件で、どのような内容だったのか伺います。
東京都の教育をめぐっては、都立高校の統廃合問題や、国旗掲揚・君が代斉唱を義務付ける「一〇・二三通達」関連、体罰やいじめ問題など様々な課題が山積しています。教育委員であれば、こうした問題について都民から寄せられた意見に真摯に向き合い、東京都の教育について考えるべきでしょう。しかし現状では、東京都教育委員会請願取扱要綱に基づき、都民から寄せられた請願の一部しか教育委員には届いていません。
都議会には、行政から独立した機関である教育委員会が都民の教育に関する意見や要望を聞いて欲しいと、教育委員会の請願制度の改善を求める陳情が過去何度も出されてきました。主には、教育委員会に提出された請願を教育委員会会議で審議すること、請願者から要請があれば、都教育委員会の場で意見陳述をさせることなどです。
Q3 都議会に4回も都教育委員会の請願制度について改善を求める陳情が出されていることについて、今も改善を求める要望が強いことについてどう受け止めているか、都教育委員会の見解を伺います。
教育委員会に報告しない請願があることについて、この要綱を決めた教育委員会の中でも「提出された請願を、教育庁の中で教育委員会に諮るか否か事前にセレクトするということですね。しかし教育長の権限の中でやると、非常に恣意的に、個人的なものがほかに影響してくることもあります。・・・だからこのことをきちっと決めておかなければいけないと思います。」「重要事項であるかどうかということを決めるのが非常に重要であって、いわゆるあいまいな書き方というのはこういうときは一番問題になるのです。」など議論が様々出ていました。
Q4 「すでに方針が決まったこと」についての請願については、教育委員会に報告していないということになっていると聞いています。その制度の見直しを求める声が都民から出されても都教育委員会は門前払い、話も聞きませんということになるのではありませんか。見解を伺います。
Q5 請願を選別する根拠となっている「東京都教育委員会請願取扱要綱」の改善を求める請願も、都教育委員会に提出されましたが、都教育委員会の会議には報告もされませんでした。都教育委員会で議論されたものであるにも関わらず、都教育委員会に報告もされないというのはなぜか。要綱について教育委員会では検討することはできないのか、うかがいます。
2014年に教育委員会制度が大幅に変わりました。教育委員会制度廃止という声もありましたが、やはり教育委員会は行政から独立した形で残すべきだという結論に至りました。同時に、教育委員会は今のままでいいというわけではなく、更なる改革が求められていると思います。
その一つが、地域に開かれた教育委員会になること、住民の声を聴き、教育施策をチェックできる教育委員会になることです。文科省は通知の中で、公聴会や意見交換会の開催など幅広く地域住民の意見を聞くことを促しています。2015年6月の国会質疑では、日本共産党の教育委員会の改革提言で、教育委員たちが保護者、子ども、教職員、住民の不満や要求をつかみ、自治体の教育施策をチェックし改善する、これが必要だということを紹介した我が党の田村智子委員の質問に、当時の下村文部科学大臣は「それは適切なすばらしい提案だと思います。」と答弁しています。教育委員会が都民の声を聞くのは当然であり、積極的にすすめるべきだというのが、文科省の方針としても示されているのです。
Q6 教育委員会制度が変更され、教育委員会の改善が求められています。教育委員会の請願制度については、その取扱いについては再検討の必要があると思いますが、いかがですか。
都立雪谷定時制の廃止見直しを求める皆さんが、7月に都教育委員会に請願を提出しました。雪谷定時制は、昨年10月に来年廃止予定とされた学校です。例年通りであれば今年の10月の教育委員会で募集停止の決定がされることを予想して7月に請願を出しましたが、その後の教育委員会に傍聴に行っても、自分たちの請願がどのようにあつかわれたのか、また少なくとも教育委員のみなさんに請願の文書が届いたのかどうかすらわからなかったそうです。
都民にかかわる重大問題で、関係者が教育委員に直接意見を聞いてほしい、議論して欲しいと請願をだしているのに、その声を門前払いするようなやり方は教育委員会としてやはりおかしいのではないでしょうか。
Q7 今の方針を変更して欲しいという請願が、その方針を決定する会議の前に、教育委員のみなさんに渡らず、審議されないというのはおかしいのではないでしょうか、見解を伺います。
Q8 教育委員会がその役割を果たすためには、今の方針をわけへだてなく教育委員会で審議するべきです。見解を伺います。
また、都民の教育に関する要望や苦情については、教育庁における苦情等の取扱いに関する要綱に基づいて対応されています。要綱には、原則として、苦情等の内容にかかわる業務を担当する課が行うことが明記されています。しかし実際に教育庁に具体的な要望をもっていくと教育情報課に回されてしまい、担当所管に話ができない、という声が数多くよせられています。
Q9 教育庁への要望や苦情については、担当所管が丁寧に都民の要望に応えるべきと思いますが、見解を伺います。
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書
一 東京都教育委員会の請願制度について
A1 既に都教育委員会で決定された教育施策の基本方針等に基づく事項に係る請願については、「東京都教育委員会請願取扱要綱」、「東京都教育委員会事案決定規程」等に基づき、主管課において当該事案について決定権限を有する者が適正に処理しています。
平成15年度から平成28年度までに都教育委員会に提出された請願数と、そのうち都教育委員会定例会及び同臨時会に報告した請願の件数は、平成15年度5件のうち0件、平成16年度2件のうち1件、平成17年度8件のうち5件、平成18年度5件のうち4件、平成19年度9件のうち6件、平成20年度11件のうち5件、平成21年度20件のうち10件、平成22年度8件のうち0件、平成23年度22件のうち12件、平成24年度3件のうち0件、平成25年度382件のうち180件、平成26年度20件のうち12件、平成27年度45件のうち35件、平成28年度11件のうち1件で、合計551件のうち271件です。
なお、平成24年度下半期分から半期ごとに、提出された請願の件数及び主な内容について、都教育委員会定例会に報告しています。
また、平成28年10月分から毎月、当該月に提出された請願の件数及び主な内容について、都教育委員に資料配布により報告しています。
A2 平成15年度から平成28年度までに、都教育委員会に提出された請願のうち、都教育委員会定例会及び同臨時会に報告して議論した請願の件数は、271件です。
主な内容は、東京都教育委員会による特定教科書の採択排除に抗議し撤回を求める請願、「東京都教育委員会請願処理規則」の一部改正を求める請願、「はだしのゲン」を学校図書室(館)から排除する請願、都立中高一貫校・特別支援学校の教科書採択に関する請願、都立高校定時制の存続を求める請願などです。
A3 平成22年から平成23年にかけて4回、ほぼ同じ陳情者や陳情団体から、都教育委員会の請願制度に関して、請願者の声を直接担当主管課が聴くようにするほか、請願内容を都教育委員会定例会で審議すること等を求める内容の陳情が、都議会に提出されました。
これらの陳情については、文教委員会において審議された結果、いずれも不採択になったものと認識しています。
A4 都教育委員会に提出された請願については、「東京都教育委員会請願処理規則」、「東京都教育委員会請願取扱要綱」、「東京都教育委員会事案決定規程」等に基づき、都教育委員会決定とされる特に重要な事項は、都教育委員会定例会に報告し、決定しています。
また、既に都教育委員会で決定された教育施策の基本方針等に基づく事項に係る請願については、「東京都教育委員会請願取扱要綱」、「東京都教育委員会事案決定規程」等に基づき、主管課において当該事案について決定権限を有する者が適正に処理しています。
なお、こうした取扱いについては、都教育委員会定例会において議論し、決定しています。
A5 平成23年12月に提出された東京都教育委員会請願処理取扱要綱の廃止を求める請願については、「東京都教育委員会請願取扱要綱」、「東京都教育委員会事案決定規程」等に基づき、主管課において当該事案について決定権限を有する者が適正に処理しました。
その後、平成25年10月及び同年11月に提出された、請願の全てを都教育委員会定例会で審議するよう規則の一部を改正することを求める東京都教育委員会請願処理規則の一部改正を求める請願について、平成25年12月19日に開催した都教育委員会定例会において審議し、「東京都教育委員会請願処理規則」及び「東京都教育委員会請願取扱要綱」を変更する必要はないことを決定しています。
A6 請願の処理に当たっては、全ての請願を収受するとともに、請願者に対して迅速かつ誠実に回答しており、現在でも請願者の声を教育行政に反映した制度となっています。
このため、「東京都教育委員会請願処理規則」及び「東京都教育委員会請願取扱要綱」を見直す必要はないと考えています。
A7 都教育委員会に提出された請願については、「東京都教育委員会請願処理規則」、「東京都教育委員会請願取扱要綱」、「東京都教育委員会事案決定規程」等に基づき、都教育委員会決定とされる特に重要な事項は、都教育委員会定例会に報告し、決定しています。
また、既に都教育委員会で決定された教育施策の基本方針等に基づく事項に係る請願については、「東京都教育委員会請願取扱要綱」、「東京都教育委員会事案決定規程」等に基づき、主管課において当該事案について決定権限を有する者が適正に処理しています。
なお、こうした取扱いについては、都教育委員会定例会において議論し、決定しています。
A8 都教育委員会定例会での審議内容の充実と効率化の観点及び都民サービスの迅速化の観点から、「東京都教育委員会請願処理規則」及び「東京都教育委員会請願取扱要綱」を定め、都教育委員会に提出される全ての請願を誠実に処理しています。
A9 都教育委員会に提出された請願については、「東京都教育委員会請願取扱要綱」に基づき、広聴を所管する教育庁総務部教育情報課が収受し、請願者から請願の趣旨、意見及び要望を聴取し、その内容を文書にまとめ、請願書とともに事業の主管課に送付しており、請願者の意図は主管課に適切に伝えています。
請願書を受理した主管課は、その内容を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知しています。
以 上
2017年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 特別支援学校の教室不足問題等について
一 特別支援学校の教室不足問題等について
特別支援学校の教室不足は大変深刻です。東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画には、増改修等が3校、新設校4校、そのうち北多摩地区に特別支援学校(仮称)を調整中となっていることは重要です。
私は7月11日、羽村特別支援学校を視察しました。5年前に改築していますが、教室不足によるカーテン教室は26教室。しかも、給食は500食の規模を超え、職員全員に提供できない状況になっているということも明らかになりました。
羽村特別支援学校の学区エリアは、6市2町(青梅市・福生市・東大和市・立川市・武蔵村山市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町)です。東大和市内からは76人が在籍しています。スクールバスで1時間以上かかる児童・生徒は、東大和市だけでも19人でした。
今後の児童の推移は、毎年増加することが明らかであり、羽村特別支援学校の教室不足に対する支援が急務となっています。
東大和市議会で、都営住宅向原アパートの建て替えにかかわる資料要求のなかで都立特別支援学校の建設計画が明らかになりました。
Q1 北多摩地区特別支援学校(仮称)の新設は東大和市の都営住宅向原アパートの都有地活用で実現することを求めるものです。しかし、都営住宅向原アパートの地域は、住宅しか建てられない地区計画があり、特別支援学校をつくるためには、都市計画の変更が必要になるため、東大和市は都内で他に活用できる都有地があるのであれば、他を活用すべきだと市議会でも発言しています。都内で羽村特別支援学校の教室不足解消に資する特別支援学校の新設ができるような都有地はあるのですか。
Q2 羽村特別支援学校の教室不足への対策を早急に行うべきですが、都の認識を伺います。
Q3 羽村特別支援学校の給食の規模を増やし、児童・生徒、職員の給食がまかなえるよう改善すべきですが、都の認識を伺います。また、今後の具体的な対策について、伺います。
Q4 スクールバスで1時間以上かかる児童・生徒がいます。スクールバスのルートの改善やスクールバスを増やすなど改善し、通学時間の改善を行うべきですが、いかがですか。
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書
一 特別支援学校の教室不足問題等について
A1 特別支援学校を新設する際には、一定規模の大きさがあり、接道条件が良いなどの条件を満たした土地が必要となります。
都教育委員会では、羽村特別支援学校の教室不足の解消や今後見込まれる児童・生徒数の増加等に対応するため、北多摩地区において北多摩地区特別支援学校(仮称)の設置を計画しています。
現在、学校設置の条件に合う都有地が所在している自治体と設置に向けた調整を行っています。
A2 都教育委員会は、羽村特別支援学校の近隣の学校整備を行うことで、羽村特別支援学校の教室不足を解消していくこととしています。
新たな特別支援学校が整備されるまでの間は、羽村特別支援学校において、間仕切りや特別教室からの転用により、普通教室を確保していくこととしており、教室の間仕切りについては、条件に合う場合、遮音性の高い可動式パーテーションを整備していくこととしています。
A3 羽村特別支援学校の給食については、教育の特殊性に鑑み、児童・生徒の心身の健全な発達に資するよう、在籍する児童・生徒と給食指導を行う教職員に提供しており、必要な給食は実施しています。
なお、給食指導に関わっていない教職員については、給食を提供しておらず、現在、当該教職員への給食を提供するための施設の整備は予定していません。
A4 都教育委員会は、学校からのヒアリングを踏まえ、バスの小型化やコース設定の工夫等により計画的に特別支援学校のスクールバス乗車時間を短縮し、児童・生徒の通学負担の軽減を図っています。
以 上
質問事項
一 小・中学校における発達障害教育推進について
一 小・中学校における発達障害教育推進について
東京都は、すべての公立小中学校への特別支援教室設置をすすめています。これまでの通級指導学級でおこなってきた特別な指導(個別指導と小集団活動)を、在籍校で受けられるようにし、これまでより多くの発達障害の児童・生徒が必要な指導を受けられるようにする、巡回教員と学級担任の連携も密にしていくと説明しています。
東京都教育委員会が2014・2015年度に行なった調査では、通常の学級に在籍する発達障害と考えられる児童・生徒の在籍率は、小学校で6.1%、中学校で5.0%となっています。こうしたことからも、多くの児童・生徒に必要な支援をしていくということは重要です。しかし、同時に課題も出てきています。
「ある時間だけ、別の教室に移動して指導を受けることができない、つらい」「行きたくない」「通級指導学級では、朝から夕方までだったので、まず体をほぐす体育からはじまり、だんだんと落ち着いて勉強ができたが、短い時間だけ場所を変えて指導を受ける支援教室は対応できない」「通級指導学級では、子どもの特性をみて、先生が適切なグループ分けもしてくれての小集団活動により、仲間のなかで自信をつけていけたが、支援教室では事実上、小集団活動が十分保障されず不安定になっている」「通級指導学級に週1回通うことで、1週間在籍校でがんばれたが、拠点校での指導、特別支援教室、通常学級の3ヶ所で過ごすことに無理があり、情緒障害固定学級にうつった」など、たくさんの声が寄せられています。
特別支援教室実施に伴い、どのように発達障害教育を推進するかは、区市町村それぞれ工夫もしながら進めており、違いがあります。拠点校での指導を毎週受けられる自治体もあれば、そうでない自治体もあります。大事なのは、どの児童・生徒も必要な指導が受けられることであり、今出てきている声や課題については各自治体まかせにせず、特別支援教室を推進している東京都としてどうしていくかが問われています。そこでうかがいます。
Q1 特別支援教室が、児童・生徒にとって、安心して過ごせるスペースになるように、環境整備が必要です。現在、東京都公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助事業は、1校あたりの補助上限が、簡易工事費70万円、物品購入費30万円となっていますが、現場からはこれでは不足しているとの声があがっています。現場からの声を十分に聞いて、抜本的に補助の強化をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
Q2 特別支援教室で、一人ひとりに応じた指導、小集団活動が保障されるように、巡回指導教員の増員が必要です。通級指導学級から特別支援教室に移行するにあたり、現状より教員の配置が減ることになります。2020年度までは経過措置がありますが、その後、教員配置が後退することのないようにしていただきたいと考えますが、いかがですか。
Q3 東久留米市では、今年度、小学校の自閉症・情緒障害固定学級の在籍人数が、30人。そのうち、11人が1年生という状況になっています。昨年度と比べて8人も増えています。特別支援教室を推進してもそれだけでカバーできるわけではないことがよくわかります。固定学級増設に向け、東京都はどのような支援ができますか。
Q4 小学校の固定学級人数がふえているもとで、中学校にも固定学級をつくる必要性はますます高まっています。東久留米市では、「東久留米市特別支援教育推進計画」において、「小学校の固定学級(自閉症・情緒)の状況について継続して調査・研究を行い、小学校への新たな設置や中学校への設置についての検討を行う」と位置づけています。小学校で増えているということはその受け皿である中学校にも固定学級をつくる必要があります。しかし、財政的な面からも、小学校への増設と中学校への新設を、同時にすすめていくことは困難な課題です。
「東京都発達障害教育推進計画」には、さらに検討を要する取組として、「区市町村における自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)の設置に向けた支援」として、「通常の学級で指導を受けることが困難な発達障害の児童・生徒に対し、障害の状態に応じた適切な指導を行うため、区市町村が必要に応じて固定学級を設置できるよう、方策を検討します」とあります。問題は、いったいどういう方策になるのかがわからないことです。そのため、財政力が厳しい自治体としては、なかなか、踏み切れないという実態があります。具体的に、どのような方策、支援を検討しているのか、明らかにしてください。
Q5 東久留米市では、中学校に自閉症・情緒固定学級がないため、小学校卒業後の進路は、50%が知的固定学級、30%が私立中学校、20%が通常学級となっています。ふさわしい場所がなく、不登校になるケースもあります。東京都全体で、このような調査はやっているでしょうか。一人ひとりの発達障害の児童・生徒が、どのような道筋をたどって中学を卒業し、どのような進路選択をしていくのか、調査し、公表してください。
原のり子議員の文書質問に対する答弁書
一 小・中学校における発達障害教育推進について
A1 公立小・中学校に係る施設整備については、原則として設置者である区市町村がその経費を負担することとされています。
特別支援教室の導入に当たり、都教育委員会は、区市町村に対し、教材等の物品購入に要する経費について1校当たり30万円と、教室環境の整備に要する簡易工事相当の経費について1校当たり70万円を、それぞれ上限とした金額を補助しています。
この金額を超える施設・設備の整備については、各小学校の実情に応じて設置者である各区市町村が適切に判断し実施しています。
なお、特別支援教室の中学校への導入に当たっては、現在実施しているモデル事業の状況を踏まえて支援体制を検討しています。
A2 小学校の特別支援教室における巡回指導教員については、今後とも、定数配当方針に基づき、適切に措置していきます。
A3 公立小・中学校における特別支援学級の設置については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に基づき、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行うこととされています。
都教育委員会は、区市町村教育委員会の求めに応じて、必要な助言をしています。
A4 都教育委員会は、区市町村が固定学級を設置する際、設置に向けてのスケジュール、必要な手続、障害の状態に応じた特別な教育課程の編成などの相談に対して助言を行うことで、設置意向のある区市町村を支援しています。
A5 都教育委員会は、都立特別支援学校高等部の受入計画策定等の基礎資料とするため、自閉症・情緒障害特別支援学級(固定)及び情緒障害等通級指導学級(通級)を含め、公立小・中学校の在籍学級別の卒業者の進路状況について、平成27年度以降毎年、調査を実施しています。
調査結果は、個人が特定されるおそれがあること等から公表はしませんが、区市町村教育委員会等からの求めがあれば、個人が特定されないよう配慮した上で情報提供しています。
以 上