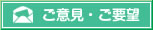主な活動
第4回定例会に提出した文書質問
第4回定例会で、以下の文書質問を提出しました。
- 畔上三和子(江東区選出) 混合介護について
- 白石たみお(品川区選出) 待機児童対策について
- 大島よしえ(足立区選出) 東京都建築安全条例について
- 清水ひで子(八王子市選出) 八王子市川町の(仮称)スポーツパーク建設計画について
文書質問 混合介護について
2016年12月13日 あぜ上三和子(江東区選出)
一 混合介護について
知事は、今定例会の所信表明において「10月には、都庁内に東京特区推進共同事務局を立ち上げ、その具体策として、今後、介護サービスの充実や介護職員の待遇改善にもつながる混合介護の弾力化など検討を進める」と表明されました。
1 東京特区推進共同事務局を立ち上げ検討を進めるとした「混合介護の弾力化」とは、具体的にどういうことを考えているのですか。また、都民から「混合介護」の要望があるのですか。
この間、混合介護については国の動きが加速しています。9月5日に公正取引委員会が介護分野に関する調査報告書を発表していますが、その中で「混合介護」が提案されていて、その具体例として、利用料金の自由化やホームヘルパーの指名料を徴収できるなどとしています。介護分野の規制を外し市場競争にゆだねれば介護サービスの供給量がふえ、介護の質、利用者の利便性、事業者の採算性も介護労働者の賃金まで上がると報告書ではその期待を書いています。
また、10月6日、国の規制改革推進会議において混合介護の議論を深めるという発言を大田議長がしたと報道されています。
本会議において知事は「さまざまな意見がある」としながらも「検討しモデル実施をすすめたい」と表明されました。
介護の各区分に限度額が設けられている区分支給限度基準額に比べ利用額の割合についての都内要介護者の状況は、利用額の割合が3割から、一番多い介護5で7割弱となっています。制度はあるけれど負担できないから使えないというのが都内の要介護者の実態ではないでしょうか。
昨年度東京都がおこなった福祉保健基礎調査では、高齢者の約4割が年収150万円未満、世帯の家計もほぼ毎月赤字、ときどき赤字をあわせると約4割にのぼりました。
2 介護保険の利用料負担に加えて新たなメニューを別料金で使えるようになるといっても、保険外部分は10割負担ですから、手が出せるのはごく一部ではありませんか。その点、都は、どのように考えますか、見解を伺います。
広範な高齢者に貧困が広がる中で、国政・都政が責任をもって、誰もがお金の心配なく、必要な介護が受けられるようにすることこそ、求められているのだと考えます。先日公表された都民生活に関する世論調査でも、都政への要望のトップは、昨年よりも4ポイント増加して高齢者対策です。
3 都は、高齢者の生活実態、都民要望について、どう受け止めていますか。必要な介護は公的に保障し、可能な負担で利用できるようにする事が重要と思いますが、見解を伺います。
この間の介護報酬の引下げ等で、介護の現場では職員の処遇改善も困難な中で、事業を継続できないなど深刻な事態が生まれています。また、東京都社会福祉協議会・東京都高齢者福祉施設協議会がおこなった介護保険制度改定にともなう利用者への影響調査報告では「削減と抑制を求めるだけでなく、負担を強いられた高齢者・家族をフォローする新たな施策も早急に検討すべきと考える」としています。
そうしたなかで都が国と一緒になって介護分野の規制を外し市場競争にゆだねることは、介護の利用の格差を広げ、公的介護保険制度の充実を求める都民の願いにも逆行するものと言わざるを得ません。
4 混合介護の検討の撤回を求めますが、伺います。
いま、安心して受けられる介護が切実に求められています。そのためには介護報酬を引き上げ介護施設整備と介護職の処遇改善に努めることと、負担可能な介護保険料・利用料に軽減をはかることです。しかし、安倍政権は、来年度から、高齢者の更なる介護負担増などを計画しています。厚生労働省の社会保障審議会は介護保険部会をひらき、介護保険制度の見直し案づくりに向け、意見が取りまとめられました。要介護1、2の人に対する生活援助サービスを保険対象からはずすことや、福祉用具貸与の全額自己負担化などについては、反対世論と運動に押されて見送りとなりました。しかし、自己負担の3割負担への引き上げなどサービス抑制に向けて負担増や給付減が検討されています。これ以上、公的介護サービスが縮減され、負担が重くなったら、高齢者をはじめ国民の暮らしに大打撃です。
5 介護の負担増・給付減政策を国民に押し付けることは、介護の公的制度を崩壊させることになると思いませんか。また、国に対し、介護保険制度の国民負担強化につながる見直しはやめるよう求めるべきではありませんか。
平成28年第四回都議会定例会
畔上三和子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 混合介護について
1 東京特区推進共同事務局を立ち上げ検討を進めるとした「混合介護の弾力化」とは、具体的にどういうことを考えているのか伺う。また、都民から「混合介護」の要望があるのか伺う。
回答
「混合介護」の弾力化の具体例としては、現行の介護保険制度では認められていない、保険内サービスと保険外サービスの同時・一体的な提供や、公定価格以外の指名料の設定などが考えられます。
「混合介護」に関しては、様々な意見があることは承知しており、具体的な内容については、広く関係者から意見を聴取しながら検討していきます。
質問事項
一の2 介護保険の利用料負担に加えて新たなメニューを別料金で使えるようになるといっても、保険外部分は10割負担であるから、手が出せるのはごく一部ではないか、都の見解を伺う。
回答
「混合介護」の弾力化が認められることにより、事業者が創意工夫を行う幅が広がり、利用者の利便性やサービスの質の向上、ひいては介護職員の待遇改善にもつながることが期待されます。
具体的な内容については、広く関係者から意見を聴取しながら検討していきます。
質問事項
一の3 都は、高齢者の生活実態、都民要望について、どう受け止めているか。必要な介護は公的に保障し、可能な負担で利用できるようにする事が重要だが、見解を伺う。
回答
高齢者対策は、平成28年度の「都民生活に関する世論調査」において、東京都に特に力を入れて欲しい対策のトップに挙げられているなど、都政の重要な課題と認識しています。
都は、高齢者の介護を社会全体で支え合う介護保険制度の安定的な運営に努めるとともに、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいます。
質問事項
一の4 都が国と一緒になって介護分野の規制を外し市場競争にゆだねることは、介護の利用の格差を広げ、公的介護保険制度の充実を求める都民の願いにも逆行するものと言わざるを得ず、混合介護の検討の撤回を求めるが、見解を伺う。
回答
「混合介護」の弾力化に当たっては、広く関係者から意見を聴取しながら検討を進めていきます。
質問事項
一の5 介護の負担増・給付減政策を国民に押し付けることは、介護の公的制度を崩壊させることにならないか。また、国に対し、介護保険制度の国民負担強化につながる見直しはやめるよう求めるべきだが、見解を伺う。
回答
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う社会保険制度であり、将来にわたり持続可能なものとしていく必要があります。
都は国に対し、利用者負担の見直しに当たっては、低所得者に配慮するとともに、過度の負担が生じないようにすることを提案要求しています。
以上
文書質問趣意書 待機児童対策について
2016年12月13日 白石たみお(品川区選出)
一 待機児童対策について
東京都は「待機児童解消に向けた緊急対策」の中で、新たな支援策を2017年度予算案に反映するとしています。区市町村や保育の現場の実情に応じたきめ細かな支援が求められます。そこで質問します。
1 東京都が行った「待機児童解消に向けた緊急対策活用意向調査」では、待機児童解消区市町村支援事業について、補助率のかさ上げの要件を自治体の規模を考慮したものにしてほしいという意見が複数の自治体から出されています。
同事業では、〔1〕当該区市町村の区域における4月1日現在の0歳児から2歳児までの待機児童数の合計以上の保育所等の定員の拡充を行う、〔2〕0歳児から2歳児までの保育所等の定員について、150人以上の拡充を行う、〔3〕0歳児から2歳児までの保育所の利用児童数を100人以上増やす、という要件を定め、これを一つ満たした場合は補助率が引きあがり、二つ満たすとさらにかさ上げされます。
このうち〔2〕と〔3〕は人口の多い自治体に有利な条件となっています。それは、保育の定員や利用児童を同じ人数増やす場合、人口の少ない自治体ほど、住民にとっての意義も、財政的な重みも大きくなりますが、一律の基準になっているからです。
そして、「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」によれば、今年1月1日時点で23区のうち人口20万人を下回る自治体は3つだけですが、逆に多摩26市で人口20万人以上の自治体は4つしかないなど、多摩の自治体は区部と比べて人口が少ない傾向にあります。そのため、結果的に多摩の自治体で条件を満たしにくくなっています。しかも、多摩の小規模な自治体は財政力も相対的に弱いところが少なくありません。かさ上げ条件の見直しを求める意見が出されたのも多摩の自治体からでした。
そこで、自治体からの要望に応え、待機児童解消区市町村支援事業における補助率かさ上げの条件を自治体の規模を考慮したものに見直す必要があると思いますが、都の考えをうかがいます。
2 借地料への補助について、今年度の補正予算で補助率や上限額が引き上げられたのは重要です。一方で補助の期間は5年間となっています。
先日開かれた「待機児童解消に向けた緊急対策会議」では、世田谷区の保坂展人区長から期間を延長してほしいという要望が出されました。認可保育園の運営は長期にわたって継続するものであり、世田谷区は20年間にわたり補助を行っています。都としても補助期間の延長を検討すべきだと考えますが、いかがですか。
平成28年第四回都議会定例会
白石たみお議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 待機児童対策について
1 自治体からの要望に応え、待機児童解消区市町村支援事業における補助率かさ上げの条件を自治体の規模を考慮したものに見直すべきだが、都の見解を伺う。
回答
保育の実施主体は区市町村であり、保育所等の整備費の負担割合は、原則、国が2分の1、区市町村と事業者がそれぞれ4分の1となっています。
待機児童解消区市町村支援事業は、区市町村の保育サービス拡充に向けた取組を更に加速させるため、その取組に応じて、区市町村や事業者の整備費の負担を軽減する補助事業です。
この補助は、都内の待機児童の約95パーセントを占める0歳児から2歳児までについて、〔1〕4月1日時点の待機児童数以上の保育サービスの定員拡充を行うこと、〔2〕150人以上の保育サービスの定員拡充を行うこと、〔3〕認可保育所の利用児童数を100人以上増やすことの三つの要件を設定し、区市町村が保育サービスの拡充に取り組み、要件を満たした場合、区市町村や事業者の負担を最大で16分の1まで軽減するものです。
今後とも、こうした仕組みにより、待機児童解消に向けて積極的に取り組む区市町村を支援していきます。
質問事項
一の2 借地料への補助について、今年度の補正予算で補助率や上限額が引き上げられたのは重要だが、補助期間は5年間である。認可保育園の運営は長期にわたり継続するものであり、世田谷区は20年間にわたり補助を行っている。都も補助期間の延長を検討すべきだが、見解を伺う。
回答
都が実施している借地料に対する補助は、収入のない開設前の工事期間中を含め、経営が安定しにくいと考えられる期間を対象としています。
以上
文書質問趣意書 東京都建築安全条例について
2016年12月13日 大島よしえ(足立区選出)
一 東京都建築安全条例について
1 共同住宅と呼ばれるアパート、マンションは、建築基準法では特殊建築物に位置づけられていて、住宅棟の一般的な建築物に比べて、防火対策などの規制が強化されています。ところが近年、「重層長屋」とよばれる、共同住宅と同規模な集合住宅が増えていますが、共同住宅とは違う規制がかけられています。重層長屋と共同住宅の定義はそれぞれどのようなものか。また規制の違いは何か伺います。
2 東京都建築安全条例では、民家で四方を囲まれている住宅地を分割する場合、道路に2メートル以上接していなければなりません。ところが道路から奥まったところにある敷地については、道路までの通路を確保するため、旗竿形状の路地状敷地が形成されます。共同住宅を含む特殊建築物は建築安全条例第10条で、「特殊建築物は路地状部分のみによって道路に接する敷地に建築してはならない」と明記され原則として路地状敷地には建てられませんが、そのように規制する理由について伺います。
3 一方、多数の人が住む重層長屋は、特殊建築物に含まれないと解釈され路地状敷地に建設可能となっていますが、その理由は何か伺います。
4 共同住宅を含む特殊建築物は、不特定多数の人が利用する建築物であるということから、建築基準法の耐火性能について厳しく規制されています。
しかし、重層長屋は共同住宅に求められている2方向避難経路が不要であり、消防法により消防用設備を設置し、維持しなければならないというような規定はなく、戸建て住宅と同じ規制の扱いとなっています。
重層長屋で火災が起きたらどうなるのか。路地状敷地に建てられた重層長屋は、路地状幅員が2メートル以上あれば建築可能なため、避難通路の幅が狭く、消防車も中まで入れず、火災が周辺に拡大する恐れがあります。路地状部分をはじめとする避難経路に入居者が集中した場合、逃げることも容易でない状況に陥ります。こうした長屋の火災などの安全性について、どのように認識していますか。対策はどのように確保するのか伺いたい。
5 路地状敷地が不動産業界でにわかに注目を集め、土地の有効活用ができると宣伝され、重層長屋の建設が増えています。都として都内に建築された路地状敷地における重層長屋の件数について把握していますか。
6 重層長屋が建築されることにより、防災問題、通風・採光など環境問題で近隣住民の不安や苦情が高まり、深刻な建築紛争が起きています。都は、都内における路地状敷地におけるこうした長屋についての周辺住民をはじめとした都民の声について、どのように把握しているか伺いたい。
7 現在、足立区西竹ノ塚で、同一敷地内に木造2階建て32戸と30戸のロフトつきの長屋が2棟建設されることになり、住民の間に不安が広がっています。敷地面積も1000平方メートル以上あるものを2つに分割し、高さも10メートル以内ぎりぎりに押さえて開発行為の届けも免れています。
しかも、路地状敷地に入る道路幅員は、建築基準法第42条2項道路で、1.8メートル程度の狭さです。長屋建築敷地先から法第42条1項道路に接道するまでの「道」の両側を道路上に築造され、幅員4メートルを確保された状態の道路でなければならないのに、現況の長屋の建築敷地先だけを道路上に築造しても幅員4メートルを確保した状態にはならず、都建築安全条例4条に言う「道路」扱いにはならないと思いますがどうですか。
8 62戸もの重層長屋であっても、都の建築安全条例で言う特殊建築物とは異なり、規制の対象から外れています。災害時の避難や防犯、環境整備を考慮して長屋の建築できる住戸数の制限を都建築安全条例でするべきではないですか。
9 長屋と共同住宅はどちらも集合的に住む用途です。使用上は共同住宅と同じであるのに、建築安全条例で共同住宅に適用される防火規定や避難規定がなく、発災による地域への影響を低減させる規制も少ないのです。共用部の有無だけで長屋と、共同住宅の規制を変えたことが最大の原因になっているのではないでしょうか。同じ集合的に住む用途の重層長屋も都建築安全条例を見直し、重層長屋は特殊建築物に指定し、共同住宅と規制をそろえることを検討すべきではありませんか。
平成28年第四回都議会定例会
大島よしえ議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 東京都建築安全条例について
1 近年、「重層長屋」とよばれる、共同住宅と同規模な集合住宅が増えているが、共同住宅とは違う規制がかけられている。重層長屋と共同住宅の定義はそれぞれどのようなものか伺う。また規制の違いは何か伺う。
回答
日本建築行政会議による定義によれば、重層長屋を含む長屋は、「隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建築物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有しない形式のもの」、共同住宅は「隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建築物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有する形式のもの」です。
東京都建築安全条例上の規制に関する違いは、敷地の接道条件などがあります。
質問事項
一の2 共同住宅を含む特殊建築物は建築安全条例上、原則として路地状敷地には建てられないが、そのように規制する理由を伺う。
回答
東京都建築安全条例において、共同住宅を含む特殊建築物は、火災発生のおそれが大きく、廊下・階段等を各住戸で共有するため避難上の制約があることなど、安全上及び防火上の観点から、路地状敷地の建築制限をしています。
質問事項
一の3 多数の人が住む重層長屋は、特殊建築物に含まれないと解釈され、路地状敷地に建設可能となっているが、その理由を伺う。
回答
長屋については、容易に各住戸の出入口から直接屋外へ出られることに加え、各戸の主要な出入口を道路又は道路に通ずる幅員2メートル以上の敷地内の通路に面するように規定することで、避難上の安全性が確保されることから、路地状敷地に建設可能となっています。
質問事項
一の4 重層長屋で火災が起きたらどうなるのか。路地状部分をはじめとする避難経路に入居者が集中した場合、逃げることも容易でない状況に陥るが、こうした長屋の火災などの安全性について、どのように認識しているのか伺う。対策はどのように確保するのか伺う。
回答
長屋については、火災時などの避難上及び安全上の観点から、各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員2メートル以上の敷地内の通路に面しなければならないこととしています。
さらに、耐火建築物又は準耐火建築物でない場合については、主要な出入口が通路のみに面する住戸の数は3を超えることができないこととしていることに加え、一定規模以上のものは、路地状部分の長さに応じた幅員の制限を強化する規定を設けています。
質問事項
一の5 路地状敷地が不動産業界でにわかに注目を集め、土地の有効活用ができると宣伝され、重層長屋の建設が増えているが、都として都内に建築された路地状敷地における重層長屋の件数について把握しているのか伺う。
回答
都内の路地状敷地に建築される一定規模以上の重層長屋の件数は、建築確認に関する区市等への調査を通じ把握しています。
質問事項
一の6 重層長屋が建築されることにより、防災問題、通風・採光など環境問題で近隣住民の不安や苦情が高まり、深刻な建築紛争が起きているが、都は、都内における路地状敷地におけるこうした長屋についての周辺住民をはじめとした都民の声について、どのように把握しているか伺う。
回答
都は、区市との建築行政に関する連絡会議などを通じ、長屋についての情報を収集しています。
質問事項
一の7 足立区西竹ノ塚で、同一敷地内に木造2階建て32戸と30戸の長屋が2棟建設されることになり、住民の間に不安が広がっている。路地状敷地に入る道路幅員は、建築基準法第42条2項道路で、1.8メートル程度の狭さであり、現況の長屋の建築敷地先だけを道路上に築造しても幅員4メートルを確保した状態にはならず、都建築安全条例4条に言う「道路」扱いにはならないと思うが、見解を伺う。
回答
当該道は、特定行政庁が建築基準法第42条第2項の規定に基づき指定したものであることから、東京都建築安全条例上の「道路」となります。
質問事項
一の8 62戸もの重層長屋であっても、都の建築安全条例で言う特殊建築物とは異なり、規制の対象から外れている。災害時の避難や防犯、環境整備を考慮して長屋の建築できる住戸数の制限を都建築安全条例でするべきだが、見解を伺う。
回答
東京都建築安全条例では、火災時などの避難上及び安全上の観点から、主要な出入口が通路のみに面する住戸の数が3を超える場合は、少なくとも準耐火建築物としなければならないこととしています。
さらに、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で、一定規模以上のものは、路地状部分の長さに応じた幅員の制限を強化する規定を設けています。
質問事項
一の9 同じ集合的に住む用途の重層長屋も都建築安全条例を見直し、重層長屋は特殊建築物に指定し、共同住宅と規制をそろえることを検討すべきだが、見解を伺う。
回答
長屋については、火災時などの避難上及び安全上の観点から、各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員2メートル以上の敷地内の通路に面しなければならないこととしているなど、長屋の特性に応じた規定を適切に設けているものと考えています。
以上
文書質問趣意書 八王子市川町の(仮称)スポーツパーク建設計画について
2016年12月13日 清水ひで子(八王子市選出)
一 八王子市川町の(仮称)スポーツパーク建設計画について
八王子市川町346番1他の約15.4haに、「特定非営利活動法人 東京スポーツビジョン21」が事業主となって、(仮称)八王子スポーツパークの建設が計画されています。スポーツ施設建設は否定するものではありませんが、建設場所やその手法、住民合意に大きな問題があると考え、以下の点について質問します。
この計画は、八王子市西部の川町地区で、市内に公的スポーツ施設が不足しているという理由で、山林を伐採し、谷戸を残土で埋立て、サッカー場2面、野球場1面、テニスコート3面、アーチェリー場等をつくるというものです。
建設予定地の貴重な谷戸は、約55万の大量の建設残土で埋め立てられてしまうことになります。搬入で地域内に入ってくる車両は、10トントラックで12万台にも及び、1日あたり130台と予測されています。地域住民の生活環境悪化も強く懸念されています。
川町周辺は、都立高尾陣場自然公園の一角にあり、豊かな緑に恵まれた地域です。地域住民は突然の(仮称)スポーツパーク建設に数多くの疑問を持ち、同時に、大切な緑の喪失と希少種とされている動植物の絶滅をまねく結果となる、この残土埋立ての方法による(仮称)スポーツパーク建設は、中止して欲しいと要望しています。
東京の緑、特に多摩地域の緑は、減少の一途を辿っています。自然環境を保全する東京都の努力を求めて、以下、質問します。
当初は計画地に、トラックターミナルが建設される予定だったのが、2014年から、スポーツ施設建設へと計画が変更になりました。事業主は、「特定非営利活動法人 東京スポーツビジョン21」と、都南建設株式会社、新開工業株式会社です。スポーツ施設建設は、谷戸埋立の建設残土受け入れは、新開工業株式会社が中心に事業にあたるとのことです。
2012年9月に、事業主が行なった住民への説明によると、建設残土は「株式会社 建設資源広域利用センター」(UCR)から受け入れますが、事業主には1あたり1940円の受け入れ料がUCRから支払われる試算ですから、55万の受け入れとすると10億6700万円になります。
トラックターミナルに比べて、住民が反対しづらいスポーツ施設建設を名目にした、残土処理の事業ではないか、と強い疑問の声があがっています。
1 説明会で、3社共同の事業体の1つである「特定非営利活動法人 東京スポーツビジョン21」の代表者は、自らの名前で書いた事業計画説明書では、工事代金(2億)は協力企業、協賛企業により無担保無利子にて協力をいただく予定です」としているにもかかわらず、説明会では「協力企業の自己資金2億円や土地購入費など、これまでのお金の流れについて全く関知していない」と発言するなど資金計画についての理解がうたがわれ、人材などに照らしてみても、当事者としての能力がはっきりせず、共同事業者としての実態そのものが疑われています。このような事業体が、15.4haもの大規模な開発行為にあたることについて、東京都はどのような判断をお持ちですか。お答えください。
2 また本年10月23日の事業者開催の住民説明会において、事業主は住民に対し、「土砂搬入する財源は考えないで下さい。融資証明、残高証明を出すように八王子市から言われている」と事業者の資金計画について、誠実に説明しようとしていません。資金計画についても住民の問いに答えるべきと考えますが、東京都は、どのような見解をお持ちか、伺います。
3 土砂の搬入をする10トントラックが1日に130台も入って来れば、生活環境に大きな影響を及ぼします。1日に往復260台の通行になります。
当該地には、現在、都道が存在していますが、幅員は広くありません。事業者は、この道路の拡幅と開発地域内に新たな道路をつくる予定にしていますが、これまで生活道路として、車両通行も限られた数だった川町に土砂を積載した大型ダンプが大量に入ってくれば、騒音、振動、空気の汚染などの環境悪化に加えて、交通事故の発生も心配されています。
事業者は騒音、振動、大気汚染について、どのような対策を講じようとしているのですか。
また都は、生活環境の変化について、どのような認識をお持ちか、お答えください。
4 八王子市市街化調整区域の保全にむけた適正な土地利用に関する条例は事業の60%は緑地を残さなければならない、としています。事業主は、八王子市の条例を遵守する、自然環境を破壊するものではない、と説明しています。しかし、限りない自然破壊につながる開発である懸念は拭いきれません。4割の面積の緑がなくなり、高さ38メートルにおよぶ建設残土で埋め立てられる事業によって、この地域に生息している多くの動植物の生息が危ぶまれる事態となります。
特に、東京の区部では絶滅し、多摩地域の中でも、八王子市の当該事業予定地域でしか確認されていない、絶滅が危惧されているシダ類が生息していることは、重視されなくてはなりません。
2014年9月、事業主が行なった住民説明会の資料によると、事業区域内の大径木は12種108本を確認、注目種とされている植物、鳥類、爬虫類、昆虫、魚類、底生動物は69種を確認、その他周辺区域には、1700種を超える動植物が生息していると報告されています。
大規模な樹木の伐採と建設残土埋立で、これらの種が絶滅する事態を招きかねません。生物多様性の大事さが強調されている今日、東京都は、種の保存について、どのようなお考えを持って、開発に対応されるのでしょうか。お答えください。
5 埋立計画地域は、建設局が、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域に指定している箇所が存在します。傾斜が急で、土砂崩壊が起こりやすい場所だからこその指定ですが、この地域の木々を切り、38メートルの高さで建設残土を積み上げる事業が行なわれることは、事業地域の安全性を大きく損なうものではないでしょうか。建設局が、土砂災害警戒区域、特別警戒区域に指定したのは、どのような判断に基づくものでしょうか。また、大量の建設残土の埋立で、地盤の安全性は確保されるのでしょうか。東日本大震災では、盛り土した地盤が崩壊していますし、都内でも荒川のスーパー堤防地域でも盛り土が崩れたりしています。土砂埋立の地盤は安全ではないと考えます。東京都のご見解を、それぞれお示しください。
6 事業区域内の周辺に、保安林があると聞いていますが、保安林は、どのようなものでしょうか。お答えください。
7 保安林又は保安林に隣接する土地で、木々を伐採し、大量の盛り土をする場合、保安林制度上どのような規制があるか、伺います。見解をお聞きします。
8 事業予定地内は、大沢川の源流です。樹林帯には、細い水流があり、下流に向かって水を集め、大沢川となります。この源流の谷戸を建設残土で埋め立てると、水源はどうなるのでしょうか。事業者は、管路を作るなどのことを提案しているようですが、水源が確保される保障は不透明です。
大沢川の源流を保存することについて、いかがお考えでしょうか。お答えください。
9 水源の守られない場合、事業区域内の水生植物や動物が生息している湿地帯はなくなってしまいます。事業主は、この場所をビオトープとする、と説明しているようですが、自然の流水とは異なる流れになった場合、その保障はありません。この点についてのご見解もお聞きします。
10 都市整備局にお聞きします。都内では、水道管や下水道管の敷設工事で建設残土が発生しています。また、外かん道の建設や超高層ビル建設の開発行為で大量の建設発生土が出ています。
都市整備局が把握している都内工事によって生じる建設発生土の実績をお示しください。
11 建設残土の発生を抑制しないと、残土処理の能力が限界を超えることが予測されます。現在でも、建設残土の再利用を名目に、八王子市をはじめとした多摩の山間部などで、谷戸の埋立工事が行なわれ、緑が失われています。都内で一団の緑の塊をなしている多摩地域の自然を守るのは、地球温暖化や大気汚染を防止し、都民生活の安らぎを守る都政の大事な仕事です。
現在、リニア新幹線建設工事も浮上しているおり、さらに建設残土の発生量増加が懸念されていますから、発生抑制の対策を講じることが重要です。
都は、建設残土の発生抑制に向けて、努力されるよう求めます。いかがでしょうか。
12 八王子市議会では、川町地域を中心とした市民の「自然と生活環境を守りたい」との願いを受けて、この4年余、(仮称)スポーツパーク建設計画が市政をめぐる重要な課題となっています。
幅広い市民の運動と、議会では党派を超えて(仮称)スポーツパーク建設計画は、撤回、見直しをと求めています。
この事業計画は、東京都自然環境保全審議会の審議にかかることが見込まれます。審議にあたっては八王子市議会を中心とした地元の意見や要望を踏まえた上で、生物多様性の保全に向けた最善の方策を検討されるよう求めるものです。お答えください。
平成28年第四回都議会定例会
清水ひで子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 八王子市川町の(仮称)スポーツパーク建設計画について
1 資金計画についての理解がうたがわれ、人材などに照らしてみても、当事者としての能力がはっきりせず、共同事業者としての実態そのものが疑われているような事業体が大規模な開発行為にあたることについて、都はどのような判断を持っているか伺う。
回答
都市計画法では、開発行為を許可するに当たり、許可申請者に対し、当該開発行為を行うために必要な資力や信用があることを要件としており、施行規則において資金計画書や事業経歴書等の提出を定めています。
したがって、本件区域の開発行為を所管する八王子市においても、事業者の資力や信用については、許可申請を受けた際にその審査において判断するものと認識しています。
質問事項
一の2 事業主は住民に対し、資金計画について、誠実に説明しようとしていない。資金計画についても住民の問いに答えるべきだが、都の見解を伺う。
回答
都市計画法では、国土交通省の「開発許可制度の運用指針」において「許可権者は、申請者には、周辺住民等に対し開発許可手続きとは別に説明、調整を行うよう、指導することが望ましい」という記載があります。この趣旨を踏まえ、本件区域の開発行為を所管する八王子市が、事業者に対して、周辺住民等に対し事業に関する説明、調整を行うよう、適切に指導を行うものと認識しています。
質問事項
一の3 これまで生活道路として、車両通行も限られた数だった川町に土砂を積載した大型ダンプが大量に入ってくれば、環境悪化に加えて、交通事故の発生も心配されるが、事業者は騒音、振動、大気汚染について、どのような対策を講じようとしているのか伺う。また、生活環境の変化について、都の認識を伺う。
回答
当該開発計画については、現時点で許可申請がされていないため、内容は把握していません。
なお、車両通行に伴う騒音及び振動については、騒音規制法及び振動規制法に基づき市町村長が測定を行い、要請限度の超過により道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、所要の措置を講ずることとされています。
質問事項
一の4 事業主が行なった住民説明会の資料によると、事業区域内の大径木は12種108本を確認、注目種とされている植物、鳥類、爬虫類、昆虫、魚類、底生動物は69種を確認、その他周辺区域には、1700種を超える動植物が生息していると報告されているが、大規模な樹木の伐採と建設残土埋立で、これらの種が絶滅する事態を招きかねない。生物多様性の大事さが強調されている今日、都は、種の保存について、どのような考えを持って、開発に対応するのか伺う。
回答
都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「自然保護条例」という。)に基づき、宅地の造成など土地の形質を変更することで自然環境に影響を及ぼす一定規模以上の開発行為について、知事の許可を必要とする開発許可の制度を設けて運用しています。
開発許可制度では、事業者に一定の緑地面積の確保や、既存樹木等の保護の検討、動植物の生息又は生育についての適正な配慮などを求めており、事業者が許可を受けるためには、これらの要件を満たすことが条件となります。
都は、この制度を適切に運用し、開発行為により損なわれる自然を最小限にとどめるほか、自然が損なわれるおそれがある場合には、その回復を図るよう開発事業者を指導することにより、自然環境の保全に努めています。
質問事項
一の5 埋立計画地域は、建設局が、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域に指定している箇所が存在するが、土砂災害警戒区域、特別警戒区域に指定したのは、どのような判断に基づくものか。また、大量の建設残土の埋立で、地盤の安全性は確保されるのか。都の見解をそれぞれ伺う。
回答
土砂災害警戒区域は、傾斜が30度以上で斜面の高さが5メートル以上の急傾斜地など一定の要件を満たし、かつ、住宅もしくは居室を有する建築物が立地している場合又は平地があり将来住宅等の立地の可能性がある場合において、警戒避難体制を整備すべき土地として指定します。
このうち、斜面の崩壊等により建築物に著しい損壊を生じるおそれがある場合は、住宅分譲や要配慮者利用施設に係る開発行為の制限及び住宅等の構造を規制すべき土地として土砂災害特別警戒区域の指定をします。
八王子市川町においても、現地調査等を行い、これらの要件を満たす箇所を土砂災害警戒区域等として指定したものです。
また、当該建設計画における造成行為による地盤の安全性については、都市計画法や宅地造成等規制法等における許可が必要な場合には、それぞれの法令に基づく審査において確認することとなります。
質問事項
一の6 事業区域の周辺に保安林があるが、どのようなものなのか伺う。
回答
保安林は、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、森林法に基づき、農林水産大臣等によって指定される森林です。保安林に指定されている土地では、立木の伐採や土地の形質を変更する行為等が規制されます。
質問事項
一の7 保安林または保安林に隣接する土地で、木々を伐採し、大量の盛り土をする場合、保安林制度上どのような規制があるのか伺う。
回答
保安林に指定されている土地については、立木の伐採、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為等が規制されています。保安林に指定されていない土地については、保安林の規制は適用されません。
質問事項
一の8 事業予定地内は、大沢川の源流であり、この源流の谷戸を建設残土で埋め立てると、水源はどうなるのか。大沢川の源流を保存することについて、都の見解を伺う。
回答
当該開発計画については、現時点で許可申請がされていないため、内容は把握していません。
なお、自然保護条例施行規則第52条では、土地の造成、土地の形質の変更が必要最小限であり、かつ地形に順応した開発計画であることなどを開発許可の要件として規定しています。
都はこの規定に基づき、原則として、水源域の形質の変更を避けるよう求めており、やむを得ず変更する場合には、周辺の自然環境を考慮の上、水道(みずみち)の確保など十分な配慮を行うよう指導しています。
質問事項
一の9 水源の守られない場合、事業区域内の水生植物や動物が生息している湿地帯はなくなってしまう。事業主は、この場所をビオトープとすると説明しているようだが、自然の流水とは異なる流れになった場合、その保障はない。この点について都の見解を伺う。
回答
当該開発計画については、現時点で許可申請がされていないため、内容は把握していません。
なお、自然保護条例に基づく開発許可では、原則として、行為地の面積が1ヘクタール以上の場合、事業者に自然環境調査を実施させるとともに、調査で把握された動植物については、その生息又は生育について適正な配慮がなされた自然環境保全計画書の提出を求めています。
また、保全計画において、事業者が希少植物を移植して保全に取り組む場合には、許可条件としてモニタリング調査を事業者に義務付けることとして、希少植物の保護にも努めています。
質問事項
一の10 外かん道の建設や超高層ビル建設の開発行為で大量の建設発生土が出ているが、都市整備局が把握している都内工事によって生じる建設発生土の実績を伺う。
回答
都が把握している、都内工事によって生じる建設発生土の実績については、平成24年度で約920万立方メートルです。
質問事項
一の11 都は、建設残土の発生抑制に向けて、努力すべきだが、都の見解を伺う。
回答
都は、建設残土の発生抑制のため、「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき「東京都建設リサイクルガイドライン」を定め、自ら努めるとともに、建設工事において発生する土砂の再使用などに取り組むよう各事業者に求めています。
質問事項
一の12 八王子市議会では、党派を超えて(仮称)スポーツパーク建設計画は、撤回、見直しをと求めている。東京都自然環境保全審議会の審議にあたり、八王子市議会を中心とした地元の意見や要望を踏まえた上で、生物多様性の保全に向けた最善の方策を検討されるよう求めるが、見解を伺う。
回答
都は、3ヘクタール以上の開発行為に対する許可を行う場合には、自然保護条例に基づき、あらかじめ自然環境保全審議会の意見を聴くこととしています。審議会では、自然環境に関する各分野の専門的な視点から審議を行うほか、当該開発行為が行われる区市町村に対して自然環境保全計画書案に関する意見照会を行うなど、地元の意見も参考にしながら審議を行うこととしています。